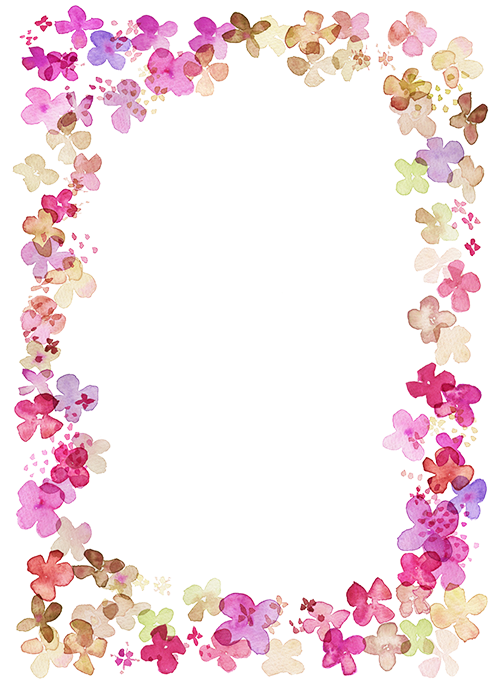(うわ)
となりのビルの1階にあるイタリアンレストランで昼食をゆっくり摂り、販促部のオフィスに戻ったら、
やつがひとりでいたので思い切り回れ右をした。
昼になり天気が回復した。うらうらとした光が大きなガラス窓からさんさんと入って来る。
白壁に白いデザイナーズデスクと椅子と言うオフィスには、いささかまぶし過ぎるくらいの陽気だ。色白の彼の頬もうっすら赤らんでいる。
久しぶりに気持ちの良い天気だが、気分が急降下した。
「何その顔。可愛くないな」
いつの間にか彼が俺の背後に立ち、私を背中からぎゅうっと抱きしめて来る。け、気配をまったく感じなかった!!
「可愛い後輩をあんまりいじめてくれるなよ、先輩」
「ん」
うなじをすうっと舐め上げられ、私は思わず甘い声を漏らしてしまった。腰から背中、首へとゾクゾクしたしびれが這いあがってくる。
この男とは何度か寝た。慣れない外国でひとり暮らすのはさびしかったからだ。
それ以来、彼は私に猛烈なアピールをして来る。気を持たせて悪いと思ってはいるが、
私は特定の相手を作らない派だ。何度もそう言ったのに、彼は一向にあきらめる気配を見せない。
コイツも慣れない外国でさびしいのかな、と、最初は思っていた。
だが、コイツはそんな可愛いタマではない。絶対的な自信があり、常に最高の自己プロデュースをする。そう言う男だ。
「あなた、
俺にかまって欲しくてさっき噛みついたんだろう。しつけのなってない子犬だな」
彼はくすくす笑いながら私にそうささやく。蜜をたっぷりまとったテノールで、吐息まじりに。
私の身体を反転させて壁に押しつける。私があわてて振り返ると、彼は自身のスーツの胸ポケットから何かを取り出した。
(うち、の、新作の、ティントリップ)
どぎつい赤だ。コロンとした丸いフォルムと緑色のフタ。彼の白くて大きな手にすっぽり隠れてしまう。
「な、何をするつもり?」
「あなたの唇にこれを塗る」
「何を言っているの? 私はさっき口紅を塗り直したばっかりだよ。
それに、それ、1度塗ったらなかなか落ちないじゃない」
「そうだ。それがこの商品のセールスポイントだからな」
彼の笑顔が怖い。薄い唇は笑っているが目が笑っていない。
こいつは時々そう言う目で私を見る。見下した目だ。
(女だと思って甘く見るなよ!!)
となりのビルの1階にあるイタリアンレストランで昼食をゆっくり摂り、販促部のオフィスに戻ったら、
やつがひとりでいたので思い切り回れ右をした。
昼になり天気が回復した。うらうらとした光が大きなガラス窓からさんさんと入って来る。
白壁に白いデザイナーズデスクと椅子と言うオフィスには、いささかまぶし過ぎるくらいの陽気だ。色白の彼の頬もうっすら赤らんでいる。
久しぶりに気持ちの良い天気だが、気分が急降下した。
「何その顔。可愛くないな」
いつの間にか彼が俺の背後に立ち、私を背中からぎゅうっと抱きしめて来る。け、気配をまったく感じなかった!!
「可愛い後輩をあんまりいじめてくれるなよ、先輩」
「ん」
うなじをすうっと舐め上げられ、私は思わず甘い声を漏らしてしまった。腰から背中、首へとゾクゾクしたしびれが這いあがってくる。
この男とは何度か寝た。慣れない外国でひとり暮らすのはさびしかったからだ。
それ以来、彼は私に猛烈なアピールをして来る。気を持たせて悪いと思ってはいるが、
私は特定の相手を作らない派だ。何度もそう言ったのに、彼は一向にあきらめる気配を見せない。
コイツも慣れない外国でさびしいのかな、と、最初は思っていた。
だが、コイツはそんな可愛いタマではない。絶対的な自信があり、常に最高の自己プロデュースをする。そう言う男だ。
「あなた、
俺にかまって欲しくてさっき噛みついたんだろう。しつけのなってない子犬だな」
彼はくすくす笑いながら私にそうささやく。蜜をたっぷりまとったテノールで、吐息まじりに。
私の身体を反転させて壁に押しつける。私があわてて振り返ると、彼は自身のスーツの胸ポケットから何かを取り出した。
(うち、の、新作の、ティントリップ)
どぎつい赤だ。コロンとした丸いフォルムと緑色のフタ。彼の白くて大きな手にすっぽり隠れてしまう。
「な、何をするつもり?」
「あなたの唇にこれを塗る」
「何を言っているの? 私はさっき口紅を塗り直したばっかりだよ。
それに、それ、1度塗ったらなかなか落ちないじゃない」
「そうだ。それがこの商品のセールスポイントだからな」
彼の笑顔が怖い。薄い唇は笑っているが目が笑っていない。
こいつは時々そう言う目で私を見る。見下した目だ。
(女だと思って甘く見るなよ!!)