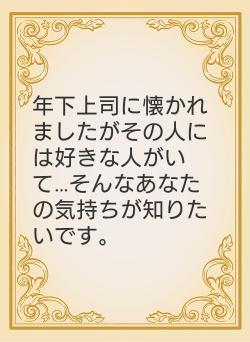「え、これって」
「去年のインターハイ」
「見ていいの?」
「見せたくて持ってきた(笑)パソコン買ったら見たいと思ってて実家から持ってきてたんだ」
テレビの裏側からDVDを入れると2人で見始める。
「この時のダンクかっこよかったよね」
さくらは嬉しそうに解説してくれる。
さっきまで興奮してたのに、急にさくらは話さなくなった。
「さくら?」
「……何回観ても泣いちゃう……」
「何回って、映像持ってんの?」
「決勝戦…少しだけスマホで録画してるの…ごめんなさい、勝手に撮って…」
スマホを見せた。
「遠いし、5分くらいだけどね、グスッ、あっ!」
さくらは雑誌を部屋から持ってきた。
「このカメラマンさん凄い綺麗に遥海くんのシュートを撮影してて私のお気に入りなの……あっ…」
ポロポロとまた涙が出てきた。
「ごめ、ごめんなさい」
遥海は手でさくらの頬を触ると自分の方に引き寄せた。
「泣くなよ、可愛いけどさ」
「遥海くん、私…遥海くんと知り合って疫病神になってない?熱とか怪我とか続いてさ……私はただ遥海くんの力になりたいだけなのに……」
「もう充分なってるよ、さくらは疫病神なんかじゃない」
「だって……ぐすっ……」
「今までの不摂生がたまたまきてんだよ、さくらは関係ない」
頭をポンポンとなでてくれる。
(遥海くん、優しい……)
「遥海くん、足が治るまでここに住まない?」
「それは……さくらにめい……」
「迷惑じゃない、大学も近いしバイトも出来るかどうか病院に行ってみないとでしょ?自転車も乗れないかもだよ?」
「そうだけど……そうなると生活費がさくらに負担になるし、俺、ずっとさくらといたら我慢できなくなりそうだし」
「ご飯を作ってあげたい……ん、我慢?って?」
さくらは遥海を見上げた。
「……っ、さくらを抱きたくなるってこと」
さくらはポカンとしていた。