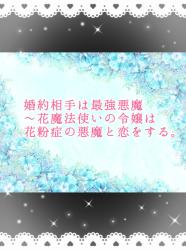外に出るとまだ暗かった。冷たい空気が一気に体を包んでくる。積もりきった雪に街灯の光が反射し、街全体がほのかに光っていた。だけど静かで、眠っているような街。終電を逃した時の瞬間なまま、まるで時間が止まっているみたいだった。だけど、それはただの、私の願望。ふたりの時間の終わりがみえてくる。
――時間が巻き戻ればいいのに。
室内で暖められていた身体の体温が、寒さで急に下がっていく感じがしてきた。
「寒いっ!」と、私が身震いすると「真希さん、大丈夫っすか?」と言いながら、荒木は自分の紺色のマフラーを外す。そしてなんと、私の首にそのマフラーを巻いてきた。そんなことをされるのは一切慣れていないから、倒れそうなくらいに動悸がしてくる。
「いや、いいよ! 荒木の首元が寒くなっちゃう」
「俺、平気っすよ。筋肉あるんで!」
さっきまでの子供みたいな様子とは違い、急に荒木が大人っぽく見えてきた。
「荒木って、本当によく分からないね」
「そうっすか?」
「うん、分からない。無邪気な子供になったり、急に頼れる大人になったり……いつも笑顔なのに闇が深そうだなとか思わせてきたり」
「うれしいっす」
「なんでうれしいの? 何も褒めてないよ?」
「だって、真希さん、俺のことをそこまで見てくれているから……」
「そうかな?」
真剣な表情になった荒木と目が合うと心臓が跳ねる。私は視線をかわすように足元を見た。
「寒いの、大丈夫っすか?」
突然訪れるあたたかい感触。荒木が私のことを抱きしめてきた。
「荒木? これはちょっと……」
「真希さんの体温を上げたいです」
「まだ寒いけど、もう大丈夫だよ」
緊張してきて、私の声が少し震えてくる。荒木を跳ね除けることもできるけれども、このままでいたくて私はされるがまま、荒木に包まれた。
「そろそろ、行きますか」と、荒木の言葉を合図に私たちは離れた。
駅に向かって歩き出す。昨日は比較的暖かかったから、雪が水になり真夜中に凍った歩道は少し滑りやすくなっていた。私は慎重に足を進めた。
荒木は私に合わせて、ゆっくりと歩いてくれた。
大きな雪の粒が、ゆっくりと舞い降りてきた。紺色の空に、白い花が浮かんでいるようで、なんだか幻想的。
「雪が今日は綺麗に感じる」
「俺と過ごしてるからっすかね?」
いつもなら「何言ってるの荒木」なんて笑いながら言葉をかわすだろう。今はそのまま流したくはなかった。
「うん、そうかも……荒木と過ごしてるこの時間、このまま止まっちゃえば良いのにって思っちゃった」と私は声を振り絞り、静かに言った。
「俺も……」
いつもの荒木はテンション高めな声なのに、珍しく低くて柔らかくて、胸にじんわりと響いてくる。
駅に近づくと、ホームの明かりが見えてきた。始発の時間まであと少し。ホームには誰もいない。そしてついにホームに着いた。着いてしまった。
「始発、来ちゃうね」
「なんか……ちょっと寂しいですね。真希さん、手、繋いでいいですか?」
「うん、いいよ」
無言で待つ私たち。言葉はなくても、隣に荒木がいるだけでなんだかあたたかい。手の温もりも、とても安心感を得るようなあたたかさで。そして触れた手を意識していると胸の鼓動が早くなる。
電車のヘッドライトが遠くに見え、ゴーッという音が近づいてくる。いつもはこの風景を見ると、やっと家に帰れるなとほっとした気持ちに包まれるけれど、今日は切なさが胸の奥から溢れてくる。
空にはまだ紺色がほのかに残っていて、薄暗い。雪の降る量が増えてきた。
「今日の雪、大きいよね」
「花弁雪(はなびらゆき)っすね」
「花弁雪って言うんだ……なんか可愛い雪だよね」
私たちは手を繋いだまま電車が来るまでずっと空を見上げていた。
荒木と一緒に残業して良かった。もしも残業がなかったら、いつものように帰宅していたら、お酒をひとりで飲んで、愚痴を頭の中でひたすら呟いて寝るだけだったろうなと思うから。そして荒木と過ごしているこの時間がとても楽しかった。
――それは、もっと、この時間が長く続けば良いのにとおもってしまうほどに、だ。
「本当に荒木といるの、楽しかった。また私と遊んでくれる?」
「遊びましょう。次はきちんと計画立てます!」
「計画立ててくれるんだ、楽しみにしてるから」
頬を突き刺す冷たい風と共に、電車が目の前に止まる。
電車のドアが開くと手を離し、二人で中に乗り込んだ。ドアが閉まると、ふたりきりの幸福な夜が、静かに終わりを告げた。
**.✼ ゜
――この夜を、きっと忘れないだろう。
――時間が巻き戻ればいいのに。
室内で暖められていた身体の体温が、寒さで急に下がっていく感じがしてきた。
「寒いっ!」と、私が身震いすると「真希さん、大丈夫っすか?」と言いながら、荒木は自分の紺色のマフラーを外す。そしてなんと、私の首にそのマフラーを巻いてきた。そんなことをされるのは一切慣れていないから、倒れそうなくらいに動悸がしてくる。
「いや、いいよ! 荒木の首元が寒くなっちゃう」
「俺、平気っすよ。筋肉あるんで!」
さっきまでの子供みたいな様子とは違い、急に荒木が大人っぽく見えてきた。
「荒木って、本当によく分からないね」
「そうっすか?」
「うん、分からない。無邪気な子供になったり、急に頼れる大人になったり……いつも笑顔なのに闇が深そうだなとか思わせてきたり」
「うれしいっす」
「なんでうれしいの? 何も褒めてないよ?」
「だって、真希さん、俺のことをそこまで見てくれているから……」
「そうかな?」
真剣な表情になった荒木と目が合うと心臓が跳ねる。私は視線をかわすように足元を見た。
「寒いの、大丈夫っすか?」
突然訪れるあたたかい感触。荒木が私のことを抱きしめてきた。
「荒木? これはちょっと……」
「真希さんの体温を上げたいです」
「まだ寒いけど、もう大丈夫だよ」
緊張してきて、私の声が少し震えてくる。荒木を跳ね除けることもできるけれども、このままでいたくて私はされるがまま、荒木に包まれた。
「そろそろ、行きますか」と、荒木の言葉を合図に私たちは離れた。
駅に向かって歩き出す。昨日は比較的暖かかったから、雪が水になり真夜中に凍った歩道は少し滑りやすくなっていた。私は慎重に足を進めた。
荒木は私に合わせて、ゆっくりと歩いてくれた。
大きな雪の粒が、ゆっくりと舞い降りてきた。紺色の空に、白い花が浮かんでいるようで、なんだか幻想的。
「雪が今日は綺麗に感じる」
「俺と過ごしてるからっすかね?」
いつもなら「何言ってるの荒木」なんて笑いながら言葉をかわすだろう。今はそのまま流したくはなかった。
「うん、そうかも……荒木と過ごしてるこの時間、このまま止まっちゃえば良いのにって思っちゃった」と私は声を振り絞り、静かに言った。
「俺も……」
いつもの荒木はテンション高めな声なのに、珍しく低くて柔らかくて、胸にじんわりと響いてくる。
駅に近づくと、ホームの明かりが見えてきた。始発の時間まであと少し。ホームには誰もいない。そしてついにホームに着いた。着いてしまった。
「始発、来ちゃうね」
「なんか……ちょっと寂しいですね。真希さん、手、繋いでいいですか?」
「うん、いいよ」
無言で待つ私たち。言葉はなくても、隣に荒木がいるだけでなんだかあたたかい。手の温もりも、とても安心感を得るようなあたたかさで。そして触れた手を意識していると胸の鼓動が早くなる。
電車のヘッドライトが遠くに見え、ゴーッという音が近づいてくる。いつもはこの風景を見ると、やっと家に帰れるなとほっとした気持ちに包まれるけれど、今日は切なさが胸の奥から溢れてくる。
空にはまだ紺色がほのかに残っていて、薄暗い。雪の降る量が増えてきた。
「今日の雪、大きいよね」
「花弁雪(はなびらゆき)っすね」
「花弁雪って言うんだ……なんか可愛い雪だよね」
私たちは手を繋いだまま電車が来るまでずっと空を見上げていた。
荒木と一緒に残業して良かった。もしも残業がなかったら、いつものように帰宅していたら、お酒をひとりで飲んで、愚痴を頭の中でひたすら呟いて寝るだけだったろうなと思うから。そして荒木と過ごしているこの時間がとても楽しかった。
――それは、もっと、この時間が長く続けば良いのにとおもってしまうほどに、だ。
「本当に荒木といるの、楽しかった。また私と遊んでくれる?」
「遊びましょう。次はきちんと計画立てます!」
「計画立ててくれるんだ、楽しみにしてるから」
頬を突き刺す冷たい風と共に、電車が目の前に止まる。
電車のドアが開くと手を離し、二人で中に乗り込んだ。ドアが閉まると、ふたりきりの幸福な夜が、静かに終わりを告げた。
**.✼ ゜
――この夜を、きっと忘れないだろう。