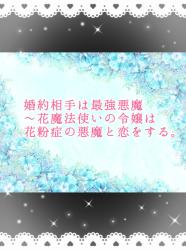「本気で走れば間に合うかな?」
「もう、あきらめましょうよ」
残業のせいで帰りが遅くなった。終電が発車する五分前。私たちはあきらめて立ち止まった。
*
「全力で走れば間に合ったかもな……荒木はこれからどうするの?」
「駅の近くにあるネカフェで始発まで時間潰しでもしますかねぇ……」
駅が小さく見える交差点で今、私よりも三歳年下で二十四歳の後輩、荒木とふたりきりでいる。彼は職場ではいつもテンション高めで輪の中心にいることが多いけれど、でも誰にも本音を見せない雰囲気も纏っていて、掴みどころのない男。
「真希さんは、この後、どうします?」
「うーん、明日休みだし、荒木についていこうかな?」
「タクシー、拾います?」
「私がもしもいなかったら、荒木は歩いていく予定だった?」
「まぁ、近いんで」
近いのか――雪は少し降っているけれどそんな寒くはないし、歩きでも大丈夫かな?
「じゃあ、歩くかな。場所分からないから、とりあえずついていく」
「了解っす!」
荒木は私の前をゆっくり歩いていく。私は彼の後ろを歩いた。近いって言うから、五分ぐらいで着くかと思っていたのに。
「結構、歩くね?」
「そうっすか?」
「あと何分ぐらいで着く?」
「十五分ぐらいでしょうか?」
「あれ? そんなに遠いの? 駅の近くって言ってなかったっけ?」
前を歩いていた荒木は突然立ち止まり、振り向いた。
「一緒に歩きたかったんで、目的地が遠くなりました」
「……何それ?」
「そのままっす」
いつものような明るい笑顔で彼はそう言った。本当によく分からない男だな。ただ適当なのか、それとも深い意味を含んでいる言葉なのか。
再び歩きだすと、荒木は大きな公園の中に入っていった。
「公園通るの、近道?」
「全然、遠回りっす」
荒木は急に止まり、しゃがみだす。
「どうしたの? 大丈夫?」
覗き込むと雪玉を作っていた。荒木は身長が高くて筋肉もあり、全体が私よりも遥かに大きいのだけど、少年のように見えてきて可愛く思えてくる。私もなんとなく、荒木の横に並んでしゃがんだ。そして真似をして雪玉を作った。
「こんなことしたの、かなり久しぶりかも」
「真希さんはもう、俺と違って大人ですもんね」
「いやいや、荒木も大人だから」
私と荒木は見つめ合い、それから微笑み合った。
「今日の雪は湿り気があって、雪玉作りやすいすね」
「そうだね」
「このまま、こうして――」
荒木は雪の上に雪玉を置いてコロコロしだした。楽しそうな雰囲気な荒木に釣られて私も同じことをした。雪玉がどんどん大きくなってくる。それは両手で持たないと持てないぐらいの大きさになった。
「寒いはずなのに、暑くなってきた! 楽しいね」
今私は、大人の本気の遊びをしている。こんな無邪気にいられる時なんて、滅多にない。
「真希さんが作った雪玉、そこに乗せていいですか?」と、荒木は端に寄せてある、自ら作った大きな雪玉を指さす。
「いいよ」と返事をすると、荒木は私が作った雪玉を持ち上げて、それに乗せる。
「雪だるまだ!」
「雪だるまっす。そしてこれをつけて、と」
荒木は落ちていた枝をひとつ拾い、雪だるまの手の位置につけた。
「可愛い!」と言いながら私はスマホで一枚写真を撮る。
「真希さんも雪だるまと一緒に写りませんか? 俺、撮りますよ?」
「私は、写らなくていいかな?」
「いや、撮りますって」
「うーん、じゃあ」と、強引な態度に負けて私はスマホを荒木に渡した。
とりあえずしゃがみ、雪だるまに顔をよせて口角を上げてみる。
「いいっすね」と言いながら荒木はシャッターボタンを何度も押している様子だった。荒木からスマホを返してもらい、私は画面を見てどう撮れたのか確認をする。雪だるまと、少し照れた微妙な笑顔の私が写っていた。
「いい写真っすね!」
「そうかな?」
「最高っす。真希さん、雪だるま似合ってて可愛いから、後から俺のスマホに送ってください」
久しぶりに可愛いだなんて言われて、少し照れちゃうな――。
「でも、荒木の連絡先知らないしな……」
「じゃあ、今から交換しましょうよ」
「う、うん。分かった」
ぐいぐいくるから、流されるように連絡先を交換した。交換すると、すぐにスマホをバッグにしまった。そしてまた私は小さな雪だるまをいくつも作り、ふたつひと組にして小さな雪だるまをたくさん作った。横では荒木も同じ動きをしていた。
「さて、そろそろネカフェに行こうか……寒くなってきたし」
「了解っす!」
並べられた雪だるまも写真に撮った。そして公園を出るとネカフェに再び向かう。街灯の光が雪に反射して、夜の街がほんのり明るくて綺麗だ。
「ねえ、荒木、また遠回りしてない?」
「いやいや、ちゃんと近道っすよ」
荒木は振り向くと微笑む。その笑顔がなんだか悪戯っぽくて、信じてもいいのか怪しい。まぁ、怪しいと思うのなら今すぐスマホで地図を見れば一発で正解が分かるのだけど、私はスマホを開かなかった。
荒木に流されていたい気分で。だって、楽しいから――。
「ほんとかなあ。さっきの公園までの道も遠回りだったよね?」
「まぁ、雪だるまが作れたから、結果オーライじゃないっすか?」
たしかに――あの無邪気な時間は有意義な時間だった。最近は仕事に追われる毎日で、家と会社の往復で精一杯だった。こんなふうに雪で遊ぶなんて、景色が綺麗だなんて感じたのは、何年ぶりだろう。
荒木の軽くみえるそのノリに付き合っていると、ずしんとして重たかった心が軽くなってゆく気がした。
「真希さんは雪、好きっすか?」と、荒木が突然聞いてきた。
「うーん、子供の頃は好きだったかな。今は、電車止まったり、歩きずらかったり……あと除雪もしないといけないし、雪が降る日は色々と面倒だなって思っちゃう」
「真希さんは大人っすねえ」
「なぜそこで大人だと思うの?」
「いや、なんとなく? 俺なんて雪を見た瞬間にテンション上がっちゃって……初雪の日には特にはしゃいじゃって、走り回りますよ」
「犬みたいにはしゃいでる荒木、すっごい想像できる」
つい私は想像して、声を出して笑ってしまった。
「荒木って、ほんと子供っぽいよね」
「それ、褒め言葉っすか?」と、彼はニヤッと笑う。
「褒め言葉だよ!」
本当にそう思う。荒木のそんなとこをもっと見習って、もっと気軽に生きたい。
「なら、いいですけど。まぁ、雪見ても全然テンション上がらなかった時期もあったんですけどね」
「荒木でも、そんな時があるんだ?」
「ありますよ」
そんな感じで和気あいあいと話しながらしばらく歩いていると、ネオンが光るネットカフェの看板が見えてきた。ビルの一階で、ガラス越しにカウンターと派手めなアニメのポスターが見える。荒木が「着いたっす!」と自動ドアの前に立つ。
「もう、あきらめましょうよ」
残業のせいで帰りが遅くなった。終電が発車する五分前。私たちはあきらめて立ち止まった。
*
「全力で走れば間に合ったかもな……荒木はこれからどうするの?」
「駅の近くにあるネカフェで始発まで時間潰しでもしますかねぇ……」
駅が小さく見える交差点で今、私よりも三歳年下で二十四歳の後輩、荒木とふたりきりでいる。彼は職場ではいつもテンション高めで輪の中心にいることが多いけれど、でも誰にも本音を見せない雰囲気も纏っていて、掴みどころのない男。
「真希さんは、この後、どうします?」
「うーん、明日休みだし、荒木についていこうかな?」
「タクシー、拾います?」
「私がもしもいなかったら、荒木は歩いていく予定だった?」
「まぁ、近いんで」
近いのか――雪は少し降っているけれどそんな寒くはないし、歩きでも大丈夫かな?
「じゃあ、歩くかな。場所分からないから、とりあえずついていく」
「了解っす!」
荒木は私の前をゆっくり歩いていく。私は彼の後ろを歩いた。近いって言うから、五分ぐらいで着くかと思っていたのに。
「結構、歩くね?」
「そうっすか?」
「あと何分ぐらいで着く?」
「十五分ぐらいでしょうか?」
「あれ? そんなに遠いの? 駅の近くって言ってなかったっけ?」
前を歩いていた荒木は突然立ち止まり、振り向いた。
「一緒に歩きたかったんで、目的地が遠くなりました」
「……何それ?」
「そのままっす」
いつものような明るい笑顔で彼はそう言った。本当によく分からない男だな。ただ適当なのか、それとも深い意味を含んでいる言葉なのか。
再び歩きだすと、荒木は大きな公園の中に入っていった。
「公園通るの、近道?」
「全然、遠回りっす」
荒木は急に止まり、しゃがみだす。
「どうしたの? 大丈夫?」
覗き込むと雪玉を作っていた。荒木は身長が高くて筋肉もあり、全体が私よりも遥かに大きいのだけど、少年のように見えてきて可愛く思えてくる。私もなんとなく、荒木の横に並んでしゃがんだ。そして真似をして雪玉を作った。
「こんなことしたの、かなり久しぶりかも」
「真希さんはもう、俺と違って大人ですもんね」
「いやいや、荒木も大人だから」
私と荒木は見つめ合い、それから微笑み合った。
「今日の雪は湿り気があって、雪玉作りやすいすね」
「そうだね」
「このまま、こうして――」
荒木は雪の上に雪玉を置いてコロコロしだした。楽しそうな雰囲気な荒木に釣られて私も同じことをした。雪玉がどんどん大きくなってくる。それは両手で持たないと持てないぐらいの大きさになった。
「寒いはずなのに、暑くなってきた! 楽しいね」
今私は、大人の本気の遊びをしている。こんな無邪気にいられる時なんて、滅多にない。
「真希さんが作った雪玉、そこに乗せていいですか?」と、荒木は端に寄せてある、自ら作った大きな雪玉を指さす。
「いいよ」と返事をすると、荒木は私が作った雪玉を持ち上げて、それに乗せる。
「雪だるまだ!」
「雪だるまっす。そしてこれをつけて、と」
荒木は落ちていた枝をひとつ拾い、雪だるまの手の位置につけた。
「可愛い!」と言いながら私はスマホで一枚写真を撮る。
「真希さんも雪だるまと一緒に写りませんか? 俺、撮りますよ?」
「私は、写らなくていいかな?」
「いや、撮りますって」
「うーん、じゃあ」と、強引な態度に負けて私はスマホを荒木に渡した。
とりあえずしゃがみ、雪だるまに顔をよせて口角を上げてみる。
「いいっすね」と言いながら荒木はシャッターボタンを何度も押している様子だった。荒木からスマホを返してもらい、私は画面を見てどう撮れたのか確認をする。雪だるまと、少し照れた微妙な笑顔の私が写っていた。
「いい写真っすね!」
「そうかな?」
「最高っす。真希さん、雪だるま似合ってて可愛いから、後から俺のスマホに送ってください」
久しぶりに可愛いだなんて言われて、少し照れちゃうな――。
「でも、荒木の連絡先知らないしな……」
「じゃあ、今から交換しましょうよ」
「う、うん。分かった」
ぐいぐいくるから、流されるように連絡先を交換した。交換すると、すぐにスマホをバッグにしまった。そしてまた私は小さな雪だるまをいくつも作り、ふたつひと組にして小さな雪だるまをたくさん作った。横では荒木も同じ動きをしていた。
「さて、そろそろネカフェに行こうか……寒くなってきたし」
「了解っす!」
並べられた雪だるまも写真に撮った。そして公園を出るとネカフェに再び向かう。街灯の光が雪に反射して、夜の街がほんのり明るくて綺麗だ。
「ねえ、荒木、また遠回りしてない?」
「いやいや、ちゃんと近道っすよ」
荒木は振り向くと微笑む。その笑顔がなんだか悪戯っぽくて、信じてもいいのか怪しい。まぁ、怪しいと思うのなら今すぐスマホで地図を見れば一発で正解が分かるのだけど、私はスマホを開かなかった。
荒木に流されていたい気分で。だって、楽しいから――。
「ほんとかなあ。さっきの公園までの道も遠回りだったよね?」
「まぁ、雪だるまが作れたから、結果オーライじゃないっすか?」
たしかに――あの無邪気な時間は有意義な時間だった。最近は仕事に追われる毎日で、家と会社の往復で精一杯だった。こんなふうに雪で遊ぶなんて、景色が綺麗だなんて感じたのは、何年ぶりだろう。
荒木の軽くみえるそのノリに付き合っていると、ずしんとして重たかった心が軽くなってゆく気がした。
「真希さんは雪、好きっすか?」と、荒木が突然聞いてきた。
「うーん、子供の頃は好きだったかな。今は、電車止まったり、歩きずらかったり……あと除雪もしないといけないし、雪が降る日は色々と面倒だなって思っちゃう」
「真希さんは大人っすねえ」
「なぜそこで大人だと思うの?」
「いや、なんとなく? 俺なんて雪を見た瞬間にテンション上がっちゃって……初雪の日には特にはしゃいじゃって、走り回りますよ」
「犬みたいにはしゃいでる荒木、すっごい想像できる」
つい私は想像して、声を出して笑ってしまった。
「荒木って、ほんと子供っぽいよね」
「それ、褒め言葉っすか?」と、彼はニヤッと笑う。
「褒め言葉だよ!」
本当にそう思う。荒木のそんなとこをもっと見習って、もっと気軽に生きたい。
「なら、いいですけど。まぁ、雪見ても全然テンション上がらなかった時期もあったんですけどね」
「荒木でも、そんな時があるんだ?」
「ありますよ」
そんな感じで和気あいあいと話しながらしばらく歩いていると、ネオンが光るネットカフェの看板が見えてきた。ビルの一階で、ガラス越しにカウンターと派手めなアニメのポスターが見える。荒木が「着いたっす!」と自動ドアの前に立つ。