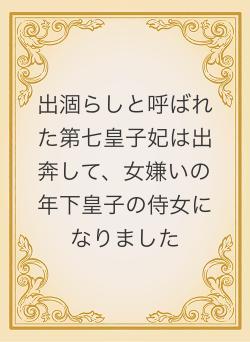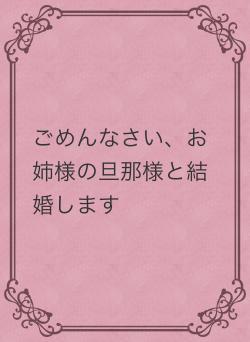あんなに、優しい方を……方達にこれ以上迷惑を掛けてはいけない。心の底から、こんな自分を心配してくれた。こんな自分を、好きだと言ってくれた。そんな彼を、巻き込んではいけない。
「では、行ってきます」
翌朝フィオナは、一人馬車に乗り込んだ。門の前まで見送るヴィレームに、挨拶をする。すると彼は呆然とした様子で「うん」とだけ返事をした。
「ごめんなさい……」
馬車が大きく揺れ、動き出す。窓の外にはまだヴィレームが立ち尽くしているのが見えた。その彼にフィオナは、聞こえる筈もないのに、そう呟いた。
「今日は一人なのか」
誰もいない廊下を歩いていると、背後から声を掛けられた。立ち止まり振り返ると、そこにはオリフェオの姿があった。その瞬間、緊張と動悸が激しくなる。
「……」
彼はゆっくりと近寄って来ると、フィオナの仮面に触れ、何度も撫でてくる。
「……ようやく、二人きりだ」
仮面を外そうとするが、その手をフィオナは叩いた。
「どうした?」
「やめて……」
「怒ってるのか」
「……ヨハン」
フィオナがそう呟くと、目を丸くして、次の瞬間彼の口元がゆっくりと綺麗な弧を描いた。
「何時、気付いたの?姉さん」
「ハンス様が亡くなった日の休み時間に、オリフェオ殿下……いいえ、貴方が私に会いに来たでしょう」
あの日授業の合間の休み時間に、オリフェオがわざわざ教室までやって来た。これが平常時で、フィオナに第二王子である彼が会いに来たとなれば、教室が騒がしくなりそうなものだが、今のこの状況では多少視線を感じる程度だった。無論シャルロットもいたのだが、彼女はオリフェオを好いていない様で、出入り口まではついて来なかった。
『ハンス・エルマーが死んだ』
『⁉︎』
余りの事に声も出なかった。だが、彼が嘘を吐いているとは思えなかった。
『ニクラス同様、今朝図書室で倒れているのが見つかった。また心臓だけが抜かれていた』
昨日の、様子のおかしいハンスを思い出す。やはり、今更復縁したいなど、何かあったに違いない。亡くなったニクラスと関係があるのだろうか……。
『ハンス様が……どうして』
フィオナは俯き、身体が震えた。昨日、自分が拒絶するだけでなく、もっと詳しく彼の話を聞いてあげていたら……何か違ったかも知れない。彼は必死の形相で、今考えれば怯えた様にも思える。
ハンスの事は赦せない。だからと言って死んで欲しかった訳じゃない。だが、嘆いた所で今更に過ぎない……。
『意外だな。君を裏切り捨てた男だぞ。死んで当然だ。天罰でも食らったのだろう』
ハンスとは昨日まで初対面だったオリフェオが、そこまで言うなんて……違和感を感じた。フィオナとだって、ダンスパーティーの時に一度顔を合わせただけで、良い印象などなかった。それなのにも関わらず、昨日の彼の態度や振る舞いも、改めて考えると違和感しかない。
『……確かに私は、彼の事は赦せませんでした。ですが、死んで欲しいと願った事などありません』
『愚かだな。だから、あんな男に引っかかるんだ』
確かに彼の言う通りかも知れない。だが、やはりフィオナには彼がした事が、死に値する様な事だったとは思えない。もし彼の死が天罰と言うならば、いき過ぎた罰だ。
ふとオリフェオを見ると、苛々を隠せない様子で首の後ろをしきり触っていた。
同じだ、そう思った。弟のヨハンの癖と、同じ……。
何時も優しい弟がたまに、ふとした瞬間、首の後ろを触る時があった。多分無自覚なのだと思うが、そう言う時は決まってヨハンは苛々している様子だった。フィオナは人より他人の感情の変化に敏感な方だ。だから隠しているつもりでも、何時も僅かな感情の変化が伝わってくるのを感じていた。
オリフェオを見ると、未だ不満そうにしていた。昨日も感じた違和感を、感じる。モヤモヤとして、気持ちが悪いとすら思う。
『……そう言えば、ダンスパーティーの際、妹のミラベルとご一緒でしたが、もしかして婚約でもなさるんですか』
『何だ、妬いているのか』
『い、いえ、そう言う訳では……』
『案ずるな。あんな我儘で口悪く淑女の風上にも置けない女など、この私が相手にする筈がないだろう。また泣き喚かれても煩くて構わんからな』
この瞬間、フィオナの違和感は確信に変わった。
「では、行ってきます」
翌朝フィオナは、一人馬車に乗り込んだ。門の前まで見送るヴィレームに、挨拶をする。すると彼は呆然とした様子で「うん」とだけ返事をした。
「ごめんなさい……」
馬車が大きく揺れ、動き出す。窓の外にはまだヴィレームが立ち尽くしているのが見えた。その彼にフィオナは、聞こえる筈もないのに、そう呟いた。
「今日は一人なのか」
誰もいない廊下を歩いていると、背後から声を掛けられた。立ち止まり振り返ると、そこにはオリフェオの姿があった。その瞬間、緊張と動悸が激しくなる。
「……」
彼はゆっくりと近寄って来ると、フィオナの仮面に触れ、何度も撫でてくる。
「……ようやく、二人きりだ」
仮面を外そうとするが、その手をフィオナは叩いた。
「どうした?」
「やめて……」
「怒ってるのか」
「……ヨハン」
フィオナがそう呟くと、目を丸くして、次の瞬間彼の口元がゆっくりと綺麗な弧を描いた。
「何時、気付いたの?姉さん」
「ハンス様が亡くなった日の休み時間に、オリフェオ殿下……いいえ、貴方が私に会いに来たでしょう」
あの日授業の合間の休み時間に、オリフェオがわざわざ教室までやって来た。これが平常時で、フィオナに第二王子である彼が会いに来たとなれば、教室が騒がしくなりそうなものだが、今のこの状況では多少視線を感じる程度だった。無論シャルロットもいたのだが、彼女はオリフェオを好いていない様で、出入り口まではついて来なかった。
『ハンス・エルマーが死んだ』
『⁉︎』
余りの事に声も出なかった。だが、彼が嘘を吐いているとは思えなかった。
『ニクラス同様、今朝図書室で倒れているのが見つかった。また心臓だけが抜かれていた』
昨日の、様子のおかしいハンスを思い出す。やはり、今更復縁したいなど、何かあったに違いない。亡くなったニクラスと関係があるのだろうか……。
『ハンス様が……どうして』
フィオナは俯き、身体が震えた。昨日、自分が拒絶するだけでなく、もっと詳しく彼の話を聞いてあげていたら……何か違ったかも知れない。彼は必死の形相で、今考えれば怯えた様にも思える。
ハンスの事は赦せない。だからと言って死んで欲しかった訳じゃない。だが、嘆いた所で今更に過ぎない……。
『意外だな。君を裏切り捨てた男だぞ。死んで当然だ。天罰でも食らったのだろう』
ハンスとは昨日まで初対面だったオリフェオが、そこまで言うなんて……違和感を感じた。フィオナとだって、ダンスパーティーの時に一度顔を合わせただけで、良い印象などなかった。それなのにも関わらず、昨日の彼の態度や振る舞いも、改めて考えると違和感しかない。
『……確かに私は、彼の事は赦せませんでした。ですが、死んで欲しいと願った事などありません』
『愚かだな。だから、あんな男に引っかかるんだ』
確かに彼の言う通りかも知れない。だが、やはりフィオナには彼がした事が、死に値する様な事だったとは思えない。もし彼の死が天罰と言うならば、いき過ぎた罰だ。
ふとオリフェオを見ると、苛々を隠せない様子で首の後ろをしきり触っていた。
同じだ、そう思った。弟のヨハンの癖と、同じ……。
何時も優しい弟がたまに、ふとした瞬間、首の後ろを触る時があった。多分無自覚なのだと思うが、そう言う時は決まってヨハンは苛々している様子だった。フィオナは人より他人の感情の変化に敏感な方だ。だから隠しているつもりでも、何時も僅かな感情の変化が伝わってくるのを感じていた。
オリフェオを見ると、未だ不満そうにしていた。昨日も感じた違和感を、感じる。モヤモヤとして、気持ちが悪いとすら思う。
『……そう言えば、ダンスパーティーの際、妹のミラベルとご一緒でしたが、もしかして婚約でもなさるんですか』
『何だ、妬いているのか』
『い、いえ、そう言う訳では……』
『案ずるな。あんな我儘で口悪く淑女の風上にも置けない女など、この私が相手にする筈がないだろう。また泣き喚かれても煩くて構わんからな』
この瞬間、フィオナの違和感は確信に変わった。