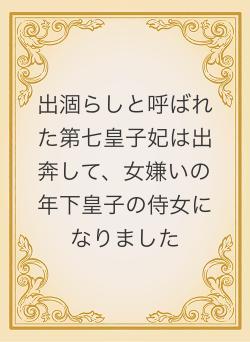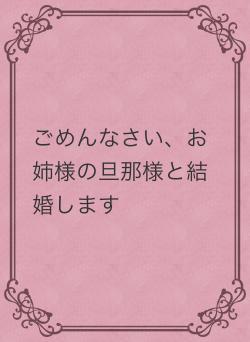あれからもう直ぐ一年が経とうとしている。この一年、ユスティーナは妃教育で忙しい日々を送っていた。元々レナードの婚約者の時から王子妃の教育は受けていたが、王太子妃となると次元が違った……。
王子妃と王太子妃がこれだけの差があるのだ。レナードとヴォルフラムが受けてきた教育の差はユスティーナが想像していたものを遥かに超えるものだろう。
「ユティ、お疲れ様」
その日の妃教育がようやく終わり、ユスティーナが城の中庭で一息吐いていると、ヴォルフラムがやって来た。
「ヴォルフラム様も、お仕事お疲れ様です」
彼はベンチを素通りして、木を背にして地べたに座った。
「おいで」
ユスティーナはヴォルフラムの膝の上に横向きに座らせ、抱き締められる。彼はこれがお気に入りらしく、中庭に来ると必ずこうする。
「後、一月だね」
一ヶ月後に、ユスティーナとヴォルフラムの挙式が執り行われる。最近は妃教育に加えその準備にも追われており、彼とこうやって過ごすのはかなり久々だった。
「はい。でも私なんかが本当に王太子妃なんて……少し、不安です」
「大丈夫だよ。君は大変優秀だと、教育者等からも評判だし、不安になる必要などないよ。それに君はこの僕が選んだ女性だ。それを忘れないで」
暫くたわいない話を愉しんだ後、ヴォルフラムが急に黙り込んだ。
「ヴォルフラム様、どうかなさいましたか」
「……言おうかどうか悩んだんだ。だがやはり伝えるべきだと思ってね。実は……昨夜知らせが届いたんだ」
「?」
「レナードが亡くなった」
目を見開き、一瞬心臓が止まった気がした。聞き間違えなんじゃないかと耳を疑った。
「自害したそうだ」
「そんな……どう、して……」
レナードはあれから郊外の屋敷から、遠い北の地にある古城に幽閉されたと聞いていた。あんな風になってはしまったが、彼には悔い改め、何時か生きていて良かったと思える日が来て欲しいと願っていた。それなのに……。
「やっぱり、君は優しいね。あんな弟の為にも、泣いてくれるんだね」
どうしようなく涙が溢れた。それをヴォルフラムは自らの唇で優しく丁寧に拭ってくれる。
「愚かでどうしようもない弟だったが……残念でならないよ。あんな事にはなってしまったが、レナードには生きていて欲しかった。何時か兄弟として和解出来る日が来るかも知れないと期待していたんだけどね……。ただ王族から除籍されただけではなく生涯幽閉となった事で、レナードの自尊心は傷付き、きっと耐えられなかったんだろうね……。ユティ」
彼の唇が目尻、頬、そして唇に触れた。
「レナードの分まで、僕達は幸せになろう」
その一ヶ月後、二人は婚儀を挙げ、夫婦になった。幸せそうに微笑むユスティーナをヴォルフラムは屈託のない笑顔で見つめていた。
終