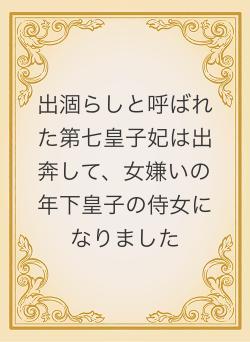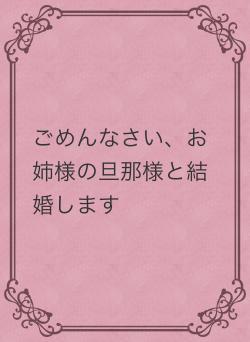あの後、動揺し過ぎてどうやって帰って来たのか余り良く覚えていない。
『こんな事、冗談で言う筈ないよ』
彼からそう言われ、少し潤んだ熱を帯びた瞳で見つめられた。ユスティーナはあの目を知っている。レナードがジュディットを見る時と同じだ。
「そんな訳ある筈、ない!ない!ない!」
ユスティーナは本を勢いよく閉じると頭を振る。突然叫んだユスティーナに、侍女のエルマが目を丸くした。
「ユスティーナ様、如何なさいましたか」
「え、あ……いえ、何でもないわ」
ユスティーナは気不味そうに、ワザとらしい咳をして何事もなかった様に本を開いた。
きっとアレはヴォルフラムに揶揄われただけだ。いやもしかしたら試された可能性もある。そもそもヴォルフラムが他に好きな女性がいる事自体が嘘で、例えばあの時ユスティーナがヴォルフラムにコロッと靡いたら、尻軽女なんて可愛い弟とは婚約破棄させる!とか言われていたかも知れない。
多分そうだ、そうに違いない!……そうじゃないとおかしい。あんな絶世の美女が婚約者にいるのに、態々こんな何の取り柄もないつまらない娘を好きになるなんてあり得ない!
きっとユスティーナとレナードが上手くいっていないと思って、ここぞとばかりに試されたのだ。将来の王子妃に義妹に相応しいか否かと。
ヴォルフラムは王太子で眉目秀麗で、レナードとはまた違った魅力のある青年だ。文武両道で多才でもある。詳しくは知らないが、芸術面でも秀でていると聞いた事がある。そんな人から好きだなんて言われたら、大抵の女性は悪い気はしないだろう。寧ろ喜んで手を取るかも知れない。例えパートナーがいたとしても……。きっと彼はそれを十分に理解しながら狙って…………もしユスティーナがヴォルフラムの手を取っていたなら婚約破棄だけじゃなくて、不貞を働いたとして牢に入れられたり、それを口実にオリヴィエ家を取り潰したり……。
「怖、過ぎる……」
「?」
色々と想像したら背筋が寒くなり、身震いをする。
すると様子のおかしいユスティーナを見て、益々エルマは不審そうな表情を浮かべた。だが今はそんな事を気にしている場合じゃない。未だかつてないくらいの人生の危機だ。
ヴォルフラムの意図は分からないが、十分警戒する必要がありそうだ。彼の狙いが分からない以上また仕掛けてくる可能性がある。
怖過ぎる……ー。
◆◆◆
「相変わらずだね、お前は」
ジュディットを馬車に乗せ、見送ったタイミングで兄のヴォルフラムに声を掛けられた。
「兄上」
「そんなに彼女が好きか」
冷笑され、レナードは顔を顰めた。
「申し訳、ありません」
「何故謝る?別に責めている訳じゃないよ」
レナードは昔から兄が苦手だ。兄は全てにおいて完璧で隙がない。自分に向ける蔑む様な眼差しも好きになれない。
「ですがジュディットは、兄上の婚約者ですから……」
そう言うとヴォルフラムは鼻で笑った。
「それを承知の上で、お前は彼女の誘いに応じているのだろう。謝るくらいなら、これからは断る事だね」
「……」
「まあ、お前には出来ないか。自分の婚約者を悲しませていると知りながら、それでもジュディットと会う事をやめられないのだからな」
そんな事、言われなくても分かっている。
毎回、今日こそは断らなくてはならないと強く思いながらも、ジュディットを前にすると口が身体が勝手に動いてしまう。美しい彼女の声や笑みに抗えない。
「いっそのこと噂通り、お前が彼女を奪ってくれたらこんなに嬉しい事はないんだけどね」
「兄上‼︎なんて事を言うんですか⁉︎兄上はジュディットの気持ちを知っていてそんな酷い事を言うんですか⁉︎」
瞬間、頭に血が上りレナードは声を荒げた。
「ジュディットは兄上の事を本当に愛しているんです!そんな彼女の気持ちを踏み躙るつもりですか⁉︎」
ジュディットは兄のヴォルフラムが好きだ。だからレナードは諦めたのだ。もしジュディットがヴォルフラムを好きではなかったなら、疾うの昔に奪っているだろう。そんなレナードの気持ちもジュディットの気持ちも敏い兄ならばそれ等を十分に理解している筈だ。それなのにも関わらず、そんな風に言うなんて赦せない。
「お前がそんな風に言うなんて、滑稽だね。婚約者であるユスティーナ嬢の気持ちを何時も踏み躙っているのは誰だ?お前こそ彼女の気持ちを知りながらジュディットを優先させているだろう」
「……で、ですが私は、ユスティーナと婚約解消などするつもりなど有りませんから」
ちゃんと最後までユスティーナに対して責任を果たす。例え彼女に対して愛がなくともヴォルフラムの様に放り出すなどとは思わない。
「余計にタチが悪いな。お前、それ分かってて言ってるの?そうだとしたら僕の弟は随分と性悪なんだな。ユスティーナ嬢が不憫でならない」
「それは、どう言う意味ですか……」
「莫迦なお前には一生掛けても分からないかもね。まあ、これからも精々ジュディットと仲良くしていなよ」
ヴォルフラムはそれだけ言うと踵を返して去って行った。
「何れ、後悔する日が来るから……」
レナードは、ヴォルフラムが去り際に言った言葉だけは良く聞き取れず、眉根を寄せる。
その場に残されたレナードは暫し立ち尽くしていた。