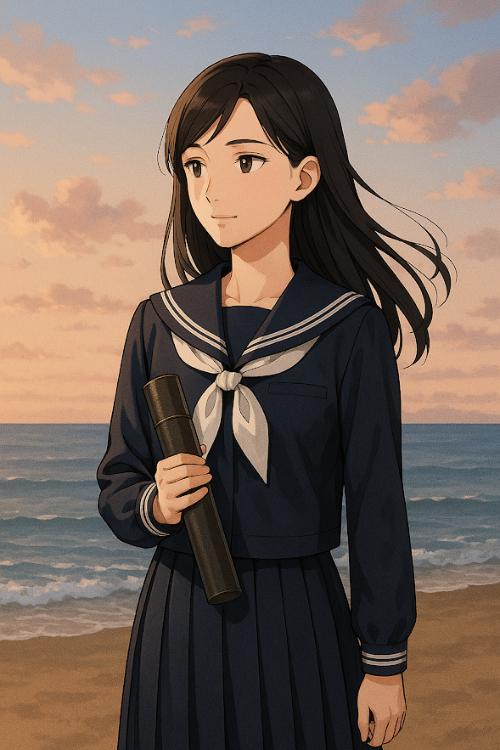別れの日が決まっている恋は、こんなにもつらいものなのか。逢えば逢うほど、切なさが加速する。
マツアはその感覚に耐えきれず、眠れぬ夜をいくつも数えた。
夢の中に堕ちていくときだけが、ほんの少し現実から逃げられる時間だった。
冬休みに入ると、朝から夕方まで、二人はずっと一緒にいた。
スマホで他愛ない写真を撮り合い、浜辺では凍える風に震えながら、
互いの片方の手袋を脱いで、恋人繋ぎをした。
マツアの瞳に揺れる悲しみは、セイラの胸に痛く刺さった。
(何かを隠している……)
そう感じていたが、問い詰めれば、この関係が一瞬で泡のように消えてしまう気がして、言えなかった。
冬休みが終わり、セイラにとって最後の三学期が始まった。
地元の小さな会社に就職が決まっていたセイラ。
だが――
「就職先、決まったよ」
そうマツアには伝えたけれど、「地元だ」とは、なぜかまだ言えずにいた。
ある日、マツアはぽつりと告げた。
「セイラさん、僕は……父に逢いに行くことにしたよ」
その呼び方に、セイラは息をのんだ。
――“先輩”じゃない。“さん”と呼んだのは、これが初めてだった。
何かが終わり、そして何かが始まる。そんな予感が胸をよぎった。
「そう……。どこにいるのか、わかったんだね」
「うん。遠いよ。とても遠い、この海の果てにいるんだ」
「……しばらく、逢えないってことか」
「何、泣いているんだよ、マツア」
「一緒にいたい。ずっとそばにいたい」
――かわいいヤツだな、マツア。
(あたしたちの心は、いつも一緒だよ)
その言葉を、セイラはそっと飲み込んだ。
東京での就職をやめ、地元に残る決意をしたことも、まだ伝えられずにいた。
---別れまで、あとどれくらい?
そのフレーズが、今度はセイラの耳の奥で繰り返された。
無意識に、彼女はマツアの鼻をつまんだ。
「一緒だよ、ずっと。心は、いつも」
ふたりは、ためらいもなく唇を重ねた。
涙が頬をすべっていく。
それが愛しさの涙なのか、悲しみの涙なのか、わからなかった。
いろんな想いが混ざり合って、切なさという形になっていた。
「この浜辺が、あたしたちの待ち合わせ場所だよ、マツア」
「……うん」
「だから、あたしはここで待ってる」
「……東京には?」
マツアの問いかけに、セイラはもう一度、彼の唇をそっと塞いだ。
「ここで、待っているから」
※ ※ ※
---別れまで、あと……1日
そして、卒業式が来た。
セイラが卒業証書を受け取る後ろ姿を、在校生席からマツアは静かに見つめていた。
マツアは涙が、止まらなかった。
胸の奥が、引き裂かれるように痛んだ。
卒業式が終わって、セイラは校内を探し回った。けれど、マツアの姿はどこにもなかった。
卒業証書を握りしめたまま、セイラは街を彷徨い、そして……いつもの浜辺へとたどり着いた。
そこには、何もなかった。
冷たい海風が吹きつけ、冬の海が広がっているだけだった。
でも、ふと顔を上げたセイラは、その先に――
ほんの微かな、春の気配を感じた。
それはまるで、マツアの気配のようだった。
「マツア……ここで、待っているからね」
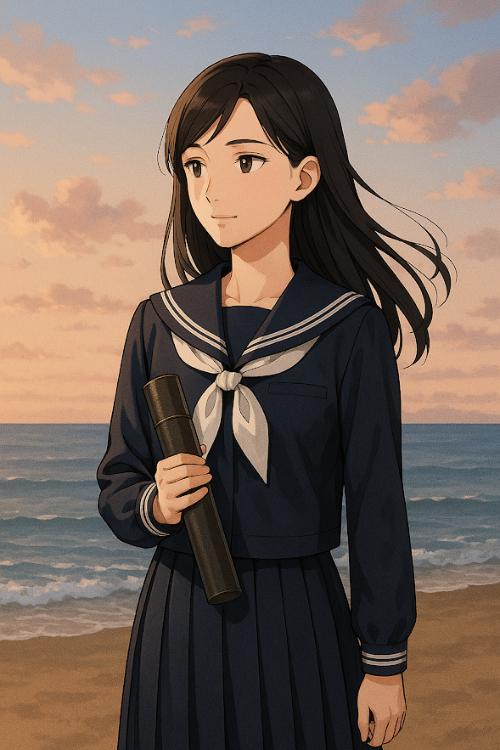
マツアはその感覚に耐えきれず、眠れぬ夜をいくつも数えた。
夢の中に堕ちていくときだけが、ほんの少し現実から逃げられる時間だった。
冬休みに入ると、朝から夕方まで、二人はずっと一緒にいた。
スマホで他愛ない写真を撮り合い、浜辺では凍える風に震えながら、
互いの片方の手袋を脱いで、恋人繋ぎをした。
マツアの瞳に揺れる悲しみは、セイラの胸に痛く刺さった。
(何かを隠している……)
そう感じていたが、問い詰めれば、この関係が一瞬で泡のように消えてしまう気がして、言えなかった。
冬休みが終わり、セイラにとって最後の三学期が始まった。
地元の小さな会社に就職が決まっていたセイラ。
だが――
「就職先、決まったよ」
そうマツアには伝えたけれど、「地元だ」とは、なぜかまだ言えずにいた。
ある日、マツアはぽつりと告げた。
「セイラさん、僕は……父に逢いに行くことにしたよ」
その呼び方に、セイラは息をのんだ。
――“先輩”じゃない。“さん”と呼んだのは、これが初めてだった。
何かが終わり、そして何かが始まる。そんな予感が胸をよぎった。
「そう……。どこにいるのか、わかったんだね」
「うん。遠いよ。とても遠い、この海の果てにいるんだ」
「……しばらく、逢えないってことか」
「何、泣いているんだよ、マツア」
「一緒にいたい。ずっとそばにいたい」
――かわいいヤツだな、マツア。
(あたしたちの心は、いつも一緒だよ)
その言葉を、セイラはそっと飲み込んだ。
東京での就職をやめ、地元に残る決意をしたことも、まだ伝えられずにいた。
---別れまで、あとどれくらい?
そのフレーズが、今度はセイラの耳の奥で繰り返された。
無意識に、彼女はマツアの鼻をつまんだ。
「一緒だよ、ずっと。心は、いつも」
ふたりは、ためらいもなく唇を重ねた。
涙が頬をすべっていく。
それが愛しさの涙なのか、悲しみの涙なのか、わからなかった。
いろんな想いが混ざり合って、切なさという形になっていた。
「この浜辺が、あたしたちの待ち合わせ場所だよ、マツア」
「……うん」
「だから、あたしはここで待ってる」
「……東京には?」
マツアの問いかけに、セイラはもう一度、彼の唇をそっと塞いだ。
「ここで、待っているから」
※ ※ ※
---別れまで、あと……1日
そして、卒業式が来た。
セイラが卒業証書を受け取る後ろ姿を、在校生席からマツアは静かに見つめていた。
マツアは涙が、止まらなかった。
胸の奥が、引き裂かれるように痛んだ。
卒業式が終わって、セイラは校内を探し回った。けれど、マツアの姿はどこにもなかった。
卒業証書を握りしめたまま、セイラは街を彷徨い、そして……いつもの浜辺へとたどり着いた。
そこには、何もなかった。
冷たい海風が吹きつけ、冬の海が広がっているだけだった。
でも、ふと顔を上げたセイラは、その先に――
ほんの微かな、春の気配を感じた。
それはまるで、マツアの気配のようだった。
「マツア……ここで、待っているからね」