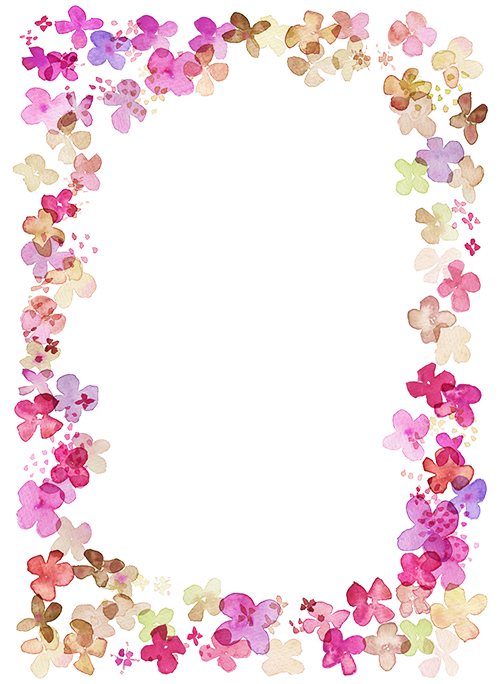「何処から来たんだろうね」
僕は君の隣に並び、その隕石のかけらが入ったガラスの箱をそっと手に取った。
「どうやって来たんだろうね」
君はギターのアルペジオのような調べで、また呟いた。
遠く、遠く、とおくの、またとおく、太陽系を超えて、コーラの泡のような透明な星々が無数に散りばめられた銀河のその泡のひとつから、
「ワープして来たのかな」
「何百光年もかけて、はるばる来たのかも知れない」
超えて、超えて、暗闇を超えて、走って、走って、はしって。
「こんな場所で売られるために来たんじゃないだろうに」
最終的に地球の引力にひかれ、アフリカの広大な地に落ちた。
「きっと地球に恋をして、はるばるやって来たんだよ」
無邪気な君のアルペジオを聞きながら、僕は、
手にした箱の中身の遥かな故郷を思い浮かべてみた。
其処は僕らには想像もつかない文明を持っている星かも知れない。
其処では石も意志を持っているかも知れない。
この隕石は何らかの方法で「地球」と言うこの星を知り、
そのあおさに恋をしたのかも知れない。
「独りで来たのかな」
「独りで来たんだよ」
「物凄く遠いよね」
「うん。きっと、途方もなく遠い」
飛んだ。
果て無き闇を、何百光年もの孤独を超えて、
ただ、ひたすらにそのあおを目指して、求めて、すがって。
それはただのときめきだけでは決して辿り着けない長い旅だ。
他の星に打つかるかも知れない。燃え尽きて芥(あくた)すらにも成れない程こわされるかも知れない。
(この恋は成就しないかも知れない)
其れは宇宙の暗闇よりも、ずっとずっと深い「執着」だ。
其れ程までにこのあおい惑星(ほし)は美しかったのか。
僕は君の隣に並び、その隕石のかけらが入ったガラスの箱をそっと手に取った。
「どうやって来たんだろうね」
君はギターのアルペジオのような調べで、また呟いた。
遠く、遠く、とおくの、またとおく、太陽系を超えて、コーラの泡のような透明な星々が無数に散りばめられた銀河のその泡のひとつから、
「ワープして来たのかな」
「何百光年もかけて、はるばる来たのかも知れない」
超えて、超えて、暗闇を超えて、走って、走って、はしって。
「こんな場所で売られるために来たんじゃないだろうに」
最終的に地球の引力にひかれ、アフリカの広大な地に落ちた。
「きっと地球に恋をして、はるばるやって来たんだよ」
無邪気な君のアルペジオを聞きながら、僕は、
手にした箱の中身の遥かな故郷を思い浮かべてみた。
其処は僕らには想像もつかない文明を持っている星かも知れない。
其処では石も意志を持っているかも知れない。
この隕石は何らかの方法で「地球」と言うこの星を知り、
そのあおさに恋をしたのかも知れない。
「独りで来たのかな」
「独りで来たんだよ」
「物凄く遠いよね」
「うん。きっと、途方もなく遠い」
飛んだ。
果て無き闇を、何百光年もの孤独を超えて、
ただ、ひたすらにそのあおを目指して、求めて、すがって。
それはただのときめきだけでは決して辿り着けない長い旅だ。
他の星に打つかるかも知れない。燃え尽きて芥(あくた)すらにも成れない程こわされるかも知れない。
(この恋は成就しないかも知れない)
其れは宇宙の暗闇よりも、ずっとずっと深い「執着」だ。
其れ程までにこのあおい惑星(ほし)は美しかったのか。