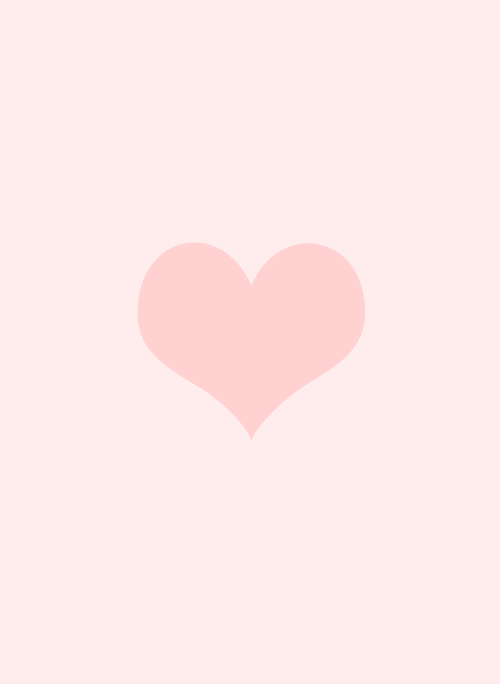てっぺんにはスターの飾りが輝いていて、もみの木に数十分の天使が今年も風に揺れていた。
二十八歳のクリスマスイヴ。
わたしは空っ風にビュウビュウ煽られて、ツリーの真下で立ち尽くしていた。
二十時を過ぎた頃、ツリーを隔てた向こうのCDショップから、懐かしい音色が聴こえてきた。
パッヘルベルの、カノン。
そのオルゴール調の音に耳を澄ませて、わたしはクスクス笑った。
シンデレラを夢見てきたけれど、所詮、夢は夢。
やっぱり、夢は見るからこそ、いいものなんだわ、と思って笑った。
街中、幸せに満ちた恋人達で溢れ返っていて、甘い香りが漂っていた。
パッヘルベルのカノン、好きだって言っていたわね、隼。
会いたいわ、とても。
すごく、よ。
その時、わたしの鼻先を擽ったのは、森林のような清らかな香りだった。
わたしは、必要以上にどきどきした。
「ぼく、好きだなあ。カノン」
「……嘘」
「本当だよ。真央さん、元気だった?やっぱり、会えたね」
そう言って、呆然とするわたしに微笑んでいたのは、三年前とはほど遠い容姿の、隼だった。
ショートボブにしたわたしの黒い髪の毛が、つめたい空っ風に揺れた。
「髪の毛、短くしたんだね」
「ええ」
「すごく、似合ってる。すごく、だよ」
「隼も似合ってるわ、それ」
亜麻色の無造作にセットされていた髪の毛は、すっかり短くなっていて、黒く染まっていた。
左耳に光って揺れていたシルバーピアスも、今は姿も形も無い。
二十八歳のクリスマスイヴ。
わたしは空っ風にビュウビュウ煽られて、ツリーの真下で立ち尽くしていた。
二十時を過ぎた頃、ツリーを隔てた向こうのCDショップから、懐かしい音色が聴こえてきた。
パッヘルベルの、カノン。
そのオルゴール調の音に耳を澄ませて、わたしはクスクス笑った。
シンデレラを夢見てきたけれど、所詮、夢は夢。
やっぱり、夢は見るからこそ、いいものなんだわ、と思って笑った。
街中、幸せに満ちた恋人達で溢れ返っていて、甘い香りが漂っていた。
パッヘルベルのカノン、好きだって言っていたわね、隼。
会いたいわ、とても。
すごく、よ。
その時、わたしの鼻先を擽ったのは、森林のような清らかな香りだった。
わたしは、必要以上にどきどきした。
「ぼく、好きだなあ。カノン」
「……嘘」
「本当だよ。真央さん、元気だった?やっぱり、会えたね」
そう言って、呆然とするわたしに微笑んでいたのは、三年前とはほど遠い容姿の、隼だった。
ショートボブにしたわたしの黒い髪の毛が、つめたい空っ風に揺れた。
「髪の毛、短くしたんだね」
「ええ」
「すごく、似合ってる。すごく、だよ」
「隼も似合ってるわ、それ」
亜麻色の無造作にセットされていた髪の毛は、すっかり短くなっていて、黒く染まっていた。
左耳に光って揺れていたシルバーピアスも、今は姿も形も無い。