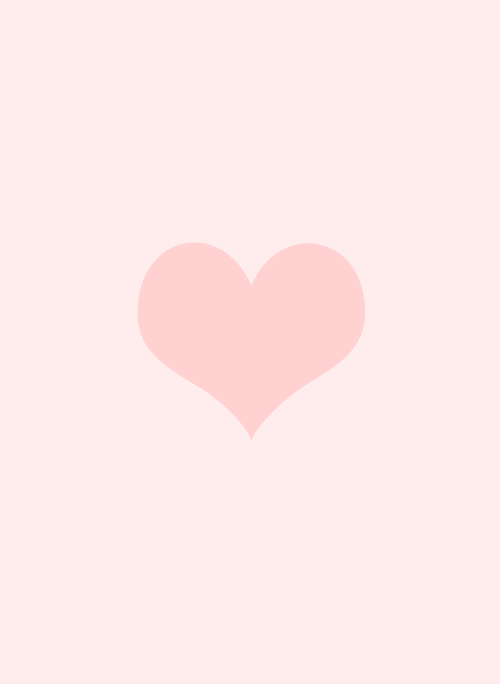「若いから、ロマンチストなのさ」
隼はわたしのあごを静かに持ち上げた。
「待っていてくれる?」
「分からないわ。たぶん、待てないわ。わたしは、もう、二十五だもの」
「いや、待っていてくれるに決まってる」
「きっと、無理ね」
「ぼくには分かるんだ。なにせ、テレパスだからね」
ミステリアスな目が、わたしを羽交い締めにした。
深い、エメラルドグリーンの。
「ぼくは真央さんを好きだよ。とても、ね」
そう言って、隼はわたしにそっと口付けをした。
「来世も真央さんに巡り逢うこと、ぼくは知ってる」
呆然として目を丸くしているわたしに、隼はもう一度口付けをした。
「次に会った時、プロポーズさせて」
「待って!隼」
「その約束をしたくて戻って来たんだ。じゃあね、真央さん」
いつか、あのクリスマスツリーの下で、そう言って、信号がエメラルドグリーンに点滅している横断歩道に駆け出して、隼は走り去った。
「隼!待って」
わたしも公園を飛び出して、追い掛けた。
でも、信号は赤になり、走り出した車にクラクションを鳴らされた。
「隼!隼」
何度も何度も叫んだけれど、車のタイヤがアスファルトと摩擦する音に掻き消されて、彼には届かなかった。
隼は自分を、テレパスだ、と言った。
でも、それは嘘だったのだ。
隼はわたしのあごを静かに持ち上げた。
「待っていてくれる?」
「分からないわ。たぶん、待てないわ。わたしは、もう、二十五だもの」
「いや、待っていてくれるに決まってる」
「きっと、無理ね」
「ぼくには分かるんだ。なにせ、テレパスだからね」
ミステリアスな目が、わたしを羽交い締めにした。
深い、エメラルドグリーンの。
「ぼくは真央さんを好きだよ。とても、ね」
そう言って、隼はわたしにそっと口付けをした。
「来世も真央さんに巡り逢うこと、ぼくは知ってる」
呆然として目を丸くしているわたしに、隼はもう一度口付けをした。
「次に会った時、プロポーズさせて」
「待って!隼」
「その約束をしたくて戻って来たんだ。じゃあね、真央さん」
いつか、あのクリスマスツリーの下で、そう言って、信号がエメラルドグリーンに点滅している横断歩道に駆け出して、隼は走り去った。
「隼!待って」
わたしも公園を飛び出して、追い掛けた。
でも、信号は赤になり、走り出した車にクラクションを鳴らされた。
「隼!隼」
何度も何度も叫んだけれど、車のタイヤがアスファルトと摩擦する音に掻き消されて、彼には届かなかった。
隼は自分を、テレパスだ、と言った。
でも、それは嘘だったのだ。