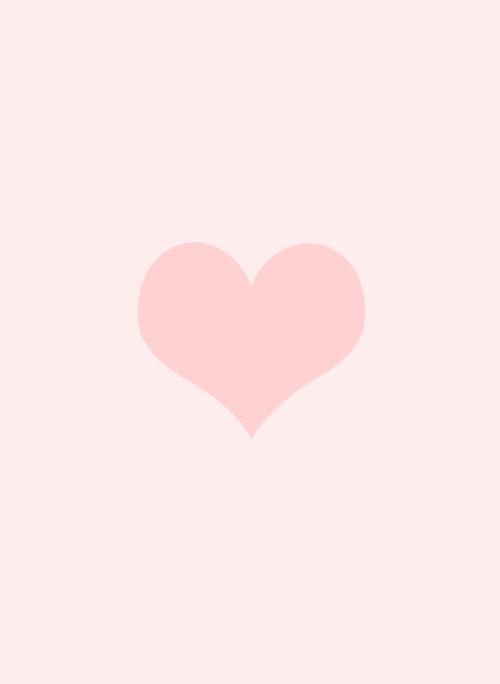「真央さん、慰謝料でも請求してやろう」
「隼!どうして?帰ったはずじゃなかったの」
涙さながらわたしが訊くと、隼はにっこり微笑んでわたしの右手を握った。
「言ったでしょ。ぼくはテレパスだ、って」
「え?」
「真央さんが泣いている気がしたから、戻ってきたのさ。ぼくに戻ってきて欲しいと、願ったんでしょ」
行こう、そう言って、隼はわたしを引きずるように歩き出した。
隼の手の温度は高く、その横顔は、オーランド・ブルームに良く似ていた。
隼は、本当にテレパスなのかもしれない。
百あるうち、八十以上、戻って来て欲しい、とわたしは願っていたのだから。
隼、今すぐ来て、と。
「真央!待てよ」
わたしを呼び止めたのは、不適な笑みを浮かべる亘だった。
「何?まだ何か話したい事があるの?わたしは、無いわ」
そう言って、わたしは隼の左手を強く強く、握った。
「きみは、二十五にもなって高校生に手を出しているのか」
驚いたよ、と亘は言い、人を馬鹿にしたようにクスクス笑った。
「ええ、そうかもしれないわね」
「何て事だ。呆れて言葉が見つからないよ。きみがそこまでだらしのない女だったとはね。思い付きもしなかったよ」
ふん、と鼻で嘲笑う亘に、無性に腹がたった。
それは、このわたしが言う方が相応しい言葉達なのだ。
「隼!どうして?帰ったはずじゃなかったの」
涙さながらわたしが訊くと、隼はにっこり微笑んでわたしの右手を握った。
「言ったでしょ。ぼくはテレパスだ、って」
「え?」
「真央さんが泣いている気がしたから、戻ってきたのさ。ぼくに戻ってきて欲しいと、願ったんでしょ」
行こう、そう言って、隼はわたしを引きずるように歩き出した。
隼の手の温度は高く、その横顔は、オーランド・ブルームに良く似ていた。
隼は、本当にテレパスなのかもしれない。
百あるうち、八十以上、戻って来て欲しい、とわたしは願っていたのだから。
隼、今すぐ来て、と。
「真央!待てよ」
わたしを呼び止めたのは、不適な笑みを浮かべる亘だった。
「何?まだ何か話したい事があるの?わたしは、無いわ」
そう言って、わたしは隼の左手を強く強く、握った。
「きみは、二十五にもなって高校生に手を出しているのか」
驚いたよ、と亘は言い、人を馬鹿にしたようにクスクス笑った。
「ええ、そうかもしれないわね」
「何て事だ。呆れて言葉が見つからないよ。きみがそこまでだらしのない女だったとはね。思い付きもしなかったよ」
ふん、と鼻で嘲笑う亘に、無性に腹がたった。
それは、このわたしが言う方が相応しい言葉達なのだ。