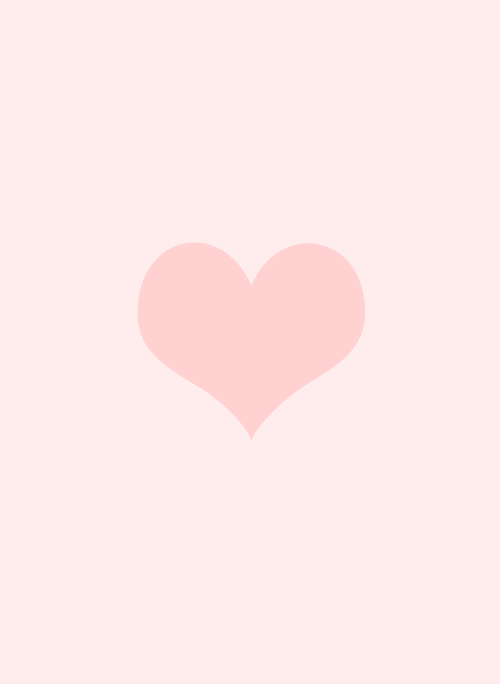わたしは、亘を、好きだった。
同時に、環奈のことも。
三人はどうしてこんなことになってしまったのだろう。
婚約指輪を外すために繋いでいた手をほどき、わたしは言った。
「これ、外すことにするわ。もう、わたしには必要無い物だもの」
「そこまで無理をする必要はないよ」
隼がすっとんきょうな声で言って触れたそれは、皮肉にも美しい光を放っていた。
九号の、婚約指輪。
純銀色で、あわよくば純白色にも見間違えてしまうほど、美しい輝きを放っていた。
「真央さんは、子供みたいな二十五歳だ」
「心外だわ。でも、そうなのかもしれない」
「思い通りにいかなくて、裏腹な行動に出る子供のような人だ」
「ますます心外だわ」
とわたしは言い、でも、心の底から納得していた。
年下の男に馬鹿にされたのに、わたしは頭にこなかった。
婚約指輪を外そうとして手をかけたのに、いざ外すとなると、わたしはひどく憂鬱になった。
凄まじく、困惑した。
亘の左手の薬指にもサイズ違いの、まったく同じデザインのものがあるだろう。
いや、もう外されているかもしれない。
「三ヶ月分の給料と夏のボーナスを合わせて、奮発したんだ」
そう言って、亘は嬉しそうにわたしの薬指に、これ、をはめてくれた。
わたしの父も母も、亘のご両親も喜んでくれたし、何よりも環奈が一番喜んでくれたのに。
同時に、環奈のことも。
三人はどうしてこんなことになってしまったのだろう。
婚約指輪を外すために繋いでいた手をほどき、わたしは言った。
「これ、外すことにするわ。もう、わたしには必要無い物だもの」
「そこまで無理をする必要はないよ」
隼がすっとんきょうな声で言って触れたそれは、皮肉にも美しい光を放っていた。
九号の、婚約指輪。
純銀色で、あわよくば純白色にも見間違えてしまうほど、美しい輝きを放っていた。
「真央さんは、子供みたいな二十五歳だ」
「心外だわ。でも、そうなのかもしれない」
「思い通りにいかなくて、裏腹な行動に出る子供のような人だ」
「ますます心外だわ」
とわたしは言い、でも、心の底から納得していた。
年下の男に馬鹿にされたのに、わたしは頭にこなかった。
婚約指輪を外そうとして手をかけたのに、いざ外すとなると、わたしはひどく憂鬱になった。
凄まじく、困惑した。
亘の左手の薬指にもサイズ違いの、まったく同じデザインのものがあるだろう。
いや、もう外されているかもしれない。
「三ヶ月分の給料と夏のボーナスを合わせて、奮発したんだ」
そう言って、亘は嬉しそうにわたしの薬指に、これ、をはめてくれた。
わたしの父も母も、亘のご両親も喜んでくれたし、何よりも環奈が一番喜んでくれたのに。