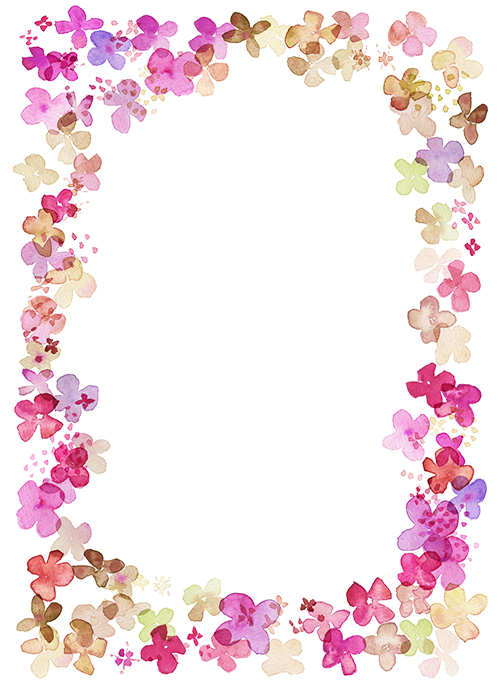ぎくり、としました。
夕飯の席で、母はご飯をよそったついでに、
私にそう聞きました。
「ネックレス」
「箪笥の一番上の引き出しに仕舞って置いたネックレスだよ」
いつも紅い口紅しかつけない母の白い顔は、今日はやつれて見えました。
「お父さんが呉れたネックレスなのよ」
「お父さん」
私は、はっとしました。
箪笥の一番上の引き出しと言うのは、他の引き出しと違って大切なものを入れる場所でした。
青い宝石を入れたベルヴェットの箱。
それは私の母に取って、不可侵の領域でした。
私は急に片腹が痛くなった気になり、箸を止めました。
私の父は、
遠方で独り、教鞭を取っていました。
普段家にいない父を、幼い頃は寂しいとも思いましたが、
いつしかいない事が当たり前で、寂しい気持ちは遠ざかっていました。
しかし、
確かに私はその父と、その母の子供であり、
その片腹と片腹に育まれているのでした。
「お父さんの誕生石なの。サファイアは」
私は急に臓器のひとつが痛み出してその存在を示すように、
食べ物が喉を通らなくなりました。
そして、
「知らない」
そう、答えたのです -
その夜、
私はこっそり、家を抜け出しました。
丸い月がぼんやりと霞む寒い夜でした。
私は駆けて駆けて、通学路の用水路を目指しました。
ふくらんだ稲穂が、重そうに頭を垂れ、ねむっていました。
そして、
その用水路に辿り着いて、私は、目を見張ったのです。
夕飯の席で、母はご飯をよそったついでに、
私にそう聞きました。
「ネックレス」
「箪笥の一番上の引き出しに仕舞って置いたネックレスだよ」
いつも紅い口紅しかつけない母の白い顔は、今日はやつれて見えました。
「お父さんが呉れたネックレスなのよ」
「お父さん」
私は、はっとしました。
箪笥の一番上の引き出しと言うのは、他の引き出しと違って大切なものを入れる場所でした。
青い宝石を入れたベルヴェットの箱。
それは私の母に取って、不可侵の領域でした。
私は急に片腹が痛くなった気になり、箸を止めました。
私の父は、
遠方で独り、教鞭を取っていました。
普段家にいない父を、幼い頃は寂しいとも思いましたが、
いつしかいない事が当たり前で、寂しい気持ちは遠ざかっていました。
しかし、
確かに私はその父と、その母の子供であり、
その片腹と片腹に育まれているのでした。
「お父さんの誕生石なの。サファイアは」
私は急に臓器のひとつが痛み出してその存在を示すように、
食べ物が喉を通らなくなりました。
そして、
「知らない」
そう、答えたのです -
その夜、
私はこっそり、家を抜け出しました。
丸い月がぼんやりと霞む寒い夜でした。
私は駆けて駆けて、通学路の用水路を目指しました。
ふくらんだ稲穂が、重そうに頭を垂れ、ねむっていました。
そして、
その用水路に辿り着いて、私は、目を見張ったのです。