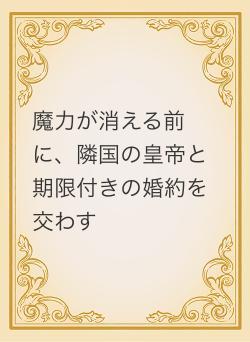私は仕事の合間に佐藤さんの部署をチラチラ見ている自分に気づいた。
仕事のアドバイスをくれるのも、ペンダントを買ってくれたのも、それにどんな意味があるのか、本当のところはわからない。ただの親切かもしれないし、お金がないことを不憫に思ったからかもしれない。好意を寄せられていると勘違いして傷つくのは嫌だ。そう思っても、佐藤さんの存在は私の中で大きくなる一方だった。
佐藤さんの部署は朝から慌ただしく動いていて、定時になっても佐藤さんは席に戻って来なかった。
「昨日のお礼くらいは言いたかったな。」
ふいにそんな言葉が口をついて出てしまった。まるで会いたかったと思っているみたいだ。会社を出て駅へ向かっていたはずなのに、気づいたら堂島屋の前に立っていた。どうやら無意識に来てしまったらしい。
「昨日来たばっかりだけどいっか。」
私はサンチェス=ドマーニのショップへ向かった。
「宮島さん、いらっしゃいませ。」
「すみません、今日も来ちゃいました。」
昨日新作を買ったばかりで金銭的な余裕がないことが丸わかりだが、三上さんは笑顔で出迎えてくれた。
「新しい香水が入ったので試しませんか?」
「是非お願いします!」
香水売り場には豪華な瓶がいくつも並んでいる。その中でもひときわ光を放っている華やかな装飾の瓶に目を引かれた。
「これが新しく出たCitrus D’amourという香水です。」
三上さんがムエットに香水を吹きかけると、爽やかな柑橘系の香りが広がった。今までの香水は甘い香りのものが多く、瓶も小さくて可愛らしい物だった。全体的に女性向けのものが多いように思えたが、この香水は瓶も大きくて男性的な印象を受ける。
「良い香りですね。」
「他のも試してみますか?」
「はい!」
三上さんのご好意に甘えて、いくつかの香水を試したが、Citrus D’amour が一番好きだ。サンチェス=ドマーニの簡単には手が届かない感じにぴったりだ。
(佐藤さんは香水使うのかな……)
ふとそんな考えが浮かんでため息をついてしまった。何かにつけて佐藤さんのことを考えてしまう。もう認めた方が良いのだろうか。佐藤さんのことが──
「宮島さん!」
振り返ると佐藤さんが立っていた。手にはコンビニの袋が握られている。
「今日も残業ですか?」
「ちょっとトラブってて。」
「だから朝からいなかったんですね。」
「もしかして今日も行ったの?」
佐藤さんは堂島屋を指さした。
「はい。」
「いいなぁ。じゃ、またね。」
「はい……失礼します……」
私はふーっと息を吐きだした。佐藤さんと話すのにこんなに緊張したのは初めてだ。今までは何も考えずに話せていたのに、無駄に意識してしまう。好意を向けられているなんて勘違いかもしれないのに、既に自分ではもうどうしようもないくらいに、気持ちが傾いてしまっているみたいだ。
「どうしよう……」
結局その日も佐藤さんのことばかり考えていた。
仕事のアドバイスをくれるのも、ペンダントを買ってくれたのも、それにどんな意味があるのか、本当のところはわからない。ただの親切かもしれないし、お金がないことを不憫に思ったからかもしれない。好意を寄せられていると勘違いして傷つくのは嫌だ。そう思っても、佐藤さんの存在は私の中で大きくなる一方だった。
佐藤さんの部署は朝から慌ただしく動いていて、定時になっても佐藤さんは席に戻って来なかった。
「昨日のお礼くらいは言いたかったな。」
ふいにそんな言葉が口をついて出てしまった。まるで会いたかったと思っているみたいだ。会社を出て駅へ向かっていたはずなのに、気づいたら堂島屋の前に立っていた。どうやら無意識に来てしまったらしい。
「昨日来たばっかりだけどいっか。」
私はサンチェス=ドマーニのショップへ向かった。
「宮島さん、いらっしゃいませ。」
「すみません、今日も来ちゃいました。」
昨日新作を買ったばかりで金銭的な余裕がないことが丸わかりだが、三上さんは笑顔で出迎えてくれた。
「新しい香水が入ったので試しませんか?」
「是非お願いします!」
香水売り場には豪華な瓶がいくつも並んでいる。その中でもひときわ光を放っている華やかな装飾の瓶に目を引かれた。
「これが新しく出たCitrus D’amourという香水です。」
三上さんがムエットに香水を吹きかけると、爽やかな柑橘系の香りが広がった。今までの香水は甘い香りのものが多く、瓶も小さくて可愛らしい物だった。全体的に女性向けのものが多いように思えたが、この香水は瓶も大きくて男性的な印象を受ける。
「良い香りですね。」
「他のも試してみますか?」
「はい!」
三上さんのご好意に甘えて、いくつかの香水を試したが、Citrus D’amour が一番好きだ。サンチェス=ドマーニの簡単には手が届かない感じにぴったりだ。
(佐藤さんは香水使うのかな……)
ふとそんな考えが浮かんでため息をついてしまった。何かにつけて佐藤さんのことを考えてしまう。もう認めた方が良いのだろうか。佐藤さんのことが──
「宮島さん!」
振り返ると佐藤さんが立っていた。手にはコンビニの袋が握られている。
「今日も残業ですか?」
「ちょっとトラブってて。」
「だから朝からいなかったんですね。」
「もしかして今日も行ったの?」
佐藤さんは堂島屋を指さした。
「はい。」
「いいなぁ。じゃ、またね。」
「はい……失礼します……」
私はふーっと息を吐きだした。佐藤さんと話すのにこんなに緊張したのは初めてだ。今までは何も考えずに話せていたのに、無駄に意識してしまう。好意を向けられているなんて勘違いかもしれないのに、既に自分ではもうどうしようもないくらいに、気持ちが傾いてしまっているみたいだ。
「どうしよう……」
結局その日も佐藤さんのことばかり考えていた。