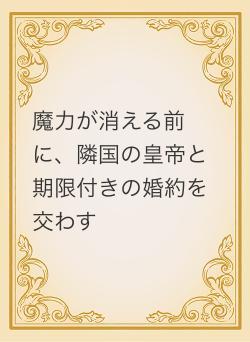週明けはいつも忙しいが、今日はさらに忙しい。欠勤している人もいるし、他の部署も休みがいるからと仕事がまわってきている。休んでいた分を取り戻したいが時間が足りない。
「宮島さん、これもお願いできる?」
「わかりました。やってみます。」
忙しいさきとは対照的に、晃太の部署は落ち着いていた。仕事を終えた晃太は、健斗のBARへ向かった。
「元気ないな。彼女まだ来ないのか?」
「来たんだけど、忙しくてあんま話せないんだよね~」
「元気になって良かったじゃないか。」
晃太はグラスに手をつけず、遠くを見つめてぼーっとしている。こんな晃太を見るのははじめてだ。絶賛恋煩い中という雰囲気が丸出しで、健斗は笑いそうになった。
「なんかずっとさきのことばっかり考えちゃう。今何してんのかなとかさ。」
「連絡したらどうだ?」
「忙しいのに迷惑じゃない?」
「彼氏なんだからいいだろ、それくらい。」
いつもならスマホを両手で持って文章を打ち始めるのに、今日はスマホをじっと見たまま動かない。
「なんだよ。喧嘩でもしたのか?」
「土日に撮影した写真、さきが見たいっていうから送ったんだけど、なんか見てくれてないみたい。待受にして欲しいって思ってるんだけど、やっぱり顔出した俺を受け入れてもらうのは難しいのかなぁ……」
「彼氏を待受にするのは恥ずかしいんじゃないのか?」
「でも、俺に似た犬を待受にしてるんだよ?俺の顔より犬がいいんだよ、さきは。」
「どんな写真を送ったんだ?女と撮った写真なのか?女のモデルとイチャイチャしてるとか。」
「姉ちゃんとは別々で撮影したから一緒には撮ってない。デートしてるシチュエーションだったから気合い入れて撮ったんだけどな。」
読者を相手にデートしている写真を撮影したのだろう。そんな最高のシチュエーションの写真を彼女が拒むはずはない。
「晃太、さきさんへ送った写真を見せてくれ。」
「いいけど……」
晃太は健斗にスマホを差し出した。
「うっわ……」
写真を見た健斗は、かつて晃太が女に追われて店に駆け込んで来た時の衝撃を思い出した。へとへとで冴えないサラリーマンに見えるが、元は立っているだけで女が寄ってくる磁石のような男なのだ。
「驚いただろうな、急にこんなのが送られてきて……」
「驚くとかじゃない。直視できないから免疫をつけてるって言うんだよ。わけがわからない。」
健斗は吹き出した。
「免疫!さきさんは、そんなこと言ったのか!あははは!」
「そんなに嫌なのかな……」
晃太はどうして彼女がそんなことを言うのかわかっていない。病気のウイルスみたいに、悪いモノの抗体を作っているとでも思っているのかもしれない。健斗は笑いが止まらなかった。
「宮島さん、これもお願いできる?」
「わかりました。やってみます。」
忙しいさきとは対照的に、晃太の部署は落ち着いていた。仕事を終えた晃太は、健斗のBARへ向かった。
「元気ないな。彼女まだ来ないのか?」
「来たんだけど、忙しくてあんま話せないんだよね~」
「元気になって良かったじゃないか。」
晃太はグラスに手をつけず、遠くを見つめてぼーっとしている。こんな晃太を見るのははじめてだ。絶賛恋煩い中という雰囲気が丸出しで、健斗は笑いそうになった。
「なんかずっとさきのことばっかり考えちゃう。今何してんのかなとかさ。」
「連絡したらどうだ?」
「忙しいのに迷惑じゃない?」
「彼氏なんだからいいだろ、それくらい。」
いつもならスマホを両手で持って文章を打ち始めるのに、今日はスマホをじっと見たまま動かない。
「なんだよ。喧嘩でもしたのか?」
「土日に撮影した写真、さきが見たいっていうから送ったんだけど、なんか見てくれてないみたい。待受にして欲しいって思ってるんだけど、やっぱり顔出した俺を受け入れてもらうのは難しいのかなぁ……」
「彼氏を待受にするのは恥ずかしいんじゃないのか?」
「でも、俺に似た犬を待受にしてるんだよ?俺の顔より犬がいいんだよ、さきは。」
「どんな写真を送ったんだ?女と撮った写真なのか?女のモデルとイチャイチャしてるとか。」
「姉ちゃんとは別々で撮影したから一緒には撮ってない。デートしてるシチュエーションだったから気合い入れて撮ったんだけどな。」
読者を相手にデートしている写真を撮影したのだろう。そんな最高のシチュエーションの写真を彼女が拒むはずはない。
「晃太、さきさんへ送った写真を見せてくれ。」
「いいけど……」
晃太は健斗にスマホを差し出した。
「うっわ……」
写真を見た健斗は、かつて晃太が女に追われて店に駆け込んで来た時の衝撃を思い出した。へとへとで冴えないサラリーマンに見えるが、元は立っているだけで女が寄ってくる磁石のような男なのだ。
「驚いただろうな、急にこんなのが送られてきて……」
「驚くとかじゃない。直視できないから免疫をつけてるって言うんだよ。わけがわからない。」
健斗は吹き出した。
「免疫!さきさんは、そんなこと言ったのか!あははは!」
「そんなに嫌なのかな……」
晃太はどうして彼女がそんなことを言うのかわかっていない。病気のウイルスみたいに、悪いモノの抗体を作っているとでも思っているのかもしれない。健斗は笑いが止まらなかった。