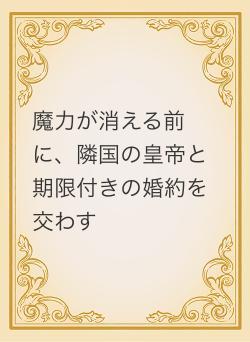「佐藤さん?」
思わず声に出てしまった。佐藤さんも私に気づいたようでこちらへやってきた。
「宮島さん、ここで何してるの?」
「買い物ですけど、佐藤さんは?」
「俺も買い物だけど……?」
私は佐藤さんのスーツをそれとなく見てしまった。サンチェス=ドマーニで販売されているメンズのスーツは奇抜で派手な色が多い。何しろ今回のメンズ新作は真っ赤なスーツだ。佐藤さんがサンチェス=ドマーニを着ている姿は想像つかない。
「何見てるの?あ、新作とお揃いのペンダントだね。これを買うの?」
「いえ、迷っていて……新作のワンピースと一緒に買うにはさすがにお金が……」
「新作のアクセサリーは高いもんね。でも、アクセサリーって早く買わないと売り切れちゃうんだよ。」
三上さんに続き、2人目の悪魔が登場した。洋服は売り切れても再入荷されることもあるが、アクセサリーは製造個数が少ないため売れてしまったら二度と入って来ない。他の店舗から取り寄せることはできるが、人気のアクセサリーというのは、どこの店舗でも売り切れているものなのだ。
私は過去に痛い目を見ている。予算の都合で買えなかったアクセサリーを後日買いに来たら売り切れていた。あんな悔しい思いは二度としたくないけれど、予算が無いことは事実。新作のワンピースは買えるのだから今日はそれで満足するしかない。
「でも、今日はワンピースだけにしておきます。」
「ペンダントは諦めるの?」
「仕方ありません。今日は新作を買いに来たので大丈夫です。」
「じゃ、俺が買ってあげる。三上さん、お願いします。」
「かしこまりました。」
三上さんはてきぱきとペンダントを準備してレジへ向かってしまう。
「え?なんで?どうしてですか?どうして佐藤さんが私のペンダントを買うんですか?」
「アクセサリーは早い者勝ちなんだ。欲しいと思ったらすぐ買わないと、次に来た時は無いんだから。」
それは知っている。でも佐藤さんに買ってもらう理由はない。私は急いで新作のワンピースの会計を終えて、佐藤さんと一緒にショップを出た。
「はい、これ。」
「ありがとうございます……」
私は佐藤さんからペンダントを受け取った。三上さんが綺麗にプレゼント包装を施してくれたから、佐藤さんからの贈り物みたいに見えるけれど、これはプレゼントではなく借金だ。
「ちゃんと払いますから、ちょっと待ってくださいね。」
「そんなのいいよ。」
「こんな高価な物をもらうわけにはいきません。」
ペンダントの価格は見ていないけれど、新作のワンピースと同じくらい高価なはずだ。
「じゃぁ、代わりにこれもらってくれない?」
佐藤さんはカバンの中からチケットのようなものを取り出して、私の前に差し出した。何気なく受け取った私は目を疑った。チケットには『サンチェス=ドマーニ レセプション』と書かれている。
「レセプション!?」
「2枚あって困ってたんだよね。」
レセプションに招待されるなんて、佐藤さんはどれだけサンチェス=ドマーニを持っているのだろうか。同じ職場のなのに、この経済格差は納得できない。不動産でも持っているのか?もしくは投資?副業?わからないけど、大金持ちであることは確かだ。
「佐藤さんと一緒に行くんですか?」
「いや、俺は1人で行くから……」
「あ、そうですか。」
(あれ、なんで私ショック受けてるんだろ。)
「新作は毎回買ってるの?」
「いえ、さすがに毎回買えなくて……貯金をして買えるようになったら買うって感じです。」
「いつも堂島屋のショップ?」
「はい。」
「そうなんだ。はじめて会ったよね。」
「佐藤さんは何を買ったんですか?」
「新作だよ。」
「あれを着るんですか?」
「うん。そうだけど……?」
私の頭の中に赤いスーツを着た佐藤さんが現れた。佐藤さんは長身で細身。確かに独創的なサンチェス=ドマーニを着こなす条件はそろっている。意外と素晴らしい着こなしをするかもしれない。
「じゃ、また明日。」
「ありがとうございました。」
私は佐藤さんに深々と頭を下げた。佐藤さんは改札には入らずに駅とは反対方向へ向かって歩いていた。
(そうだ、佐藤さん地下鉄だった!)
しれっと送ってくれたことに気づいて、私の心臓はいつかのようにドキドキし始めた。
サンチェス=ドマーニの服を買った日は、ひとりファッションショーをすることが恒例だ。私は帰宅するなり買ったばかりのワンピースに着替えて鏡の前に立ち、ひらひらさせたり、くるくる回ったりして、新作のワンピースを堪能した。
テーブルの上には佐藤さんに買ってもらったペンダントの箱がある。まさか買ってもらえるとは思わなかった。おまけにレセプションのチケットまでもらってしまった。
(好かれてるなんて思ったら、自惚れかな……)
私はペンダントの箱を開いて、輝きを放つペンダントをうっとりと眺めた。
思わず声に出てしまった。佐藤さんも私に気づいたようでこちらへやってきた。
「宮島さん、ここで何してるの?」
「買い物ですけど、佐藤さんは?」
「俺も買い物だけど……?」
私は佐藤さんのスーツをそれとなく見てしまった。サンチェス=ドマーニで販売されているメンズのスーツは奇抜で派手な色が多い。何しろ今回のメンズ新作は真っ赤なスーツだ。佐藤さんがサンチェス=ドマーニを着ている姿は想像つかない。
「何見てるの?あ、新作とお揃いのペンダントだね。これを買うの?」
「いえ、迷っていて……新作のワンピースと一緒に買うにはさすがにお金が……」
「新作のアクセサリーは高いもんね。でも、アクセサリーって早く買わないと売り切れちゃうんだよ。」
三上さんに続き、2人目の悪魔が登場した。洋服は売り切れても再入荷されることもあるが、アクセサリーは製造個数が少ないため売れてしまったら二度と入って来ない。他の店舗から取り寄せることはできるが、人気のアクセサリーというのは、どこの店舗でも売り切れているものなのだ。
私は過去に痛い目を見ている。予算の都合で買えなかったアクセサリーを後日買いに来たら売り切れていた。あんな悔しい思いは二度としたくないけれど、予算が無いことは事実。新作のワンピースは買えるのだから今日はそれで満足するしかない。
「でも、今日はワンピースだけにしておきます。」
「ペンダントは諦めるの?」
「仕方ありません。今日は新作を買いに来たので大丈夫です。」
「じゃ、俺が買ってあげる。三上さん、お願いします。」
「かしこまりました。」
三上さんはてきぱきとペンダントを準備してレジへ向かってしまう。
「え?なんで?どうしてですか?どうして佐藤さんが私のペンダントを買うんですか?」
「アクセサリーは早い者勝ちなんだ。欲しいと思ったらすぐ買わないと、次に来た時は無いんだから。」
それは知っている。でも佐藤さんに買ってもらう理由はない。私は急いで新作のワンピースの会計を終えて、佐藤さんと一緒にショップを出た。
「はい、これ。」
「ありがとうございます……」
私は佐藤さんからペンダントを受け取った。三上さんが綺麗にプレゼント包装を施してくれたから、佐藤さんからの贈り物みたいに見えるけれど、これはプレゼントではなく借金だ。
「ちゃんと払いますから、ちょっと待ってくださいね。」
「そんなのいいよ。」
「こんな高価な物をもらうわけにはいきません。」
ペンダントの価格は見ていないけれど、新作のワンピースと同じくらい高価なはずだ。
「じゃぁ、代わりにこれもらってくれない?」
佐藤さんはカバンの中からチケットのようなものを取り出して、私の前に差し出した。何気なく受け取った私は目を疑った。チケットには『サンチェス=ドマーニ レセプション』と書かれている。
「レセプション!?」
「2枚あって困ってたんだよね。」
レセプションに招待されるなんて、佐藤さんはどれだけサンチェス=ドマーニを持っているのだろうか。同じ職場のなのに、この経済格差は納得できない。不動産でも持っているのか?もしくは投資?副業?わからないけど、大金持ちであることは確かだ。
「佐藤さんと一緒に行くんですか?」
「いや、俺は1人で行くから……」
「あ、そうですか。」
(あれ、なんで私ショック受けてるんだろ。)
「新作は毎回買ってるの?」
「いえ、さすがに毎回買えなくて……貯金をして買えるようになったら買うって感じです。」
「いつも堂島屋のショップ?」
「はい。」
「そうなんだ。はじめて会ったよね。」
「佐藤さんは何を買ったんですか?」
「新作だよ。」
「あれを着るんですか?」
「うん。そうだけど……?」
私の頭の中に赤いスーツを着た佐藤さんが現れた。佐藤さんは長身で細身。確かに独創的なサンチェス=ドマーニを着こなす条件はそろっている。意外と素晴らしい着こなしをするかもしれない。
「じゃ、また明日。」
「ありがとうございました。」
私は佐藤さんに深々と頭を下げた。佐藤さんは改札には入らずに駅とは反対方向へ向かって歩いていた。
(そうだ、佐藤さん地下鉄だった!)
しれっと送ってくれたことに気づいて、私の心臓はいつかのようにドキドキし始めた。
サンチェス=ドマーニの服を買った日は、ひとりファッションショーをすることが恒例だ。私は帰宅するなり買ったばかりのワンピースに着替えて鏡の前に立ち、ひらひらさせたり、くるくる回ったりして、新作のワンピースを堪能した。
テーブルの上には佐藤さんに買ってもらったペンダントの箱がある。まさか買ってもらえるとは思わなかった。おまけにレセプションのチケットまでもらってしまった。
(好かれてるなんて思ったら、自惚れかな……)
私はペンダントの箱を開いて、輝きを放つペンダントをうっとりと眺めた。