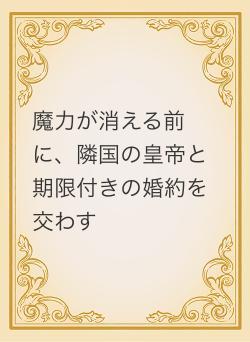「次はファッションショーだよ。こっち来て。」
「ファッションショーがあるんですか!?」
「ここから見るのが好きなんだよね。」
彼が陣取ったのは後方の壁際だった。女性から隠れたくてこんな場所を選んだのかと思ったが、単純にファッションショーが見やすい場所を確保しただけのようだった。
「最初は次回の新作だよ。」
「そっか!お店に出る前にわかるんですね!」
私は両手を握りしめて食い入るようにランウェイを歩くモデル見つめた。
「おぉー!これがお店に出るんですか?」
「そうだと思う。次は青だね。」
「綺麗な色……あのスーツは去年出たやつの色違いですよね。」
「本当だ。新色かぁ。いいね。」
モテ男と私は住む世界が違うけれど、サンチェス=ドマーニが好きだという点では同じらしい。私は披露されていく作品を、あーだこーだ言いながら彼と一緒にファッションショーを楽しんだ。
「次も一緒に見ようよ。」
「女性の反感を買いたくありませんので、遠慮しておきます。」
「なんだ、残念。」
彼はずいぶんと悲しそうな顔をした。モテ男だから断られることに慣れていないのだろうか。
「彼女と来ればいいじゃないですか。」
「彼女なんていないよ。」
「そうやって本命を決めないから、勘違いされるんですよ。」
「俺は君がいいんだけど?」
あんなに女性が寄ってくるのに彼女がいないなんてありえない。あえて特定の相手を作らないのかもしれない。やっぱりモテる人の世界は理解できない。
「あーごめん!」
「またですか!?」
私は彼に抱きしめられて心を無にした。
「私、ずっと待ってたんだけど。」
「何度言えばわかるんだよ。彼女がいるって言ってるだろ?」
最後の女の人はいつまでもグダグダ言っていた。私は何もすることができずに彼の腕の中でただ時間が経つのをじっと待っていた。するとどこからともなく美味しそうな匂いが漂ってきた。この後は食事の時間なのかもしれない。
ようやく女性がいなくなると、彼は私を解放して大きなため息をついた。
「助かった~……あの人何言っても全然聞いてくれなくてさ。でも今日は彼女を見せることができたから大丈夫だと思う。宮島さんがいてくれて良かった~」
私は言葉を失った。どうしてこのモテ男は私の名前を知っているのだろうか。名前なんて一度も言っていないのに。
(そういうことか……)
佐藤さんが仕事で来られなくなったから代わりに来たなんて言ってたけど、あれは嘘だ。私の目の前にいるモテ男はきっと──
「佐藤さんなんですね……」
「え?」
「心配したんですからね。来られなくなったって言われて、休出になったんじゃないかと思って……最初から教えてくれればよかったのに……」
騙されたみたいで悔しい。
「宮島さん、あの……これは……」
「すみません、失礼します。」
ぐっと涙がこみ上げてきて、私は会場を飛び出した。
「ファッションショーがあるんですか!?」
「ここから見るのが好きなんだよね。」
彼が陣取ったのは後方の壁際だった。女性から隠れたくてこんな場所を選んだのかと思ったが、単純にファッションショーが見やすい場所を確保しただけのようだった。
「最初は次回の新作だよ。」
「そっか!お店に出る前にわかるんですね!」
私は両手を握りしめて食い入るようにランウェイを歩くモデル見つめた。
「おぉー!これがお店に出るんですか?」
「そうだと思う。次は青だね。」
「綺麗な色……あのスーツは去年出たやつの色違いですよね。」
「本当だ。新色かぁ。いいね。」
モテ男と私は住む世界が違うけれど、サンチェス=ドマーニが好きだという点では同じらしい。私は披露されていく作品を、あーだこーだ言いながら彼と一緒にファッションショーを楽しんだ。
「次も一緒に見ようよ。」
「女性の反感を買いたくありませんので、遠慮しておきます。」
「なんだ、残念。」
彼はずいぶんと悲しそうな顔をした。モテ男だから断られることに慣れていないのだろうか。
「彼女と来ればいいじゃないですか。」
「彼女なんていないよ。」
「そうやって本命を決めないから、勘違いされるんですよ。」
「俺は君がいいんだけど?」
あんなに女性が寄ってくるのに彼女がいないなんてありえない。あえて特定の相手を作らないのかもしれない。やっぱりモテる人の世界は理解できない。
「あーごめん!」
「またですか!?」
私は彼に抱きしめられて心を無にした。
「私、ずっと待ってたんだけど。」
「何度言えばわかるんだよ。彼女がいるって言ってるだろ?」
最後の女の人はいつまでもグダグダ言っていた。私は何もすることができずに彼の腕の中でただ時間が経つのをじっと待っていた。するとどこからともなく美味しそうな匂いが漂ってきた。この後は食事の時間なのかもしれない。
ようやく女性がいなくなると、彼は私を解放して大きなため息をついた。
「助かった~……あの人何言っても全然聞いてくれなくてさ。でも今日は彼女を見せることができたから大丈夫だと思う。宮島さんがいてくれて良かった~」
私は言葉を失った。どうしてこのモテ男は私の名前を知っているのだろうか。名前なんて一度も言っていないのに。
(そういうことか……)
佐藤さんが仕事で来られなくなったから代わりに来たなんて言ってたけど、あれは嘘だ。私の目の前にいるモテ男はきっと──
「佐藤さんなんですね……」
「え?」
「心配したんですからね。来られなくなったって言われて、休出になったんじゃないかと思って……最初から教えてくれればよかったのに……」
騙されたみたいで悔しい。
「宮島さん、あの……これは……」
「すみません、失礼します。」
ぐっと涙がこみ上げてきて、私は会場を飛び出した。