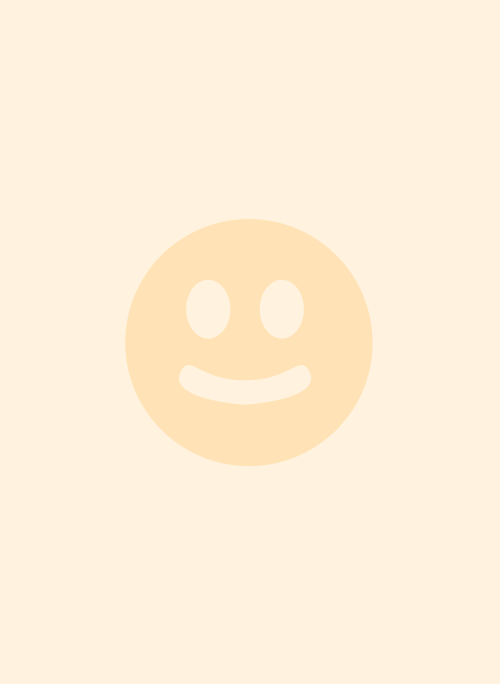「……寂しい、に決まってるでしょ……」
その言葉がこぼれた瞬間、橘の目がわずかに揺れた気がした。
「……そっか」
小さく呟いた橘が、ふっと微笑む。
「なら、ちょっとくらい引き止めてくれたらいいのに」
「なっ……!?」
思わず顔が熱くなる。
「だ、誰がそんなこと……!」
「言わないんですか?」
「……っ」
橘の顔が近い。
「先生がそう言ったら、僕、どうするか分かんないですよ」
冗談みたいに笑いながら、でもその目はどこか真剣で。
「……」
喉が詰まって、言葉が出てこない。
「まぁ、決まるまではまだ時間あるんで」
ふいに距離を戻して、橘はいつもの軽い調子で言った。
「それまでに、ちゃんと考えてくださいね」
そして、何事もなかったように原稿を指さす。
「とりあえず、そろそろ仕事しましょうか、先生?」
「……っ、うるさい!」
ペンを握り直す手が、まだ少し震えていた。