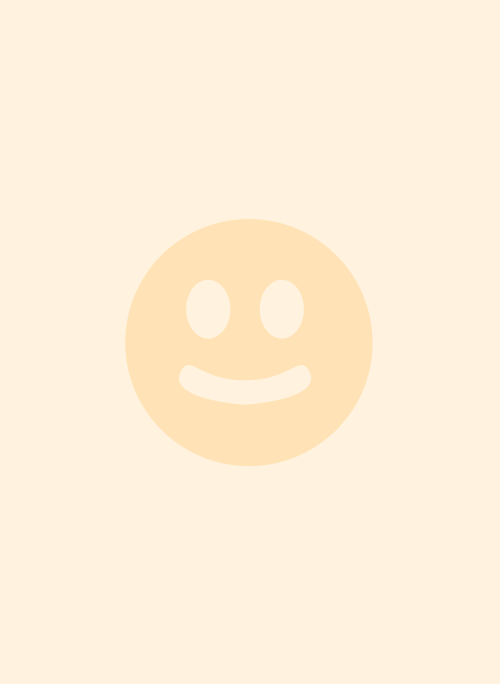「……え?」
「……橘がずっとそばにいてくれたから、描けたんだよ。私、本当にダメダメで、子どもみたいで……それでも、ずっと支えてくれて」
ほんの一瞬、橘の目が揺れる。
「……そんなの当然じゃないですか。僕、先生の担当ですよ」
「でも……“仕事”だけじゃ、できなかったことだって、あるじゃん」
——その言葉の重みを、橘はちゃんと受け止めていた。
沈黙が数秒流れて、やがて、私の口がまた開く。
「ねえ、橘」
「……はい」
「これ、取材とかじゃなくて……個人的な気持ちとして言っていい?」
「もちろんです」
息を吸って、吐いて——
私の目がまっすぐ、橘をとらえた。
「……私、橘のことが、ずっと好きだった」
深夜の空気の中で、その声はやけにクリアで。
でもどこか、震えていて。
橘の心に、真っ直ぐに届いた。
「3年も、一緒にいて。こんなに近くにいて。言えなかったけど……でも、言いたかった。連載が終わったら、最初に伝えたいのは橘だったの」
ほんの少し、目が潤んでいた。
けど、私は泣かなかった。
きちんと、言葉で気持ちを届けた。
そして——
「……橘がずっとそばにいてくれたから、描けたんだよ。私、本当にダメダメで、子どもみたいで……それでも、ずっと支えてくれて」
ほんの一瞬、橘の目が揺れる。
「……そんなの当然じゃないですか。僕、先生の担当ですよ」
「でも……“仕事”だけじゃ、できなかったことだって、あるじゃん」
——その言葉の重みを、橘はちゃんと受け止めていた。
沈黙が数秒流れて、やがて、私の口がまた開く。
「ねえ、橘」
「……はい」
「これ、取材とかじゃなくて……個人的な気持ちとして言っていい?」
「もちろんです」
息を吸って、吐いて——
私の目がまっすぐ、橘をとらえた。
「……私、橘のことが、ずっと好きだった」
深夜の空気の中で、その声はやけにクリアで。
でもどこか、震えていて。
橘の心に、真っ直ぐに届いた。
「3年も、一緒にいて。こんなに近くにいて。言えなかったけど……でも、言いたかった。連載が終わったら、最初に伝えたいのは橘だったの」
ほんの少し、目が潤んでいた。
けど、私は泣かなかった。
きちんと、言葉で気持ちを届けた。
そして——