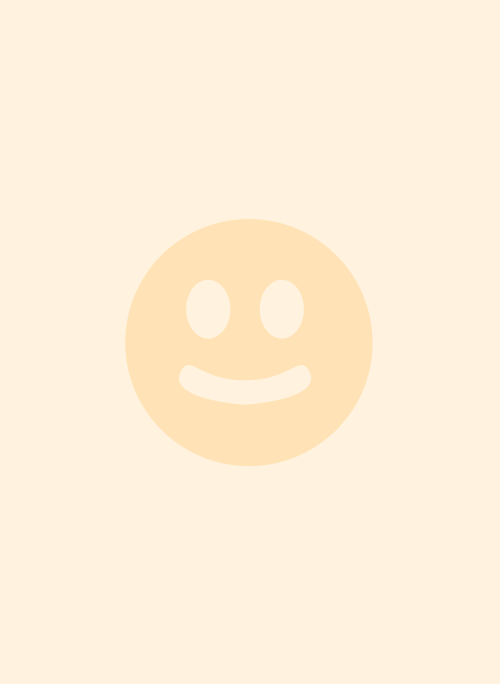ぽつりと落ちた言葉は、やけに静かで、やけに重かった。
橘は黙って頷いた。
言葉をかけるには、まだその余韻が強すぎて。
「……なんかね。まだ、夢みたい」
「3年ですもんね」
「うん、3年。……その間ずっと一緒にやってきて。気づいたら、これが日常になってて……」
言いながら、私は手元を見つめる。
インクの染みた指先、ペンだこ。
それらが、過ぎてきた年月のすべてを物語っていた。
「私ね、途中で何回もやめたいって思ったの」
「知ってますよ。編集部通して“逃亡”された日もありましたし」
「……うっ、あったね……」
「でも、やめなかった。先生は、やめなかったんです」
「それは……」
私は、少し言葉を詰まらせて。
「それは、橘がいたから」
橘は黙って頷いた。
言葉をかけるには、まだその余韻が強すぎて。
「……なんかね。まだ、夢みたい」
「3年ですもんね」
「うん、3年。……その間ずっと一緒にやってきて。気づいたら、これが日常になってて……」
言いながら、私は手元を見つめる。
インクの染みた指先、ペンだこ。
それらが、過ぎてきた年月のすべてを物語っていた。
「私ね、途中で何回もやめたいって思ったの」
「知ってますよ。編集部通して“逃亡”された日もありましたし」
「……うっ、あったね……」
「でも、やめなかった。先生は、やめなかったんです」
「それは……」
私は、少し言葉を詰まらせて。
「それは、橘がいたから」