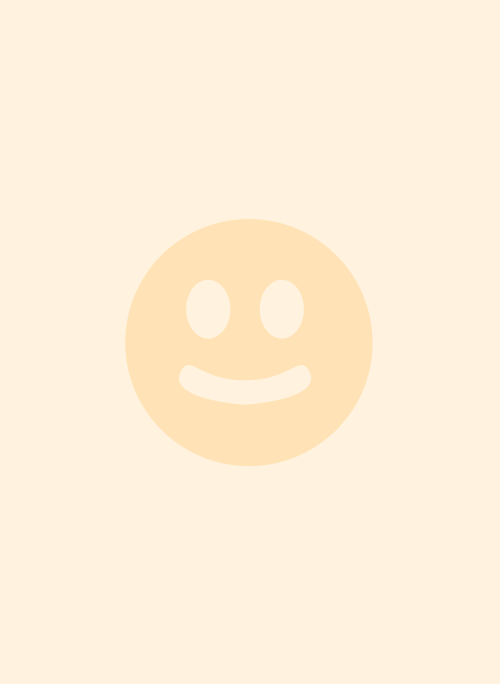ピンポーン。
玄関のチャイムが鳴る音が、いつもより大きく聞こえた気がした。
私は、ゆっくりと立ち上がり、ドアの前へ向かう。
深呼吸して、震える指でドアノブに触れる。
「……来た、んだね」
「ええ、先生が呼んだんでしょう?」
橘はいつもの余裕のある笑みを浮かべていた。でも、その瞳の奥に、少しだけいつもと違う熱を感じる。
「……あのさ、ほんとに、協力してくれる?」
「もちろん。先生の漫画のためなら、ね」
橘が一歩踏み出す。
そのまま私の手を引いて、部屋の奥へと導いた。
取材。
これはあくまで取材のはずだった。
でも、橘の指が私の頬を撫でた瞬間――その境界線が、音もなく崩れていくのを感じた。