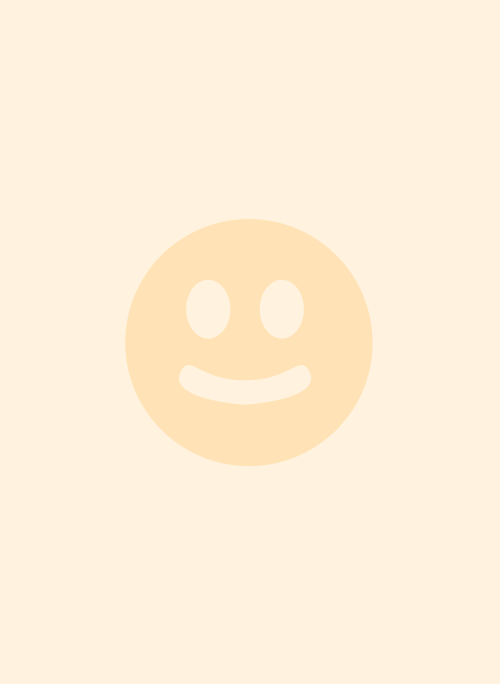「先生、歩くの遅いですね」
「……ヒールなんだから当たり前でしょ」
レストランを出て、ホテルまでの道を歩く。夜風が気持ちいいはずなのに、さっきの橘の言葉がまだ胸に残っていて、なんだか落ち着かない。
「じゃあ、手貸しましょうか?」
「は?」
「こういうとき、普通エスコートするもんですよね?」
橘は、冗談めかした笑みを浮かべながら、手を差し出してきた。
「……いい、そんなのいらない」
「そうですか?」
「そうです」
(な、なんなのよ……!! さっきからいちいち……!!)
「でも先生、さっきから結構ふらついてますよ?」
「……!!」
たしかに、ヒールに慣れてないせいで、ちょっと歩きづらいのは事実。でも、だからって橘に頼るのは……。
「無理しなくていいですよ」
そう言うと、橘は私の手を軽く引いた。
「え、ちょっ……!」
バランスを崩しかけたところを、すぐに支えられる。
(……近い!!!)
肩にまわされた腕。すぐそばで感じる橘の体温。
「これなら安心ですね」
「…………」
(何この状況!? なんで私、橘とこんなに近いの!?)
「先生?」
「……な、なんでもない!!」
振り払う勇気もなく、そのまま橘に支えられながら歩くことになってしまった。
(……これ、完全にペース握られてるじゃない……!!)
夜風が冷たいはずなのに、顔の熱さがまったく引かない。