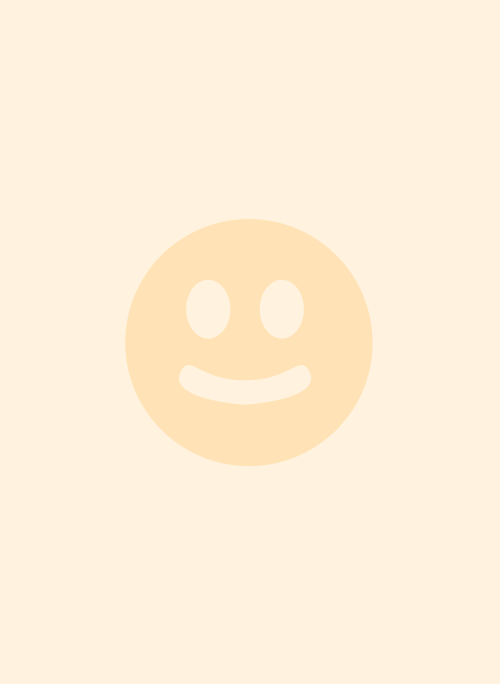「先生、ちょっと口元……」
「え?」
橘がそう言うと、ナプキンを手に取ってスッと私の口元に伸ばしてきた。
「……っ!?」
「ソース、ついてましたよ」
「じ、自分で拭けるし!!」
「そうですか?」
涼しい顔でナプキンを置く橘に、私はもうそれ以上何も言えなかった。
(な、なに今の……!? なんかめっちゃ距離近くなかった!?)
慌ててワインを飲んで気を落ち着けようとするけど、余計に顔が熱くなる気がする。
「先生って、こういう雰囲気の場所、苦手ですよね?」
「……別に」
「でも、さっきからそわそわしてますよ?」
「……してない」
橘はクスッと笑ってグラスを傾けた。
「こういう場所、誰かと来たことあるんですか?」
「は?」
突然の質問に、思わず固まる。
「……そんなの、あるわけないでしょ」
「ですよね」
「なに、その ‘ですよね’ って」
「なんとなく」
なんとなく、って何??
「先生って、仕事のことになるとすぐスイッチ入るけど……こういうのには慣れてないなって」
「……っ」
言い返そうと思ったのに、橘が静かに笑うから、なんだか言葉をなくしてしまった。
「でも、悪くないですよね」
「なにが?」
「こういう雰囲気の中で、先生と食事するの」
「っ……!?」
その言葉に、心臓が跳ねた。
(……なに、それ)
橘はいつもと同じ調子なのに、その言葉だけが妙に胸に残る。
「……そろそろ、ホテル戻る?」
「先生、顔赤いですよ?」
「うるさい!!」
橘の前では、どうしてこんなにペースを乱されるんだろう。