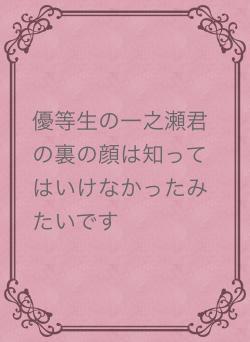「……すみませんでした」
ようやく泣き止んだフェリシアンさんは、赤い目でこちらを見ながら、至極気まずそうに言う。
「いえ、気にしないでください。人を刺したくなることくらい、誰にでもありますから」
「誰にでもはないと思いますけれど……。寛大なお言葉ありがとうございます」
フェリシアンさんはそう言うと、深々と頭を下げた。
「いえいえ」
「あなたが母と仲良くしてくれたことも、母のためにお屋敷をきれいにしようとしてくれたことも本当だったんですね。すみません。正直、呪いの屋敷に幽霊が出たなんておもしろがって言っているとばかり思っていました」
「まぁ。お母様のことをそんな悪ふざけに使われていると思ったら、不愉快にもなりますよね。気持ちはわかります」
そう言うと、フェリシアンさんは弱々しく笑って、「ありがとうございます」とまた頭を下げた。
私はさっきからずっと気になっていたことを尋ねる。
「フェリシアンさん。私、リュシアン様からあなたは十四歳の時に馬車の落下事故で亡くなったと聞いたのですけれど……」
「あぁ、それは死を偽装したんです。その時にはいつかルナール公爵家や、母に命を救われておいて公爵が母を幽閉するのをあっさり認めた王家に復讐する気でいましたから……。わざと馬車を崖に落下させ、血をつけた服を崖に生える木に引っ掛けてから遠くの町に逃げたんです。それからずっと別人として暮らして来ました」
「そうですか、そんなに前から……」
現在の私よりも三つも年下の十四歳の子が、名前を捨てて別人として生きるなんて。相当な覚悟が必要だったはずだ。フェリシアンさんの覚悟を思うと、言葉が出なかった。
しかし、「母に命を救われておいて」とはどういう意味だろう。
「二十年前の事件が、俺にはどうしても納得できませんでした。何を捨ててでも、誰を犠牲にしてでもあいつらに復讐してやりたかった。……無関係のあなたを巻き込んでしまい申し訳ありませんでした」
「いいですってば。さっきから謝ってばかりですよ」
フェリシアンさんはそう言ってもまだ申し訳なさそうにしていたけれど、私は全く怒っていなかった。
というか、私に彼を責める権利などないのだ。だって私は、彼ほど深い事情もなく人を傷つけてしまうようなクズだし。
「それより、フェリシアンさん。私、二十年前の事件やあなたがどうやって監視係になったかがとても気になるんですが……教えてくれませんか?」
尋ねると、フェリシアンさんは真剣な顔でうなずいた。
***
俺には物心ついた頃から父がおらず、母は一人で俺を育ててくれました。
父も母も子爵家の生まれでしたが、母はどちらの家にも寄り付かず、俺たちは小さな村で平民と同じように暮らしていました。
母は公爵家で侍女をしていました。
母の生家には以前ルナール公爵家で働いていた者がおり、そのつながりで働けることになったそうです。
俺が覚えている限り母の生家に行ったことは一度もありませんが、完全に縁が切れていたわけではなかったのでしょう。
公爵家での仕事は楽ではなかったでしょうが、母は一切疲れを見せませんでした。仕事のある日はほとんど顔を合わせる時間がなかったけれど、休日はずっと一緒にいて、薬草の見分け方や植物の育て方をたくさん教えてくれました。
俺は子供の頃、体が弱かったのですが、母は俺が具合が悪いと言うとすぐに青い薬草を摘んできてお茶にして飲ませてくれました。
その鮮やかな青色をしたお茶を飲むと、体のだるさが引いて、翌日には元気に走り回ることができました。
俺にとって母は、世間で悪意を込めて言われているような悪い魔女ではなく、どんなことも魔法で解決してくれる、偉大な魔法使いに見えていました。
……すみません、話が逸れてしまいましたね。
淡々と公爵家に通っていた母ですが、ある時から考え事をするように黙り込んだり、顔を青ざめさせることが増えました。
俺は当時四歳で、その意味を考えることすらできませんでしたが、母が不安そうな顔をしていると自分も不安になったので、その時のことはよく覚えています。
ようやく泣き止んだフェリシアンさんは、赤い目でこちらを見ながら、至極気まずそうに言う。
「いえ、気にしないでください。人を刺したくなることくらい、誰にでもありますから」
「誰にでもはないと思いますけれど……。寛大なお言葉ありがとうございます」
フェリシアンさんはそう言うと、深々と頭を下げた。
「いえいえ」
「あなたが母と仲良くしてくれたことも、母のためにお屋敷をきれいにしようとしてくれたことも本当だったんですね。すみません。正直、呪いの屋敷に幽霊が出たなんておもしろがって言っているとばかり思っていました」
「まぁ。お母様のことをそんな悪ふざけに使われていると思ったら、不愉快にもなりますよね。気持ちはわかります」
そう言うと、フェリシアンさんは弱々しく笑って、「ありがとうございます」とまた頭を下げた。
私はさっきからずっと気になっていたことを尋ねる。
「フェリシアンさん。私、リュシアン様からあなたは十四歳の時に馬車の落下事故で亡くなったと聞いたのですけれど……」
「あぁ、それは死を偽装したんです。その時にはいつかルナール公爵家や、母に命を救われておいて公爵が母を幽閉するのをあっさり認めた王家に復讐する気でいましたから……。わざと馬車を崖に落下させ、血をつけた服を崖に生える木に引っ掛けてから遠くの町に逃げたんです。それからずっと別人として暮らして来ました」
「そうですか、そんなに前から……」
現在の私よりも三つも年下の十四歳の子が、名前を捨てて別人として生きるなんて。相当な覚悟が必要だったはずだ。フェリシアンさんの覚悟を思うと、言葉が出なかった。
しかし、「母に命を救われておいて」とはどういう意味だろう。
「二十年前の事件が、俺にはどうしても納得できませんでした。何を捨ててでも、誰を犠牲にしてでもあいつらに復讐してやりたかった。……無関係のあなたを巻き込んでしまい申し訳ありませんでした」
「いいですってば。さっきから謝ってばかりですよ」
フェリシアンさんはそう言ってもまだ申し訳なさそうにしていたけれど、私は全く怒っていなかった。
というか、私に彼を責める権利などないのだ。だって私は、彼ほど深い事情もなく人を傷つけてしまうようなクズだし。
「それより、フェリシアンさん。私、二十年前の事件やあなたがどうやって監視係になったかがとても気になるんですが……教えてくれませんか?」
尋ねると、フェリシアンさんは真剣な顔でうなずいた。
***
俺には物心ついた頃から父がおらず、母は一人で俺を育ててくれました。
父も母も子爵家の生まれでしたが、母はどちらの家にも寄り付かず、俺たちは小さな村で平民と同じように暮らしていました。
母は公爵家で侍女をしていました。
母の生家には以前ルナール公爵家で働いていた者がおり、そのつながりで働けることになったそうです。
俺が覚えている限り母の生家に行ったことは一度もありませんが、完全に縁が切れていたわけではなかったのでしょう。
公爵家での仕事は楽ではなかったでしょうが、母は一切疲れを見せませんでした。仕事のある日はほとんど顔を合わせる時間がなかったけれど、休日はずっと一緒にいて、薬草の見分け方や植物の育て方をたくさん教えてくれました。
俺は子供の頃、体が弱かったのですが、母は俺が具合が悪いと言うとすぐに青い薬草を摘んできてお茶にして飲ませてくれました。
その鮮やかな青色をしたお茶を飲むと、体のだるさが引いて、翌日には元気に走り回ることができました。
俺にとって母は、世間で悪意を込めて言われているような悪い魔女ではなく、どんなことも魔法で解決してくれる、偉大な魔法使いに見えていました。
……すみません、話が逸れてしまいましたね。
淡々と公爵家に通っていた母ですが、ある時から考え事をするように黙り込んだり、顔を青ざめさせることが増えました。
俺は当時四歳で、その意味を考えることすらできませんでしたが、母が不安そうな顔をしていると自分も不安になったので、その時のことはよく覚えています。