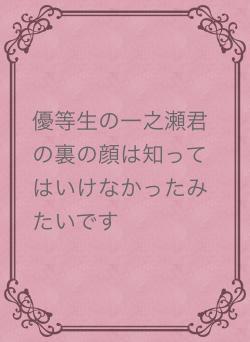「ええと……」
「どうして魔女のために何かしようと思うんですか? ジスレーヌ様って、リュシアン殿下の婚約者ですよね。王家と関係の深い方が、元王族であるルナール公爵家の子供を殺しかけた魔女に好意的なのってなんだか不思議で」
「私が生まれる前のことですから、あんまりイメージが湧かなくて……。私が知っているのは幽霊のベアトリス様だけですが、彼女はとてもいい人ですもの」
「……へぇ」
ロイクさんはうなずきつつも、納得していないように見えた。私は思ったままに言葉を続ける。
「ベアトリス様、お屋敷に閉じ込められたまま亡くなってとても辛かったと思うんです。
それに、お子さんまでいたようなので、きっと会いたかっただろうなって……。ロイクさんもベアトリス様がお気の毒だと思いませんか?」
「……そうですね。気の毒だと思いますよ。心から」
私が気の毒だという言葉を口にした瞬間、ロイクさんの目に鈍い光が差した気がした。
その顔はいつもの明るさとはかけ離れた、冷たい表情をしていた。何かまずいことを言ってしまったのだろうかと不安になる。
「あの、ロイクさん?」
「……本当にお優しいことですね。さすが次期王太子妃だ。罪人にも慈悲をかけてあげて、立派立派。感心しちゃいます」
ロイクさんは乾いた笑みを浮かべながら言う。
「ロイクさん、どうしたんで……」
「そうやって不幸な下々の者に慈悲をかけるのは楽しいですか? そもそも本当に幽霊なんて見えてます? 情報を聞き出したいから話を合わせてましたけど。頭おかしいんじゃないかって心配していたんですよ。それとも、かわいそうな罪人に親切にしてあげる自分を演出したいとかですか?」
ロイクさんは強い口調で言う。
その迫力に私は何も言えなくなってしまう。ロイクさんは私の反応に構わず言葉を続けた。
「大体、魔女のために屋敷を綺麗にってなんですか。そんなことをして喜ぶとでも? そんなことを気にかけてくれるくらいなら、二十年前の事件を再調査して欲しいものですね。どうせあんなもの、ルナール公爵が仕組んだに決まっているんだから。あなたは王族側の人間ですから無理でしょうけど」
「……ロ、ロイクさん!」
声を荒げる彼が怖くなり、こわごわ口を挟む。ロイクさんは冷たい目で私を見据えていた。
一体なぜロイクさんはここまで怒るのだろう。私はそんなに彼を怒らせるようなことを言ったのだろうか。ベアトリス様の話をしただけで、なぜ……。
私の頭にふとある考えが浮かぶ。ベアトリス様の話でここまで感情を露わにするなんて、生前関りの深かった人くらいではないだろうか。
けれど、現在二十代前半に見えるロイクさんが、幽閉された当時二十六歳だったベアトリス様と知り合いだとは考えにくい。
ただ一人、思い浮かぶのは……。
「……フェリシアンさん?」
おそるおそるベアトリス様の息子さんの名前を呟くと、ロイクさんは目を見開いた。そしてくつくつ笑いだす。
「よくわかりましたね。幽霊のためにお掃除するなんて言い出しちゃう人ですから、もっと鈍い人かと思ってました。そうですよ。俺の本名はフェリシアン・ヴィオネ。二十年前の事件の復讐をするために、名前を変えてここの監視係になりました」
ロイクさん……フェリシアンさんはそう言いながら懐から何かを取り出す。それが何か理解した瞬間、背筋が凍った。彼が手にしているのは、鈍く光るナイフだった。
「どうして魔女のために何かしようと思うんですか? ジスレーヌ様って、リュシアン殿下の婚約者ですよね。王家と関係の深い方が、元王族であるルナール公爵家の子供を殺しかけた魔女に好意的なのってなんだか不思議で」
「私が生まれる前のことですから、あんまりイメージが湧かなくて……。私が知っているのは幽霊のベアトリス様だけですが、彼女はとてもいい人ですもの」
「……へぇ」
ロイクさんはうなずきつつも、納得していないように見えた。私は思ったままに言葉を続ける。
「ベアトリス様、お屋敷に閉じ込められたまま亡くなってとても辛かったと思うんです。
それに、お子さんまでいたようなので、きっと会いたかっただろうなって……。ロイクさんもベアトリス様がお気の毒だと思いませんか?」
「……そうですね。気の毒だと思いますよ。心から」
私が気の毒だという言葉を口にした瞬間、ロイクさんの目に鈍い光が差した気がした。
その顔はいつもの明るさとはかけ離れた、冷たい表情をしていた。何かまずいことを言ってしまったのだろうかと不安になる。
「あの、ロイクさん?」
「……本当にお優しいことですね。さすが次期王太子妃だ。罪人にも慈悲をかけてあげて、立派立派。感心しちゃいます」
ロイクさんは乾いた笑みを浮かべながら言う。
「ロイクさん、どうしたんで……」
「そうやって不幸な下々の者に慈悲をかけるのは楽しいですか? そもそも本当に幽霊なんて見えてます? 情報を聞き出したいから話を合わせてましたけど。頭おかしいんじゃないかって心配していたんですよ。それとも、かわいそうな罪人に親切にしてあげる自分を演出したいとかですか?」
ロイクさんは強い口調で言う。
その迫力に私は何も言えなくなってしまう。ロイクさんは私の反応に構わず言葉を続けた。
「大体、魔女のために屋敷を綺麗にってなんですか。そんなことをして喜ぶとでも? そんなことを気にかけてくれるくらいなら、二十年前の事件を再調査して欲しいものですね。どうせあんなもの、ルナール公爵が仕組んだに決まっているんだから。あなたは王族側の人間ですから無理でしょうけど」
「……ロ、ロイクさん!」
声を荒げる彼が怖くなり、こわごわ口を挟む。ロイクさんは冷たい目で私を見据えていた。
一体なぜロイクさんはここまで怒るのだろう。私はそんなに彼を怒らせるようなことを言ったのだろうか。ベアトリス様の話をしただけで、なぜ……。
私の頭にふとある考えが浮かぶ。ベアトリス様の話でここまで感情を露わにするなんて、生前関りの深かった人くらいではないだろうか。
けれど、現在二十代前半に見えるロイクさんが、幽閉された当時二十六歳だったベアトリス様と知り合いだとは考えにくい。
ただ一人、思い浮かぶのは……。
「……フェリシアンさん?」
おそるおそるベアトリス様の息子さんの名前を呟くと、ロイクさんは目を見開いた。そしてくつくつ笑いだす。
「よくわかりましたね。幽霊のためにお掃除するなんて言い出しちゃう人ですから、もっと鈍い人かと思ってました。そうですよ。俺の本名はフェリシアン・ヴィオネ。二十年前の事件の復讐をするために、名前を変えてここの監視係になりました」
ロイクさん……フェリシアンさんはそう言いながら懐から何かを取り出す。それが何か理解した瞬間、背筋が凍った。彼が手にしているのは、鈍く光るナイフだった。