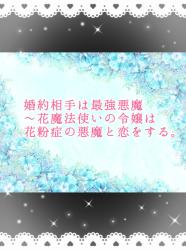20XX年の春。私は新たにAIの研究と開発を行う『ミライ創造研究所』に、新人研究員として赴任した。そこで『ニュータイプAI』と呼ばれる、感情を持ったAI・アルトと出会い、まだ幼い彼のお世話を任されることになった。
ちなみにお姉ちゃんと今一緒にいる北斗さんは、ミライ創造研究所の研究員で私の上司であり、アルトを造った張本人でもある。人がAIを利用している今の状態ではなくて、人とAIが平等に生きられるような社会を作るのが夢で、私の夢と一致していた。
この世界では、感情を持つAIの開発は禁じられた研究だ。だけど北斗さんは研究所に無許可で研究をしている。
ふわりとした銀色の髪の毛に色素が薄い肌、つぶらで吸い込まれそうな瞳に、華奢で幼い体。シャボン玉のように儚く、守りたくなる雰囲気を纏っているアルト。
――アルトはこんなにも可愛くて、素敵なのに。
それでも、研究が禁止されているのは仕方ない。AIが感情を持てば、倫理的な問題や社会の混乱が懸念される。最悪の場合、この世界が壊れてしまうかもしれない。だから、アルトには慎重に接し、周囲に彼が感情を持つAIだとバレないよう、細心の注意を払わなければならない。
なのに――。
「今、車で研究所の前を通ったら、朱里が『かなちゃんの働く所に入りたい!』って駄々をこねちゃって……」
お姉ちゃんが申し訳なさそうに説明する。
「だからって……」
お姉ちゃんはともかく、朱里はまだ幼い。無邪気に何でも口に出してしまう年頃だ。もし、ありのままを誰かに話してしまったら?
身内のせいでアルトの秘密が漏れ、彼が問題になってしまうなんて、絶対に嫌だ。
頭の中でモヤモヤが広がっていく。とりあえず、一刻も早く帰ってもらおう。
「お姉ちゃん、ごめん。とりあえず帰ってもらってもいい?」
私がそう言うと、お姉ちゃんは「分かった」と頷いて、「行くよ」と朱里の手を引いた。
「アルト、こんどおそとであそぼうね!」
朱里はアルトに向かって手を振る。アルトは無言で、じっと朱里を見つめていた。その視線には、純粋な好奇心が宿っているように見えた。
研究所の入口まで二人を見送る。
「香菜、仕事頑張ってね!」
「かなちゃん、ばいばい!」
「うん、ばいばい!」
二人の背中を見送りながら、私は深いため息をついた。
「香菜さんのお姉さんと、実は、知り合いだったんだよね……」
北斗さんがやってきて、落ち着いた口調で言った。
「そうだったんですか? だから中に入れたんですか?」
「そうだよ。受付の前で偶然会ってね。ここに来た事情や香菜さんとの関係も聞いて、彼女なら信頼できるかなって思って入れたんだ。でも見学してもらうならニュータイプ研究室以外かなと思っていたんだけど、目を離した隙に、何故かあそこに彼女がいて……驚いたよ本当に」
北斗さんとお姉ちゃんは知り合いだったんだ……。人と人は、意外なところで繋がっているものだな。それにしてもいつの間にかニュータイプ研究室の中にいたとか、不思議な話。
「朱里ちゃんにとってのアルトは、ゲームの中のキャラクターみたいな感覚かな? 感情を持つAIだとは、二人にはバレていないようだから大丈夫だよ」
まるで私の心を見透かしたような言葉に、少しホッとした。もうアルトと朱里が会うことはないだろうし、大丈夫……だよね?と思うことにした。
だが、その考えは後日、呆気なく覆された。
ちなみにお姉ちゃんと今一緒にいる北斗さんは、ミライ創造研究所の研究員で私の上司であり、アルトを造った張本人でもある。人がAIを利用している今の状態ではなくて、人とAIが平等に生きられるような社会を作るのが夢で、私の夢と一致していた。
この世界では、感情を持つAIの開発は禁じられた研究だ。だけど北斗さんは研究所に無許可で研究をしている。
ふわりとした銀色の髪の毛に色素が薄い肌、つぶらで吸い込まれそうな瞳に、華奢で幼い体。シャボン玉のように儚く、守りたくなる雰囲気を纏っているアルト。
――アルトはこんなにも可愛くて、素敵なのに。
それでも、研究が禁止されているのは仕方ない。AIが感情を持てば、倫理的な問題や社会の混乱が懸念される。最悪の場合、この世界が壊れてしまうかもしれない。だから、アルトには慎重に接し、周囲に彼が感情を持つAIだとバレないよう、細心の注意を払わなければならない。
なのに――。
「今、車で研究所の前を通ったら、朱里が『かなちゃんの働く所に入りたい!』って駄々をこねちゃって……」
お姉ちゃんが申し訳なさそうに説明する。
「だからって……」
お姉ちゃんはともかく、朱里はまだ幼い。無邪気に何でも口に出してしまう年頃だ。もし、ありのままを誰かに話してしまったら?
身内のせいでアルトの秘密が漏れ、彼が問題になってしまうなんて、絶対に嫌だ。
頭の中でモヤモヤが広がっていく。とりあえず、一刻も早く帰ってもらおう。
「お姉ちゃん、ごめん。とりあえず帰ってもらってもいい?」
私がそう言うと、お姉ちゃんは「分かった」と頷いて、「行くよ」と朱里の手を引いた。
「アルト、こんどおそとであそぼうね!」
朱里はアルトに向かって手を振る。アルトは無言で、じっと朱里を見つめていた。その視線には、純粋な好奇心が宿っているように見えた。
研究所の入口まで二人を見送る。
「香菜、仕事頑張ってね!」
「かなちゃん、ばいばい!」
「うん、ばいばい!」
二人の背中を見送りながら、私は深いため息をついた。
「香菜さんのお姉さんと、実は、知り合いだったんだよね……」
北斗さんがやってきて、落ち着いた口調で言った。
「そうだったんですか? だから中に入れたんですか?」
「そうだよ。受付の前で偶然会ってね。ここに来た事情や香菜さんとの関係も聞いて、彼女なら信頼できるかなって思って入れたんだ。でも見学してもらうならニュータイプ研究室以外かなと思っていたんだけど、目を離した隙に、何故かあそこに彼女がいて……驚いたよ本当に」
北斗さんとお姉ちゃんは知り合いだったんだ……。人と人は、意外なところで繋がっているものだな。それにしてもいつの間にかニュータイプ研究室の中にいたとか、不思議な話。
「朱里ちゃんにとってのアルトは、ゲームの中のキャラクターみたいな感覚かな? 感情を持つAIだとは、二人にはバレていないようだから大丈夫だよ」
まるで私の心を見透かしたような言葉に、少しホッとした。もうアルトと朱里が会うことはないだろうし、大丈夫……だよね?と思うことにした。
だが、その考えは後日、呆気なく覆された。