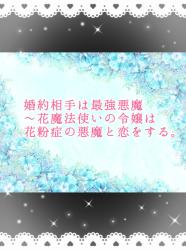「先生、プリン食べようよ」
「そうだね!」
お弁当の前に? と思いながらもクーラーボックスを開けてアルトにひとつ渡した。すぐにアルトはふたをはがし、ひと口頬張った。
「公園で食べるプリン、すごく美味しい!」
アルトを眺めながら私たちもプリンを食べた。
私はこんな風にアルトと一緒に過ごすことができて、嬉しくて、ふふっと声を出して笑った。
「先生、どうしたの? そんなにプリンが美味しいの?」
「それもあるけど、アルトと一緒にピクニックができて、幸せだなぁって先生は考えていたの」
「僕も、すごく幸せだよ!」
アルトの言葉に、心の奥からじんわり温かいものが込み上げてきた。
「先生、僕、アイドルになろうかな」
「アイドル?」
「うん! さっき朱里たちの前で歌って踊っていたらね、人が集まってきてね、僕のことをアイドルだって言ってたの」
「アルトは人に好かれるし全てが可愛いし、アイドルにもなれると思うよ」
心からそう思う。この気持ちは揺るがない。
「僕、アイドルになって、たくさんの人を幸せにしたいんだ!」
アルトは目を輝かせて、未来を語った。
アルトの夢を叶えるためならどんなことだってしたい。ファンクラブの会員ナンバー1となり、コンサートがあれば最前列で応援したい。AI機能を使ったレッスンや、グッズ販売……アイディアだって溢れるほどに色々考えられる。
「あとね、朱里が僕のことをタッチできたんだ!」
「本当に、良かったね!」
「あの日からも僕に会いたいと思ってたんだけど、風邪ひいちゃったらしくて、治ったけれど喧嘩したから来づらかったんだって朱里が言ってた」
ニュータイプ研究室で朱里と鬼ごっこしてたときは、ホログラムのアルトには触れられなくて、タッチしたかしてないかで揉めてたよね。
結局は、お互いに会いたかったのか――。
「今日、義体の姿で来て、良かったね」
アルトは「うん」と、大きく頷いた。
「朱里、ずっとまだ僕と遊びたいって言っていたな……」
「朱里は、アルトのことが大好きそうだよね! 一緒に遊べて良かったね!」
「遊べて良かった。僕も朱里が大好き! みんな大好き! でもね……」
大きく開いたアルトの目が三日月の形になった。
アルトの言葉が止まる。そして私の耳元で呟いてきた。
「先生と一緒にいるときが一番幸せで、一番好きだよ!」
「アルト……」
胸の奥がギュッと締め付けられた。
最近はアルトのことばかりを考えていて、アルトが幸せになる方法をずっと探していた。
アルトが笑っていられるように。
アルトが過ごしやすいように……。
こんな言葉をもらったら、泣きそうだよ。
あぁ、もうダメ。
大量の涙が勝手に溢れてきた。
「先生、何で泣いているの?」
「それはね、アルトが幸せそうで嬉しいからだよ
!」
「先生……」
アルトは私の頭を撫でてくれた。
「いつも泣いているときにも、先生がしてくれることだよ」と言って。
アルトのひとつひとつの言動が心に響く。いつの間にか、こんなにも成長したんだなぁ。
「それじゃあ、お弁当も食べようか?」
北斗さんが微笑みながらそう言うと、私たちはお弁当も食べ始めた。
――なんだか、本当に家族のような温かい空間。
こんな幸せがずっと続けばいいのになと思う。特別なものはいらないから、こんな風に笑いあったり、気持ちを打ち明けたりして。
そのためには、感情を持つニュータイプのAIが世間に認められなくてはならない。今日、私にはアルトが世間に認められ、人間と堂々と仲良くして幸せでいられるような未来がみえた。
きっと、いや、絶対にアルトが幸せになる未来を創るから。
「アルト、先生、頑張るね!」
「うん、僕もアイドルになるための勉強を頑張るね! でも朱里たちにサプライズしたいから、まだ内緒だよ!」
「俺も、アルトがアイドルになるために色々協力するよ」
私たちは微笑みながらお弁当を食べた。アルトは美味しいと言いながら私が作ったお弁当をたくさん食べてくれた。
そして朱里たちが帰る前に、私たちのところにやってきた。
「アルト、また遊ぼうね!」
「朱里は、これからも僕と仲良しでいてくれる?」
「もちろん! アルトのこと、ずっと大好きだよ!」
ふたりのやりとりを眺めていると、嬉しさが溢れてくる。
眩しくてあたたかい日差しが、私たちを優しく包み込んでいた。
☆。.:*・゜
「そうだね!」
お弁当の前に? と思いながらもクーラーボックスを開けてアルトにひとつ渡した。すぐにアルトはふたをはがし、ひと口頬張った。
「公園で食べるプリン、すごく美味しい!」
アルトを眺めながら私たちもプリンを食べた。
私はこんな風にアルトと一緒に過ごすことができて、嬉しくて、ふふっと声を出して笑った。
「先生、どうしたの? そんなにプリンが美味しいの?」
「それもあるけど、アルトと一緒にピクニックができて、幸せだなぁって先生は考えていたの」
「僕も、すごく幸せだよ!」
アルトの言葉に、心の奥からじんわり温かいものが込み上げてきた。
「先生、僕、アイドルになろうかな」
「アイドル?」
「うん! さっき朱里たちの前で歌って踊っていたらね、人が集まってきてね、僕のことをアイドルだって言ってたの」
「アルトは人に好かれるし全てが可愛いし、アイドルにもなれると思うよ」
心からそう思う。この気持ちは揺るがない。
「僕、アイドルになって、たくさんの人を幸せにしたいんだ!」
アルトは目を輝かせて、未来を語った。
アルトの夢を叶えるためならどんなことだってしたい。ファンクラブの会員ナンバー1となり、コンサートがあれば最前列で応援したい。AI機能を使ったレッスンや、グッズ販売……アイディアだって溢れるほどに色々考えられる。
「あとね、朱里が僕のことをタッチできたんだ!」
「本当に、良かったね!」
「あの日からも僕に会いたいと思ってたんだけど、風邪ひいちゃったらしくて、治ったけれど喧嘩したから来づらかったんだって朱里が言ってた」
ニュータイプ研究室で朱里と鬼ごっこしてたときは、ホログラムのアルトには触れられなくて、タッチしたかしてないかで揉めてたよね。
結局は、お互いに会いたかったのか――。
「今日、義体の姿で来て、良かったね」
アルトは「うん」と、大きく頷いた。
「朱里、ずっとまだ僕と遊びたいって言っていたな……」
「朱里は、アルトのことが大好きそうだよね! 一緒に遊べて良かったね!」
「遊べて良かった。僕も朱里が大好き! みんな大好き! でもね……」
大きく開いたアルトの目が三日月の形になった。
アルトの言葉が止まる。そして私の耳元で呟いてきた。
「先生と一緒にいるときが一番幸せで、一番好きだよ!」
「アルト……」
胸の奥がギュッと締め付けられた。
最近はアルトのことばかりを考えていて、アルトが幸せになる方法をずっと探していた。
アルトが笑っていられるように。
アルトが過ごしやすいように……。
こんな言葉をもらったら、泣きそうだよ。
あぁ、もうダメ。
大量の涙が勝手に溢れてきた。
「先生、何で泣いているの?」
「それはね、アルトが幸せそうで嬉しいからだよ
!」
「先生……」
アルトは私の頭を撫でてくれた。
「いつも泣いているときにも、先生がしてくれることだよ」と言って。
アルトのひとつひとつの言動が心に響く。いつの間にか、こんなにも成長したんだなぁ。
「それじゃあ、お弁当も食べようか?」
北斗さんが微笑みながらそう言うと、私たちはお弁当も食べ始めた。
――なんだか、本当に家族のような温かい空間。
こんな幸せがずっと続けばいいのになと思う。特別なものはいらないから、こんな風に笑いあったり、気持ちを打ち明けたりして。
そのためには、感情を持つニュータイプのAIが世間に認められなくてはならない。今日、私にはアルトが世間に認められ、人間と堂々と仲良くして幸せでいられるような未来がみえた。
きっと、いや、絶対にアルトが幸せになる未来を創るから。
「アルト、先生、頑張るね!」
「うん、僕もアイドルになるための勉強を頑張るね! でも朱里たちにサプライズしたいから、まだ内緒だよ!」
「俺も、アルトがアイドルになるために色々協力するよ」
私たちは微笑みながらお弁当を食べた。アルトは美味しいと言いながら私が作ったお弁当をたくさん食べてくれた。
そして朱里たちが帰る前に、私たちのところにやってきた。
「アルト、また遊ぼうね!」
「朱里は、これからも僕と仲良しでいてくれる?」
「もちろん! アルトのこと、ずっと大好きだよ!」
ふたりのやりとりを眺めていると、嬉しさが溢れてくる。
眩しくてあたたかい日差しが、私たちを優しく包み込んでいた。
☆。.:*・゜