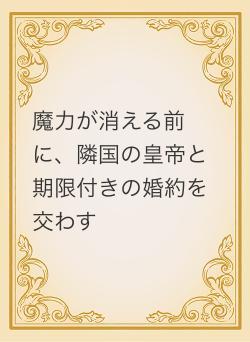放課後になると、教室の中が慌ただしくなった。久しぶりの試合とあって、気合い十分なクラスメイトたちは大声をあげて準備に余念がない。
「紗里奈ー!応援してー!」
「みんな、頑張って!」
「よっしゃー!」
私は校庭に出ていくクラスメイトたちを見送った。でも薫くんは荷物をまとめている。
「薫くんは試合に出ないの?」
「俺苦手なんだよね。」
薫くんは言葉遣いも丁寧だし、学ランもちゃんとボタンを留めてる。赤い髪色を除けばヤンキーには見えない。
「紗里奈、帰ろう?」
「待って、薫くん。ちょっとだけ見てってもいい?」
「試合を見るの!?」
「うん。ちょっとだけ。」
薫くんは険しい顔をしながらも、私の希望を飲んでくれて一緒に校庭へ出た。校庭には、1組と2組の他にも、試合を見るために集まったヤンキーたちが大勢いた。
校庭の中心にいるのは、大和くんと遥くん。向かい合って立っている2人の背後には、それぞれのクラスメイトたちが控えていた。
観客が固唾を飲んで見守る中、試合が始まった。砂埃が舞い上がり、怒号が飛び交う。想像した通りの掴み合い、殴り合いの喧嘩だ。同じクラスの人たちが殴られて倒れていくのは痛々しいけれど、みんなの顔は妙に晴れやかだった。
私は円の中心に立つ人物に釘付けになった。無駄な動きが一切なく、最小限の力で次々に相手を倒していく。余裕があるという一言では片付けられないような、圧倒的な強さ──
徐々に砂埃が落ち着くと、歓声がより一層大きくなった。大和くんの背後には2人のクラスメイトが立っている。遥くんの背後には誰もいない。大和くん率いる1組の勝利が決まった瞬間だった。
「終わったよ。帰ろう、紗里奈。」
「うん……」
私は後ろ髪を引かれながらその場を後にした。
ヤンキー同士の喧嘩なんて初めて見た。殴り合いの喧嘩なんて、見る物ではないと思っていたけれど、クラスメイトたちの清々しい笑顔は印象的だった。
負けてしまった遥くんや2組の人たちも同じように笑っていて、スポーツの試合を見ているような感覚だった。それに──
(大和くんがカッコ良すぎた──!!)
強いことは元より、喧嘩にふさわしくないほど爽やかだった。女子がいたら絶対キャーキャー言われているはずだ。
(この気持ちを共有できる女の子がいたらいいのに!)
学校を出てもドキドキと胸が高鳴り、興奮が醒めない。私は思わず胸を押さえた。
「紗里奈、大丈夫?」
「試合なんて初めて見たから、ちょっと動悸が……」
「そうだよね。あれは女の子が見るもんじゃない。」
「そ、そんなことないと思うよ?みんなイキイキしてたし、みんなの違う一面が見えたからさ……」
大和くんに惚れたなんて知られたら、何を言われるかわからない。私は気持ちを悟られないように、平静を装っていた。しかし──
(ちょっと待って!私、やばいかも!)
一度好きになってしまったら止められない。次の日から頭の中は大和くんでいっぱいだった。教室にいれば大和くんばかりに意識が向いてしまう。授業中はどうしてるのか、休み時間は何してるのか、いちいち気になってしまう。試合があれば、薫くんを無理やり付き合わせて連日試合を観戦した。
(落ち着け私!)
何度も自分に言い聞かせたけれど、気休めにもならない。大和くんへの思いは募るばかりだった。でもそんなある日、夢から覚めるような出来事が起きた。
「紗里奈ー!応援してー!」
「みんな、頑張って!」
「よっしゃー!」
私は校庭に出ていくクラスメイトたちを見送った。でも薫くんは荷物をまとめている。
「薫くんは試合に出ないの?」
「俺苦手なんだよね。」
薫くんは言葉遣いも丁寧だし、学ランもちゃんとボタンを留めてる。赤い髪色を除けばヤンキーには見えない。
「紗里奈、帰ろう?」
「待って、薫くん。ちょっとだけ見てってもいい?」
「試合を見るの!?」
「うん。ちょっとだけ。」
薫くんは険しい顔をしながらも、私の希望を飲んでくれて一緒に校庭へ出た。校庭には、1組と2組の他にも、試合を見るために集まったヤンキーたちが大勢いた。
校庭の中心にいるのは、大和くんと遥くん。向かい合って立っている2人の背後には、それぞれのクラスメイトたちが控えていた。
観客が固唾を飲んで見守る中、試合が始まった。砂埃が舞い上がり、怒号が飛び交う。想像した通りの掴み合い、殴り合いの喧嘩だ。同じクラスの人たちが殴られて倒れていくのは痛々しいけれど、みんなの顔は妙に晴れやかだった。
私は円の中心に立つ人物に釘付けになった。無駄な動きが一切なく、最小限の力で次々に相手を倒していく。余裕があるという一言では片付けられないような、圧倒的な強さ──
徐々に砂埃が落ち着くと、歓声がより一層大きくなった。大和くんの背後には2人のクラスメイトが立っている。遥くんの背後には誰もいない。大和くん率いる1組の勝利が決まった瞬間だった。
「終わったよ。帰ろう、紗里奈。」
「うん……」
私は後ろ髪を引かれながらその場を後にした。
ヤンキー同士の喧嘩なんて初めて見た。殴り合いの喧嘩なんて、見る物ではないと思っていたけれど、クラスメイトたちの清々しい笑顔は印象的だった。
負けてしまった遥くんや2組の人たちも同じように笑っていて、スポーツの試合を見ているような感覚だった。それに──
(大和くんがカッコ良すぎた──!!)
強いことは元より、喧嘩にふさわしくないほど爽やかだった。女子がいたら絶対キャーキャー言われているはずだ。
(この気持ちを共有できる女の子がいたらいいのに!)
学校を出てもドキドキと胸が高鳴り、興奮が醒めない。私は思わず胸を押さえた。
「紗里奈、大丈夫?」
「試合なんて初めて見たから、ちょっと動悸が……」
「そうだよね。あれは女の子が見るもんじゃない。」
「そ、そんなことないと思うよ?みんなイキイキしてたし、みんなの違う一面が見えたからさ……」
大和くんに惚れたなんて知られたら、何を言われるかわからない。私は気持ちを悟られないように、平静を装っていた。しかし──
(ちょっと待って!私、やばいかも!)
一度好きになってしまったら止められない。次の日から頭の中は大和くんでいっぱいだった。教室にいれば大和くんばかりに意識が向いてしまう。授業中はどうしてるのか、休み時間は何してるのか、いちいち気になってしまう。試合があれば、薫くんを無理やり付き合わせて連日試合を観戦した。
(落ち着け私!)
何度も自分に言い聞かせたけれど、気休めにもならない。大和くんへの思いは募るばかりだった。でもそんなある日、夢から覚めるような出来事が起きた。