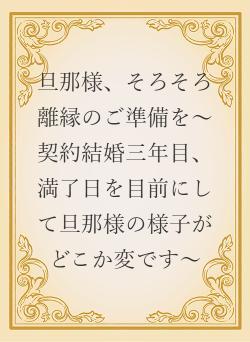「ありがとうございます、殿下。そのような重要なことをお話しくださって。――では、わたくしからも一つ、よろしいですか? わたくしも殿下に、どうしても謝らなければならないことがあるのです」
そう言うと、アレクシスは驚いたように眉を寄せたが、すぐに頷いてくれる。
そんなアレクシスに背中を押され、エリスは、シオンにすら言えなかった気持ちを、口にした。
「今回の件、殿下は何度も、全ては自分のせいだと仰いました。わたくしは何も悪くないと。……でも違うのです。リアム様に隙を与えてしまったのは、どう考えても、わたくし自身なのです。なぜなら、わたくしは――」
「…………」
「わたくしは、この子を身ごもったことを、心から喜ぶことができなかったのですから」
「――!」
それは妊娠が判明したその日から、エリスがずっと、心に秘めていた感情だった。
(わたしが、母親に……?)
妊娠を告げられたその瞬間、エリスの中に真っ先に芽生えた感情は、喜びではなく恐怖だった。
皇子妃として、いつかは子どもを産むことになるだろう――頭ではそう理解していても、実際はもっと先のことだと思っていたからだ。
母親になる覚悟も、準備も、何もできていない。
そもそも、アレクシスは以前、自分に子どもは必要ないと言っていた。それなのに――。
エリスは怖くてたまらなくなった。
子どもは不要だと言った、あの言葉がアレクシスの本音だったら。嫌な顔をされたら。
そのせいで、アレクシスの愛情が自分から遠ざかってしまったら。
父親から愛されなかった自分やシオンと同じ思いを、お腹の子どもにもさせてしまったら。
アレクシスを信じたいのに、どうしても信じきることができない。
シオンや使用人たちから「おめでとう」と言葉を掛けられる度、息が止まりそうになる。
「ありがとう」と答える笑顔の裏で、叫び出したくなる気持ちを必死に抑えていた。
――エリスはどうにかして気を紛らわそうとした。
子どものことを少しでも考えないように。嫌な想像をかき消すように。
そんなときだ。
リアムから、お茶会の招待状が届いたのは。