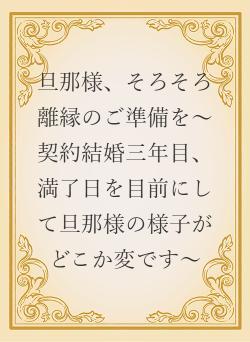◆
幼い頃のオリビアは、リアムを実の兄だと信じ、慕っていた。
日常的にリアムに暴力を振るっていた父親も、オリビアの前では決して暴力を振るわなかったし、リアム自身も、おくびにも出さなかったからだ。
オリビアにとってのリアムは、優しくて頼もしい、絶対的な存在だった。
それが揺らいだのは、オリビアが六歳のとき。
リアムが父親から背中を打たれている場面を、偶然目撃してしまった頃からだろうか。
「お兄さま……大丈夫?」
「……!」
父親の立ち去った部屋に、オリビアが入っていったとき、リアムは心底驚いていた。
当時の幼いオリビアにはわからなかったが、もし今その場面に出くわしたとしたら、リアムは間違いなく『不味いところを見られた』という顔をしていただろう。
「痛い?」
と泣き出しそうに尋ねるオリビアに、「大丈夫、痛くないよ」と微笑んだリアムは、いったい何を思っただろうか。
「どうして、お父さまはお兄さまを打つの?」
「それは……僕が悪い子だからだよ」
「……! そんなことないわ! お兄さまはとってもいい子よ! わたしが、お父さまにいってあげる!」
「……オリビアは優しいね。でも、お父さまには何も言ったらいけないよ。もしまた同じ場面に出くわしても、絶対に部屋に入ってきたら駄目だ」
「どうして?」
「どうしてもだよ」
いつもなら丁寧に説明をしてくれる兄が、何故か理由を教えてくれなかったせいで、その日の会話はオリビアの記憶に深く刻まれた。