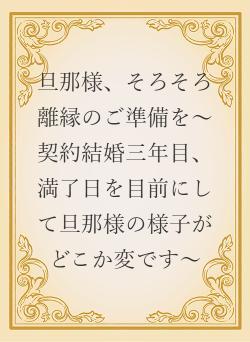◇
そして今、エリスの前には謝罪するシオンの姿があった。
シオンはベッド脇の椅子に座り、
「無断外泊なんてさせてごめんね。エメラルド宮の皆には、僕からちゃんと謝るから」
と、申し訳なさ気に瞼を伏せていた。
それは一見して、いつもと変わらないシオンだった。
――シオンが部屋を訪れてから数分足らず。
昼間に比べ顔に疲れは出ているが、エリスの体調を気遣い、これまでの経緯やオリビアから聞いた最近のリアムのおかしな態度について説明し、自身の突発的な行動を冷静に反省しているところなど、普段のシオンのまま。
声にも乱れはないし、視線も合う。
正直、言うほど思いつめている様子はない。
かと言って、ジークフリートの言葉が勘違いだとも思えなかった。
(わたしの目には、いつも通りのシオンに見える。でもジークフリート殿下は『一晩、側にいてあげて』とまで仰った。……それはつまり、シオンはわたしに本音を隠しているということなの? もしかして、あの日わたしがこの子を追いかけなかったせい?)
「……っ」
刹那、脳裏に過ぎるシオンの泣き顔。
シオンがエメラルド宮を去ったあの日、『姉さんと一緒にいられないなら、生きる意味はない……!』と叫んだ、悲痛な声。
あのときの言葉は、紛れもなくシオンの本心だった。
もう何年も聞いていなかった、シオンの弱音。
そのときエリスは、シオンを心配に思うと同時に、心の底から安堵した。
わたしはまだ、シオンに必要とされている、と。
けれど結局シオンは宮を去り、その後図書館で偶然再会するまで、手紙一つ寄越さなかった。
(あのときはシオンの行動が理解できなかったけれど、もしかしたらシオンは、あれ以上本心を見せたらいけないと思ったのかもしれないわ。わたしが長い間、そう思ってきたのと同じように)
実際のところは、本人に尋ねなければわからない。
けれどもし僅かでも、シオンがそう思っていたのなら――。