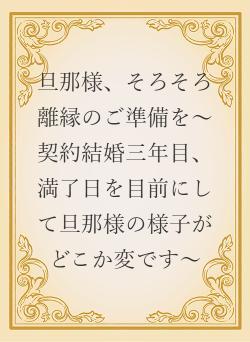それは自白以外の何ものでもなかった。
焦りも後悔も、反省の色一つ映さない。
どころか、アレクシスの反応を愉しむように見据える、かつての友。
『理由などそれで十分だ』と下卑た笑みを浮かべるリアムは、アレクシスの記憶の中のリアムとは、もはや別人だった。
「……リアム、――貴様、本当に……」
信じられなかった。信じたくなかった。
何かの間違いであってくれればと思った。
一刻も早く犯人を捕らえ、エリスの居場所を突き止めねばと思う反面、リアムではない別の誰かの仕業であってくれたらと願っていた。
もしもリアムの仕業であろうとも、リアムの心に自責の念が、あるいは、反省の色を少しでも見せるのなら、たとえ許せずとも、話し合うつもりでいた。
それが、自身の身勝手な気持ちで突き放してしまった友人にできる、唯一の贖罪だと思っていたから。
だが、そのわずかな希望はたった今消えてなくなった。
リアムは明確な悪意を持ってエリスに手を出したのだと――そう、悟ってしまったからだ。
(確かに、こいつにはこいつなりの理由があったのだろう。――だが)
日の光の閉ざされた部屋で、アレクシスはリアムを睨みつける。
「つまり、お前は認めるんだな? エリスについてあらぬ噂を流し、彼女を個室に連れ込んだと」
「ああ、認めよう。エリス妃の不貞の噂を流し、彼女を薬で眠らせ個室に連れ込んだのはこの私だ。全ては、噂を真実にするためにな……!」
「――ッ!」
瞬間、アレクシスの中で、プツリ――と、何かが途切れる音がした。
それは、必死に抑えていたリアムへの殺意が、理性を飲み込んだ瞬間だった。
――この男を、殺さねば、と。
右手が無意識に腰へと伸びる。
鞘に納められていた剣身が姿を現し――その切っ先が、大きく天を仰いだ。
だが――アレクシスが剣を振り下ろした、その瞬間。
「いけません、殿下ッ!」
――と叫び声が聞こえ、リアムの首筋を捉えるはずだった自身の剣が、セドリックによって、寸でのところで止められていた。