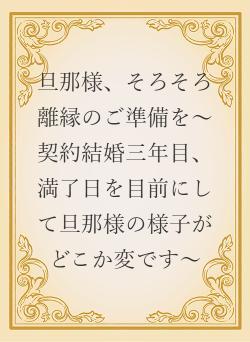すると、その瞬間だった。
今まで取り澄ました顔をしていたリアムが、突如嬉々として目を細め、「フッ」と噴き出すような声を上げたのだ。
そんなリアムの変化に、アレクシスは目を見張る。
「お前、今、笑ったのか?」
「ああ、笑ったよ。今の一言で、エリス妃が君の元にいないとわかったからね。これほど悦ばしいことはないだろう?」
「――何?」
アレクシスは、エリスがエメラルド宮に戻らないのは、当然リアムのせいだと考えていた。
侯爵家のリアムならば、帝国ホテルに部屋を取ることは容易い。
そこにエリスとシオンを軟禁することは、難しいことではないと。
だが、リアムのこの反応は……。
(リアムは、エリスの失踪とは無関係だったのか? それに、こいつの物言いは……)
混乱するアレクシスに、リアムはさも愉快そうな目を向ける。
もはや、隠す意味はないとでも言うように。
「私の目的はね、君を苦しめることなんだよ、アレクシス。オリビアを侮辱された屈辱を、オリビアを失う胸の痛みを、君に与えてやらねば気が済まない」
「……ッ! だからエリスを狙ったと? そんな理由で、何の関係もないエリスを巻き込んだのか!」
「そんな理由だと? ――ああ、そうだろうな。君はそう言うと思っていたよ。生まれながらの皇族である君に、庶子である私の気持ちなど到底理解できるはずがないのだから」
「――っ」
(庶子、だと……?)
刹那、突然リアムの口から飛び出したその言葉に、アレクシスは絶句する。
「君にはわからないだろう。娼婦の腹から生まれた私がどんな風に育てられたか。死んだ兄の身代わりとして、生涯あの男の言いなりになって生きるしかない私の気持ちが。育った孤児院に火を放たれ、かつての友人を皆殺しにされたと知ったときの絶望が……! どうしてお前に理解できる!?」
「……ッ」
「それに、エリス妃はもはや無関係な人間ではない。私は悪魔ではないからな。彼女が私に誠意を見せれば、手を出すのは止めようと決めていた。だが彼女は自身の利益を優先し、私のオリビアへの愛を踏みにじったんだ。理由など、それで十分だろう?」
「――!」