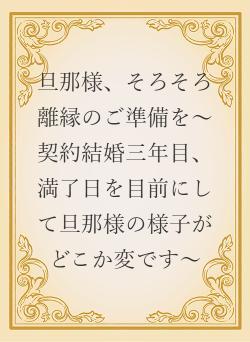「セドリックから聞いたよ。ランデル王国に、恩人を探しに行くんだって?」
「ああ。実は昔、湖に落ちたところを助けられてな。ちゃんと礼を言いたいんだ」
「湖? じゃあもしかして、君が必死に泳ぎを練習してたのって……」
「そうだ。もし会えたら、泳げるようになったところを見せようとな。まぁ、結局泳げず仕舞いだったが」
――十五の夏。
終戦から三年が経ち、兼ねてから希望していたランデル王国への留学の許可が下りたため、アレクシスはランデル王国へと立つことになった。
これはそのときの、アレクシスの記憶の中の最後の会話。
アレクシスが、結局泳げるようにならなかった、と溜め息をつくと、リアムは珍しく、「アハハ!」と大声を上げて笑った。
「まるで溺れてるようにしか見えないもんね、君の泳ぎ。――でもさ、僕は正直安心したんだ。剣も乗馬も射撃も完璧な君にも、ちゃんと苦手なものがあるんだって。僕には得意なこと、何もないからさ」
「そんなことはないだろう。お前の周りには人が集まる。それは立派な才能だ。少なくとも、俺にはないものを、お前は持っている」
「ありがとう。君にそう言ってもらえると自信が湧くよ。――ところで、戻ってきたらどうするの? 軍に入るっていう気持ちは、今も変わらない?」
「ああ」
「そう。それなら僕は、海軍に入って泳ぎを覚えようかな。そうしたら、いつか君の役に立てる日がくるかもしれないから」