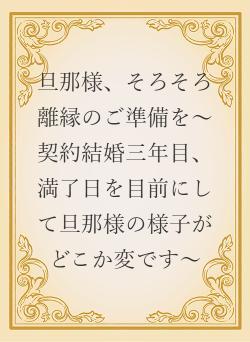だからこそアレクシスは、リアムの本当の目的は何だろうかと疑わなければならなかったが、どれだけ経っても一向に態度を変えることのないリアムに、気付けば警戒心を解いていた。
そうして半年も経つ頃には、互いをファーストネームで呼び合うほどの仲へと進展した。
「ねえ、アレクシス。今度うちに遊びに来ない? 妹の誕生日パーティーをするんだ。勿論、セドリックも一緒にさ」
「妹? 歳はいくつだ」
「次の誕生日で八歳になる。前回の休暇で帰ったとき、妹に君の乗馬が素晴らしかったって話をしたら、凄く興味を持ってね。見てみたいって言うんだよ。だから君さえよければ、妹に君の乗馬姿を見せてあげてほしいんだ」
聞いた瞬間、『面倒だ』という感情を抱いたパーティーの誘いも、結局受けることにしたのは、リアムを信頼していたからだ。
妹というのがまだたったの八歳で、女性としてカウントされなかったことも、理由としてはあっただろうが。
それに、長期休暇中に居場所を提供してくれるリアムは、都合のいい存在でもあった。
当時のアレクシスにとって、寄宿学校や皇子宮は、自身が『扱いづらい皇子』であることを否が応でも知らしめてくる、息の詰まる場所だったからである。
そこから逃げられるのなら、正直どんな場所だろうと構わなかった――そんなアレクシスの気持ちに、リアムはきっと気付いていた。
だからこそリアムは、アレクシスのランデル王国への留学が決まったときも、笑顔で送り出してくれだのだろう。