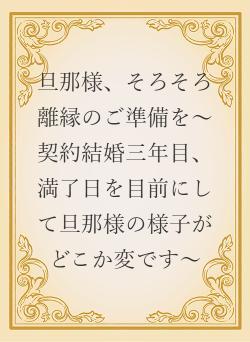◆◆◆
「あれ? ヴィスタリア、今日は一人? セドリックはどうしたの?」
「――あ? ああ、あいつは風邪だ。部屋で寝ている」
「そう。最近は夜が冷えるからね。お大事にって伝えておいて」
「ああ」
入学当初、アレクシスは、生徒たちからも教師たちからも遠巻きにされていた。
その頃はまだ、スタルク王国との戦争が終結したばかり。
ランデル王国の孤児院に身を寄せていたアレクシスとセドリックは自国へと呼び戻され、ようやく日常に戻りかけたその矢先の入学で、後ろ盾もなく、かと言って、第三皇子というあまりにも高い身分ゆえに虐げることも難しいアレクシスのことを、周りが腫れ物扱いするのは当然のことだった。
だがそんな中、リアムだけは、まるで何の事情も知らないような顔で、平然とアレクシスに接していた。
「そう言えば君、もしかしなくても、僕の名前知らなかったりする?」
「…………」
「リアムだよ。リアム・ルクレール。同じ寮なわけだし、名前くらいは覚えてくれると嬉しいな」
リアムは善人だった。
侯爵家の嫡男でありながら、下の階級の者を侮る素振りは一切なく、と同時に、上の者にこびへつらうこともしない。
努力を惜しまず、全てに誠実で前向き。
まるで、善意と正義の塊のような男。
「ヴィスタリア! ここ、席空いてるよ」
「次の移動教室、場所が変更になったって」
「来週提出のレポート、期限が二日早まったらしいよ。間に合いそう?」
胡散臭さも、同情心も、わずかな下心も感じさせない。
それにリアムは、アレクシスに興味関心を持っている態度を見せつつも、決して最後の一線は超えなかった。
彼は、これ以上は踏み込んだらいけないというラインをよくわきまえている様で、アレクシスを決して不快にはしなかった。