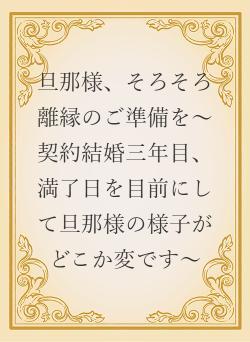「よく来てくれた。掛けてくれ」
「……はい」
事が事だからだろう、マリアンヌの表情は暗い。
アレクシスの知るマリアンヌは、兄妹相手だろうと決して微笑みを絶やさない皇女の鑑のような女性だが、今日のマリアンヌはまるで別人のように静かなのだ。
アレクシスはそんな妹の様子に、マリアンヌがエリスについて、何かを知っているのだと悟った。
アレクシスは執務卓からソファへと移動し、テーブルを挟んでマリアンヌの対面に腰かける。
すると、マリアンヌは挨拶も早々に、二通の手紙をテーブルに置いた。
「これは?」
アレクシスが尋ねると、マリアンヌは神妙な顔で瞼を伏せる。
「どちらも、エリス様からわたくしに宛てられた手紙……と言いたいところですが、右の手紙は、エリス様の名を語った別の者からの、いわゆる、偽物ですの」
「偽物だと? どういうことだ」
マリアンヌの話はこうだった。
昨日、図書館に向かうためにマリアンヌが皇女宮を出る寸前、このような手紙が届いた。
『急用のため、図書館に行けなくなりました。大変申し訳ございません。 エリス』
マリアンヌはそれを読み、多少の違和感を覚えたものの、外出を取り止めた。
だが明朝、セドリックからエリスが帰っていないことを知らされ、慌てて、以前エリスから届いた別の手紙と、筆跡を比べてみたという。
その結果、別人が書いたものであることが判明したのだ。