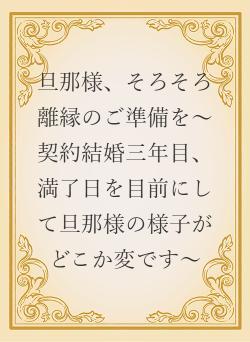「…………」
(こういうとき、殿下ならどうするのかな。『問題ない』って、自信満々に言うんだろうか。宮廷舞踏会で、踊れなくなった姉さんに言ったみたいに)
――いや、流石にそれはないだろう。
なぜって、今回のことは外ならぬ、『アレクシス自身が原因』なのだから。
「……ああ、何かもう、疲れたなぁ」
いっそこのまま、エリスを連れて国外逃亡でもしてしまおうか。
何のしがらみもない場所で、一からやり直すというのも手かもしれない。
そんな、一度は捨てたはずの自分本位な望みが、シオンの中でムクムクと頭をもたげる。
もう、何もかもが面倒だ。
この場所から、エリスと二人逃げ出してしまいたい――そう、心が闇に囚われかける。
だが、そのときだった。
シオンの思考を無理やり現実に引き戻すかのように、何の前触れもなく、耳元に「ふぅっ」と吐息らしきものを吹きかけられたのは。
「――ひッ!?」
刹那、あまりにも突然のことに、シオンは悲鳴を上げて飛び上がった。
と同時に背後で上がる、ケラケラという笑い声。
その屈託のない子供のような声に、シオンは怒りを覚えながら、ゆっくりと背後を振り返る。
するとそこにいたのは――、
「君、相変わらず耳弱いんだね。変わってなくて安心したなぁ」
と美しい笑みを浮かべる、この部屋の借主――ジークフリート・フォン・ランデルの姿だった。