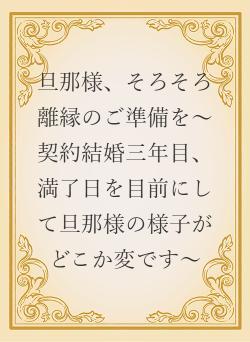(俺も彼らの意見には同感だ。しかしエリスは戻っていない。……ということはつまり、第三者が関わっている可能性が高いということ)
アレクシスは使用人らの言葉を思い出しながら、側に立つセドリックに問いかける。
「もう一度確認するが、これはシオンの字で間違いないんだな?」
「ええ、間違いありません」
「では、お前はこの事態をどう考える? これは、シオンが自らの意思で行ったことだと思うか?」
「…………」
するとセドリックは僅かばかり思案した末、「半分は」と答え、こう続けた。
「私も使用人らの言うように、シオンがこのようなやり方をするとは思えません。もし何かするならば、もっと早い時期に事を起こしていたはず。とは言え、何者かに命じられたと考えるのも少々無理がある。もし誘拐等の犯罪に巻き込まれていた場合、『数日預かる』『殿下が戻られるまで内密に』という文句にはなりませんから」
――つまり、と、セドリックは意見を纏める。
「私は、その手紙に書かれていることが全てであると考えます。シオンは、『訳あって』エリス様を帰すことができなくなった。そして『その訳』は、シオンにとって不測の事態且つ、人には知られたくない事情だったのでしょう。少なくとも、手紙に書き記すことができない程度には」
「…………」
セドリックの言葉に、アレクシスの眼光が鋭さを増す。
『不足の事態』且つ、『人には知られたくない事情』。
それはアレクシスからしてみれば、異常事態以外の何物でもなかった。
その理由が事件であれ事故であれ、決して放っておくことはできない。
――エリスの無事を、この目で確かめるまでは。
「セドリック、今すぐシオンの足取りを探れ。帝国図書館と国立公務学院に連絡を入れろ。門兵に手紙を渡したというペイジボーイも、探し出して連れてこい」
「御意。全ては殿下の御心のままに」
アレクシスが命じると、セドリックは恭しく拝命し、くるりと身を翻した。
その背中が扉の向こうに完全に消え去るのを待ち、アレクシスは、拳を強く握り締める。
「エリス……どうか、無事でいてくれ」と。
祈るような気持ちで、窓の向こうの夜月を仰ぎ見て、同じ空の下にいるはずのエリスに、想いを馳せた。