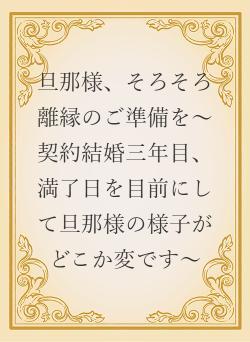リアムはエリスのすぐ前に立つと、ニコリと微笑み、脈絡もなくこう言った。
「皇女殿下はお越しになりませんよ」――と。
「……え?」
「『急用ができた』と、あなたの字で文を出しておきましたから」
「…………」
(いったい、どういうこと……?)
全く訳がわからない。なぜリアムがそんな手紙を出す必要があるのか。
エリスは酷く混乱する。
そんなエリスを前に、リアムはテーブルの上の紅茶をチラリと見やり、こう続けた。
「……良かった。その紅茶、飲んでいただけたのですね」と。
放心するエリスの反応を確かめるように、一層笑みを深める。
「そのお茶は、あなたが頼んだものではありません。私が用意させたものです」
「――!?」
「大丈夫、毒など入っておりませんから。ただ数滴、眠気を誘う薬を入れただけ」
「……!」
――そんな、まさか、どうして。
エリスは憤った。
よもや、こんな人気のある場所で薬を盛られるなどと、誰が予想しただろう。
エリスは咄嗟に椅子から立ち上がり、リアムから距離を取ろうとする。
けれど薬が回り始めていたのか、エリスはたちまち眩暈を起こし、その場にへたり込んでしまった。
「……っ」
眠い。身体に力が入らない。――声が、出ない。
(……どう、して……こんな……)
まるで天地がひっくり返ったように目が回り、意識が闇に引きずり込まれる。
目を開けていられない。眠くて、――眠くて。
エリスはもはや成すすべもなく、
「手荒なことはしませんから、ご安心を」
――というリアムの声を遠くに聞きながら、意識を手放したのだった。