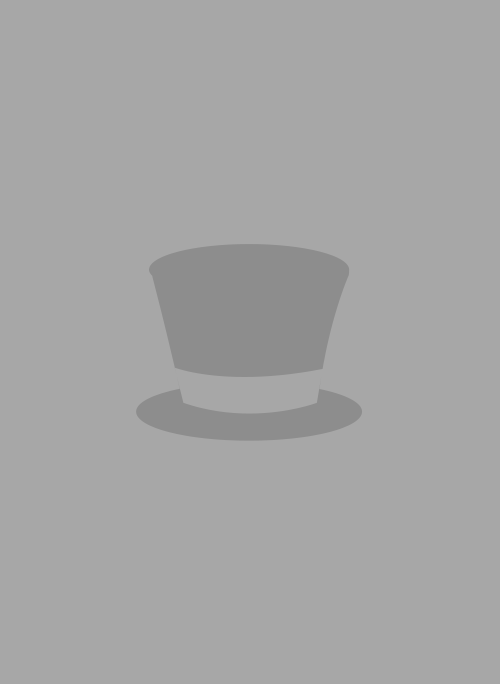1
厳めしい高いコンクリート塀、その上部に鋭利な鉄条網が張り巡らされていた。広い陰気な中庭を擁した建物は四階建てで、窓の鉄格子はかなり以前に取り払われたものの、桜島の降灰を吸った硝子窓は現在でも4分の1しか開かない。入院患者の自殺防止の為だった。
潮精神科病院は、鹿児島市の下伊敷の果てに位置していた。近隣には県立短期大学や医療専門学校があるが、此処だけは周辺と全く隔絶していて、陰湿極まりない雰囲気を醸している。
街中に在るので、所謂大型コロニーとは異なるものの、矢張り異次元の暗さが建物全体を覆っていて、陸の孤島然としている。
時刻は深夜の2時、閉鎖病棟は全て消灯され、看護師詰め所周辺だけがledを点していた。
洗面所とトイレは、人を感知した折りだけ、暗い照明を点す。
今年八十八になる老人の入院患者、山神信行は独り洗面所にて、手を洗っていた。山神は近年は加齢が著しく、歩行もままならない状態だった。老人はまた極度の不眠症でもあった。
山神はプラスチックのコップでうがいをした。
看護師詰め所では、まだ経験の浅い若い看護師、佐藤が夜間詰めていた。佐藤はパソコンに向かって、入院患者の状態の情報を打っていた。その患者はかなり重度の譫妄状態にあり、報告は容易ではなかった。佐藤看護師は作業に没頭した。
矢庭に、詰め所の硝子窓を叩く者があった。
佐藤が振り向くと、三十代の患者、横川広光だった。
「どうされました?眠れないんですか」
「そうではありません。大変なんです」
二人は刹那、意味ありげに眼と眼を合わせた。
「何事でしょう」
「山神さんが……」
「えっ」
「山神さんが、洗面所で倒れています」
「そうですか。直ぐまいります」
佐藤は詰め所を飛び出た。
人気の皆無な暗い廊下を佐藤は駆けた。
確かに、洗面所に山神がうつ伏せに倒れていた。
「山神さん、大丈夫ですか?」
看護師は山神を抱き起こした。
山神は唇から大量に出血している。意識はなかった。
佐藤は大急ぎで脈を取った。鼓動は既に失われていた。
「大変だ」
佐藤は、近くに立っていた横川に言った。
「詰め所から他の看護師を呼んでください、大至急」
「分かりました」
急いで救急車を呼ばねばならない。AEDの処置も必要かもしれなかった。
2
早朝の天文館、春まだ浅く、寒さ慣れしていない南国の住人には冴えた冷たい朝なのだった。
亀田浩志は、電車を敢えて新屋敷で降りて、少し遠方まで散歩した。運動の為だった。運動不足のせいで、最近腹に少しく脂肪が付いてきた。また動脈硬化も心配されるので、毎朝軽いウォーキングを近頃日課としていた。
天文館まで来ると、亀田は通りすがりのファミリーマートに立ち寄った。折角の運動が無駄になる、いけないと思いつつ、ハンバーガーを購入した。どうにも抗しがたい空腹を覚えていたからだ。
亀田はコンビニの外で、立ったまま、温めたハンバーガーにかじり付いた。彼は通例として、食事と言えば、ハンバーガーか牛丼かの何れかだ。彼の経済状態が常に苦しい為だった。
亀田は更に散歩を継続して、いずろの彼自身の私立探偵事務所に向かった。廃ビル寸前の旧いビル内にある事務所に、数分で着いた。
事務所に入ると、まずデスク上の書類を片付けに掛かった。本来ならば大切な個人情報の集積ながら、其処がぞんざいな探偵事務所のこと、書類整理も怠っているのだった。
亀田は雑事のbgmに、リモコンでCDを掛けた。プレイングマンティスのディファイアンスを一曲早送りして、二曲目から再生した。
始まったハードロックサウンドは恐らくは、ウクライナ戦争を歌った内容だ。ウクライナ支援を国是とする英国としては、かなり思い切った政治的反抗の歌詞だった。
亀田はどちらかと言えば、日本の大向こうとは異なり、トランプ支持者だった。停戦を望んでいるのだ。
書類の片付けは予想よりハードな仕事だった。小さな書類棚にはどうしても入り切れない、厚い束が残る。
如何に整理すべきか悩んでいる折り、机上の電話が鳴った。
亀田は急いで受話器を取った。
「はい、亀田探偵事務所」
「嗚呼、すみません。僕、松元勇樹と申します」
若い男の声だった。
「どのような御用件でしょうか」
「ええ、実はちょっと悩んでいるんです」
「と仰有いますと」
「僕、今、病院に入院しているんですが、鹿児島大学医学部の学生です」
「なる程」
「入院している病院は、ちょっと憚られるんですが、大丈夫です。学生証と成績証明書を持参します」
「どちらにご入院ですか」
「ええ、潮病院なんです」
「と仰有いますと、下伊敷のあの精神科病院ですか」
「はい、かなり不眠が続いたものですから。一ヶ月の入院予定です」
「そうですか。で、御用件は?」
「それが、正直かなり悩んでいるんです」
「どのようなお悩みでしょう」
「実は、病院内にかなり深刻で不穏な空気がありまして」
「……」
「分かります。こんなシチュエーションだから、僕が妄想を抱いていると思われるのでしょう」
「一概にそうとは申しませんが」
「有難うございます。ですから、学生証と、成績証明書をお見せ致します。僕に、事理を弁識する能力がある証明にしたいと思いますので」
「そうまで仰有るなら、お話を伺っても結構ですが」
「そうですか、安心しました」
「ただですね。学生さんですが、探偵料の方は大丈夫でしょうか」
「それは大丈夫です。医者の父が亡くなったばかりで、遺産が入りました」
「そうですか。なら結構です。外出して来られるのですね」
「はい、10時頃に伺います」
電話は切れた。
受話器を置いて、亀田は考え込んだ。精神科の患者といっても、医学生らしい。悩み事ならば、主治医に相談した方が良いのではないだろうか。
亀田に精神医学の知識はなかった。それにしても、兎も角話だけでも聞いてみて良いのではなかろうか。
午前10時5分前に、松元勇樹は事務所に現れた。医学生らしい長身の若者で、長髪に銀縁眼鏡が似合っていた。顔色が少し悪くなければ、精神科病院入院中とは到底信じられなかっただろう。
亀田はデスク対面の肘掛け椅子を勧めた。松元は幾分落ち着きなく、腰を下ろした。
「松元さん、煙草を如何ですか」
「いえ、僕は吸わないので」
「そうですか、最低の悪者扱いですが、これ程の鎮静剤は他にないと思うんですが」
「肺癌が怖いですね。指宿陽子線治療でも、肺癌の経過は決して良くない」
「既にお医者さんらしいですね。何年生ですか」
「三年です。これが学生証と成績証明書です」
亀田は、松元がデスク上に置いたそれらを確認した。彼は確かに成績優秀だった。
「で、将来は何科を志望ですか」
「普通の平凡な内科医を。外科は不得意でして」
「なる程、それでは伺いましょう。貴方の悩み事はなんですか」
松元は怯えた表情になった。
「実は、閉鎖病棟内で近く、何か大変なことが起きる予感があるのです」
「大変なこととは?」
「殺人事件です」
亀田は嘆息した。
「矢張り、信じては頂けませんか」
「それを、主治医には相談なさっていますか」
「しています」
「主治医は何方ですか」
「院長の潮晃二です」
「潮院長は何と言っています」
「妄想だろうと」
「誠に残念ながら、そうかもしれません」
「僕は、誰に頼って良いか分からないんです。警察にも相談しましたが、取り合ってくれません」
「それは仕方ありませんね」
「どうか、信じてください。病棟内には死者が多いんです」
「それは患者が高齢化しているせいではありませんか」
「認めます。先日も、山神という老人が舌を噛み切って自殺しました」
「舌を噛むと死ぬものなんですか」
「噛んだ舌が喉に詰まったらしいです」
「高齢者の自死は防げないんですかね。しかし貴方は殺人と仰有った」
松元は頷いた。
「確かに閉鎖病棟内に殺人の兆候があると、僕は予感しています。直感は科学的なものです」
「ううん、残念ながら、信じがたいです」
「其処を何とか、信じて頂きたいと思います」
亀田は煙草に火を点じた。
「殺人の兆候とは、具体的には何ですか」
「それは、申し上げ難いです。漠然としていて。唯、病棟内の空気感から、強くそれを感じるんですが」
「空気感、確証は掴んでいらっしゃらない」
「それを、貴方にお願い致したいのです。確証を掴んで頂きたいんです」
「すみません。少し考えさせてください」
亀田は煙草を吸い終わるまで熟考した。
「そうですね、規定の料金を払って頂けるなら、お引き受けしてもいいですよ」
松元の表情に明るさが兆した。
「有難うございます。何と言って良いか」
「こちらは仕事ですから、お気になさらずに。で、私は精神科病院に潜入しなくてはならないんですかね」
「宜しくお願い致したいのです」
「分かりました。酒でも呑んで、泥酔して、患者を装いましょう。任意入院なら、上手く病棟内に潜り込めると思います」
3
潮精神科病院診察室、亀田は外来患者として潮院長と対座していた。アルコールを呑んで、正体を無くそうとも考えたが、それでは口臭でばれる。しらふで何とか重病患者を装うことに決めた。
まず両目の焦点を故意に合わなくし、肩を震わせた。プロの精神科医を上手くごまかせるか余り自信はなかった。
「すみません。先生、兎に角頭痛が酷いんです」
「それから、どんな具合ですか」
潮院長の声は落ち着き払っていた。単なる入院ではなく、閉鎖病棟に入らなければならないので、ハードルは高い筈だった。
「兎に角何日も一睡も出来ません。それに恐いんです」
「何が恐いのですか」
「誰かが私を殺しに来るんです」
「何故そう思うんですか」
「そういう幻聴があります」
「なる程、お困りでしょうな」
亀田は頭を下げた。
「お願い致します。閉鎖病棟に入院させてください。恐くて溜まらないんです」
潮院長は暫し沈黙したが、口を開いた。
「現代は大量退院の時代ですから、簡単には入院出来ませんよ」
「いいえ、そこを何とかお願い致したいのです。恐くて死にそうです。いや、自殺するかもしれません、このままでは」
院長は相変わらず表情を変えず、答えた。
「仕方ありませんな。任意入院に同意なさるんですね」
「はい」
潮院長は書類を提示した。
「それでは、此方に署名と拇印をお願いします」
「有難うございます」
屈強な男性看護師が診察室に入ってきた。亀田はサインと捺印を済ませると、立ち上がった。
「亀田さんですね。私、看護師の山尾といいます。さあ、一緒に行きましょう」
「はい」
病院内の裏廊下を通って、エレベーター前まで来た。亀田は全身に緊張が走った。いよいよ正気と狂気の境界を越境するのだ。
「荷物は準備なさっていますか」
亀田は携えているボストンを示した。
「この通り、着替えとかも持ってきました。初めから入院するつもりでしたので」
「結構です」
エレベーターは不気味な音を立てて、4階に上がった。
4階に着くと、分厚い鉄の扉を開き、二人が入ると、ガタンと大きな音を立てて閉められ施錠された。亀田は深呼吸した。
看護師詰め所に入ると、手荷物を検査すると言われた。
「直ぐ済みます……なる程、着替えと洗面道具、それに小型のラジカセですか」
「はい」
「髭剃りはお持ちですか」
「入っております」
「宜しいでしょう。ボストンバッグを持って入られて結構です」
「有難うございます」
「亀田さん、貴方の病室に案内しましょう」
看護師が詰め所の内部への扉を開いた。
其処にはどんな狂騒が待ち受けているのか。亀田は覚悟した。
硬い冷たい床の廊下を看護師とともに進んだ。心に問題を抱えた患者達の群衆は、まばらに廊下を徘徊していた。大声を挙げる者、ぶつぶつ呟く者、人夫れ夫れだった。
食堂を通って、廊下の奥、401号室に案内された。亀田が見ると、偶然にも松元勇樹が同室だった。
「此処が貴方のベッドです。部屋の患者さんと仲良くしてください」
「分かりました」
四人部屋だった。松元が近寄ってきた。看護師は詰め所に戻った。
「亀田さん、凄い偶然ですね。確かにこの部屋、ベッドが一つ空いてましたが」
「松元さん、何処か二人だけで話せる場所はありませんか」
「トイレしかないですね」
「なる程」
残りの二人の同室患者が、ほぼ同時に亀田に挨拶した。
「西川竜夫といいます。宜しくお願い致します。私は言わばベテランだから、分からないことは何でも聞いてください」
西川は70歳くらいの、白髪の美しい老人だった。
「私は横川広光といいます。宜しく。私はまだ若いんですが」
「若いと言っても、君も40過ぎだろう」
西川が茶々を入れた。横川は苦笑した。
「私は亀田といいます。しがない電気工事士をしております。宜しくお願い致します」
亀田は深々頭を下げた。続いて亀田は、松元を誘った。
「松元さん、ちょっと行きましょう」
「ええ」
病棟内で唯一トイレだけが、プライバシーを保てる場所だった。亀田と松元は二人トイレに入り、内側から施錠した。
「松元さん、どうやら上手く潜り込めました」
「良かったです」
「ボストンバッグは底が二重になっていましてね、何とか探偵七つ道具も病棟に持ち込むことが出来ました」
「七つ道具と仰有ると」
「盗聴器とか、指紋検出セット」
「なる程ですね」
「あと解錠の道具も。うまくいけば、病棟内の鍵を開けて、何処へでも行けます」
「完璧ですね」
「いえ、これが仕事ですから」
「私にお手伝い出来ることはありますか」
「結構です。どうぞ、安静に療養なさってください」
「まず手始めに何を?」
「そうですね、夜の眠剤を呑む真似をして、呑まないようにします。夜は見張りにつかなければなりません」
「眠らなくて大丈夫ですか」
「昼間寝ますよ。その間、緩くでいいので見張っていてください」
「分かりました」
「昼間、ot、作業療法があるんですか」
「あります。軽スポーツ他が」
「重病患者を装って、otには出ないようにします」
「そうですね。亀田さん、同室の西川氏から当たってください。彼はこの病棟内の生き字引、長老ですから」
「了解しました」
二人はトイレを出た。
亀田は病室に戻ると、西川に探りを入れた。西川自身の何でも聞いてくれとの言葉に、甘えた形だった。温厚そうで、知性も垣間見える西川は、この未体験の世界の案内役としては適役に思われたのだ。
「西川さん、何分自分は精神科は初めてなので、分からないことだらけなんです」
「本当に何なりと聞いてください」
「甘いものはお好きですか」
「ええ、好物です」
「チョコレートを持ってきたので、差し上げます」
「有難う。此処は菓子は売店の注文制だから、充分には食べられません。有難く頂きます」
西川は板チョコにかじり付いた。
「この病院の特色は何でしょう」
「ご存知かもしれないが、鹿児島県は日本一精神科病床数が多い。その沢山ある病院の中でも、此処は一種の楽園です」
「楽園。意外な表現ですね。私は此処に堕ちたばかりで鬱になっているのかな」
「何故そう言うかというと、此処程、患者と職員が一体化している病院は、他にないからですよ」
「一体化?管理する側と、管理される側の関係とは一味違うと仰有るのですか」
「そうです。此処は医師や心理士と、患者の間でも、所謂ラポール形成以上の関係が繋げていると思いますよ」
「一体感がある。情報の非対称性ということは余り問題視されていないということでしょうか」
「そうです。この病院は極めて民主的なのです」
「それは良いですね」
「それでいて、患者は皆、潮院長を深く敬愛しています」
「結局、此処は非常に過ごし易いということなんですね」
「さようです」
亀田は首を傾げた。
「私は、外から此処の建物を見ただけて、何かしら陰気な怖い所だなという印象を持ちましたが」
「精神科ですから、それはある程度仕方ありませんな」
「エレベーターで病棟を上がってくるとき、恐くて仕方なかったんですが」
「精神科が怖いというのは、昔の話です。法律も何度か変わって、随分クリーンな空間になりました。現在では看護師は患者に敬語で接します。そんなことは昔は考えられませんでした」
「そうなんですか」
「貴方は今でも電気ショックや、ロボトミーの大昔の精神科をイメージなさっているのではありませんか」
「そうかもしれません」
「アメリカでも精神科の処遇は地獄的に最悪でしたが、北欧の思想を導入して、随分と改善されたと聞いています。何しろ、ADA法があるくらい自由なのです」
「それは日本にはない法律ですね」
「確かに無いが、時代と共に其処に近づいていると思います。実際のところ、そんな時代に逆行する、津久井とかの悲惨な事件は起きている訳ですが、時代の流れは漸次解放に向かっています。例えば、障害者に対する合理的配慮が事業者に義務化されたりしています。確実に解放に向かっているのです」
4
深夜の閉鎖病棟、薄暗い洗面所にて、水道の流れる音が響いている。
横川広光はプラスチックのコップを持ったまま、暫し静止した。
数分後のこと。横川はゆっくりと床に倒れ臥した。
倒れた横川を発見したのは、病棟内に眼を光らせていた亀田だった。亀田は、横川の唇付近が真紅に染まっているのを見て、刹那、詰め所まで駆け出そうとしたが、洗面所にコールボタンがあることに気付いた。
亀田は気を取り直して、横川に近づいた。脈を取った。鼓動はなかった。洗面台にコップがあるのに気付いて、コップを取り、丁寧にハンカチでくるんだ。それからコールボタンを押した。
夜勤の山田看護師が、洗面所に駆けてきた。
「横川さん、横川さん、大丈夫ですか」
看護師は直ぐさま脈を取り、首を振った。
「既に事切れていますか」
亀田は尋ねた。
山田看護師はそれには答えず、立ち上がった。
「亀田さん、自分の病室に戻ってください。これは命令です。当直の先生を呼ばねばなりません。何よりこの現場は保存しなければならない」
「亡くなられているんですね。横川さんは。殺人ですか」
「莫迦な。舌を噛んでいる。明らかに自殺です。さあ、亀田さん、早く病室に戻って」
山田看護師は、亀田を強引に押し戻した。
自室に亀田が戻ると、西川も松元も起き出していた。
「ばたばた廊下を走る音が聞こえましたが、何があったんですか、亀田さん」
西川が尋ねた。
「どうやら横川さんが亡くなられたようです」
「亡くなった。まさか、自殺ですか」
「そうらしいですね」
「殺人ではないんですか?」
松元は恐怖にかられた表情で訊いた。
「殺人、莫迦な、有り得ない」西川は吐き捨てた。
「数日前にも誰か自殺したんですよね」亀田が言った。
「そうです。山神さんが自殺なさった」西川が答えた。
翌日、警察が病棟内に来た。洗面所は暫く立ち入り禁止になった。
患者達は不思議なくらい、横川の死に無関心だった。亀田は首を傾げた。
401号にて、亀田は西川に尋ねた。
「西川さん、自殺者が続いていますね。これでも此処が楽園と言えますか」
「地獄なのは外の社会の方です。私は知っているが、横川はギャンブル依存症だった。到底払いきれない借金を抱えていたんです」
「借金苦で自殺したと仰有るんですか」
「そうに違いない」
「舌を噛み切っての自殺が二度連続した訳ですが」
「それは偶然でしょう」
「そうですかね。とまれ、有難うございました」
亀田は、松元の方に向き直った。
「松元さん、ちょっと行きましょう」
「ええ」
二人はトイレに逃げ込んだ。
「松元さん、横川氏には親しい友人はいましたか」
「います。405号室の浦島という人です」
「どの程度の関係でしょう」
「さあ、昔からの知り合いらしいですが」
「分かりました。その人に話を聞いてみましょう。それにしても松元さん」
「ええ」
「貴方の直感は当たりましたね」
「えっ、これは殺人なんですか」
「同じ手段の自殺が二度続くとは考え難い」
「矢張りそうでしたか」
「私も無駄足ではなかった訳です」
「良かったです」
「此処は完全な閉鎖病棟。ですから必ず犯人はこの中にいる筈なんです」
「誰でしょうか、一体」
亀田はトイレを出ると、405号室に向かった。
浦島は40格好、横川と同年齢くらいの顔色の悪い男だった。
「貴方が浦島さんと、伺って来たんですが」
「ええ、浦島ですが、貴方は?」
「横川氏と同室の亀田といいます」
浦島は明らかに何事かに怯えていた。それを悟られまいと努力するが故に却って恐怖が露わになる感じだった。
「私に何の用事ですか。話せることは何もありませんが」
「ということは何かしらご存知なんですね」
「何のお話でしょう。私は何も知らない」
「横川さんについて知りたいんです。どんなことでも良いので」
「煩いな。知らないと言っている」
「浦島さん、お願いします。お友達の横川さんの為なんです」
「何ですって。貴方は一体何者なんですか」
「私のことは何でもいい。恐らくは貴方達の味方です」
「知らない。帰ってください。他人の病室に入ってこないで」
「分かりました。浦島さん、気が変わられたら、いつでも401号室にいらしてください。それでは」
亀田は一礼して、病室を出た。
それから作業療法が始まった。
亀田は自室で、仮眠を取ることにした。同室の西川と松元はotホールに行った。
亀田は何時か眠りに落ちていた。
夢を見た。幻覚のような錯雑した夢だった。精神薬は呑むふりをして、吐き出していたから、薬のせいではなかった。経験のない特殊な状況が見せた夢なのだった。
誰かが亀田を揺り起こしていた。
眼を覚ますと、それは浦島だった。
「嗚呼、浦島さん」
亀田は身体をベッドから起こした。
「話す気になってくれましたか」
浦島は首を振った。
「私は何も知らない。しかし貴方は誰なんですか」
「しがない電気工事士ですよ。分かってくださいますか」
「全く分かりません。しかしこれだけは言っておきます」
「何でしょう?」
浦島はまだ躊躇していた。
「浦島さん、お願い致します」
「横川さんは、詰め所からスマホを取り上げられていました」
「病棟内で、スマホが使えるのですか」
「共有ルームで使うことが出来ます。でも横川さんは看護師に奪われていたんです」
「何故ですか」
「さあ、横川さんの状態が悪かったのか」
「それで、通信の制限を受けた、ということですか」
「分かりません」
「いえ、分かりました。有難うございます。他には?」
「横川さんは、見てはならないものを見てしまった、と言っていました」
「見てはならないものを見た、なる程そうでしたか」
「あと一つ、横川さんは入院したての新参の患者でした。他には私は何も知らない」
浦島は病室を出て行こうとした。
「浦島さん、あと一つだけ教えてください」
「何でしょう」
「プラスチックのコップは患者自身がコップ消毒するのですよね」
「そうです、コップは完全な自己管理です」
「私は新入りで、まだ消毒しなくて良いと言われましたが、コップ消毒は昨晩あったのですか」
浦島は頷いた。
「分かりました。大変有難うございました」
浦島は素っ気なく頭を下げると、401号室を出て行った。
5
亀田にとって意外だったのは、この閉鎖空間のもたらす精神への影響だった。常々冷静で、滅多に惑乱しない筈の彼が、悪夢にうなされるようになった。閉鎖空間が人に病をもたらす、施設病というものが、実在することに酷く混乱させられた。
今回は仕事自体は余りにも単純だった。しかしこの環境が生み出す悪夢めく狂気は確実に亀田をも蝕んだ。
実は例えようもなく、困難を伴う仕事となった。正気と狂気の狭間でもがく彼は、恐らくはシステムに内包されたスティグマに抗い得なかったのだろう。冷厳な、恐ろしい調査となった。
亀田は、潮院長の診察に呼ばれた。
亀田は既に、全ての準備を整えていた。しかし最後の一歩を踏み出すのは、実際のところ容易ではなかった。
診察室にて、潮院長と対座した亀田は、中々口を開き兼ねていた。
「どうですか、亀田さん、体調の方は」
院長の声は、相変わらず落ち着き払っている。
「院長先生、少しお話させて頂いて良いですか」
「嗚呼、どうぞ」
「調べてみたんですが、最初の自殺者、山神さんは実の妹さんを亡くされたばかりでしたね」
「ええ、そうでした」
「山神さんには他には血縁者はいない。生活保護を受給中の山神さんは天涯孤独になられた」
「それが何か」
亀田は服のポケットからicレコーダーを取り出した。
「誠に失礼ながら、私は、看護師詰め所に盗聴器を仕掛けました。最初の録音は、山尾看護師と山田看護師の会話のようです。どうぞ、お聴きください」
亀田はレコーダーのスイッチを押した。
〈……悲しいものだな〉
〈何がだ?〉
〈此処の患者は、血縁がいなくなって、天涯孤独になると自動的に舌を噛み切る〉
〈違うな、俺が夜中に、メスで患者の舌を切るんだ〉
〈まじか?〉
〈まじだよ、勿論。分かっているだろう〉
〈嗚呼、全く、やりきれないな〉
亀田はレコーダーのスイッチを一旦切った。
「院長先生、如何ですか」
潮院長は沈黙したままだった。
「院長、もう一つ、これをご覧ください」
亀田はハンカチでくるんだコップを取り出した。
「これは、第二の自殺者、横川さんのコップです。実は遺体の第一発見者の私が、こっそり遺体の傍から取ったものです。コップの指紋を検出しました。調べてみると、横川さん以外に、もう一人、別人の指紋が付着していました。コップは完全な自己管理で、あの夜にコップ消毒されたばかりなのにです。何者かが、横川さんの死の直前に、このコップに触れているんです」
潮院長は表情を硬直させた。
「あの夜に当直だった、山田看護師に、故意に私のコップを触らせました。単なる勘でしたが、驚いたことに、横川さんのコップに触れたのは、その指紋の一致から、山田看護師であることが分かりました。先程の盗聴器録音とも合致する訳です」
院長は亀田を睨めつけた。
「すると、横川さんを殺害したのは、山田看護師だったのか。私はそれだけではないと思っています。次の盗聴器録音をお聴きください。次には、院長先生、貴方の声が入っています」
〈……浦島は大丈夫か?〉
〈院長先生、大丈夫だとは思いますが〉
〈横川は奴の親友だったからな〉
〈ええ〉
〈浦島が何か口を割るようなら、浦島も処分しろ〉
亀田は、院長を見返した。
「この事件の犯人は、閉鎖空間だからこの中にいる筈と考えていましたが、犯人は実際、松元さんと私を除く、職員、患者、全員が犯人の、組織的な犯罪だった訳です。この病院の職員と患者は一体化している。浦島さんも明らかに真相を知っていましたよ。……横川氏は、山神さんの殺害を目撃したから殺されたのですね。横川氏のスマホは職員に取り上げられていた。警察に通報されないためですね」
「宜しいかね……」院長は漸く口を開いた。「全ては国の福祉行政のためなんだ。毎年生活保護費がかさんで財政はパンクする。山神のような孤独者は死んで当たり前なのだ。88歳でもう充分生きた。冷たいようだが、これが現実だ。医療パターナリズム、父権主義とは、本来こういうものなんだよ」
亀田は首を振った。
診察室のドアが開き、山尾と山田、両看護師が入ってきた。
亀田はポケットから小型ナイフを取り出した。
「精神科病棟内でそんなものを振り回したら、どうなるか分かっているかね」
「私も、自分の身は守らなくてはなりません」
亀田は片方の手で、スマホを取り出した。
「ああ、叔父さん。院長、叔父さんというのは、県警の警部補です……叔父さん、亀田です。潮病院で殺人事件が起きました。ええ、既に証拠は掴んでいます。至急来てください。それから、県に通報をお願い致します。潮病院で入院患者の虐待があります……」
意外にも、院長は平然としていた。
「無駄だ、亀田君、ナイフを捨てたまえ。此処は精神病院だ、君は全く分かっていない」
「何をです」
「君の言葉は全て妄想として、握り潰せるのだ。君は保護室に入らねばならない」
「私は任意入院だ、私の意思で退院出来る」
「違うのだ。例え警察が来ても、君は重篤患者として保護室監禁だ」
「直ぐに警察が来るんですよ」
「無駄だ。君の証拠とやらは我々が握り潰す」
亀田は立ち上がったが、診察室の端に追い詰められた。
「院長、貴方こそ無駄だ。警察は兎も角、県に虐待を通報した。精神保健福祉法の改正があった。虐待のあったこの病院は、どの道処分される。二度の不審死を警察が再捜査する」
看護師達が進み出てきた。
「私は私立探偵だ。格闘技の鍛錬にも日々精進している。舐めてもらっては困る。二人くらい楽に倒せる。院長、まだ患者の方が新時代を理解している。虐待の通報は妄想として、握り潰せない。時間の問題だ。従兄弟の警部補が直ぐに此処に来る」
厳めしい高いコンクリート塀、その上部に鋭利な鉄条網が張り巡らされていた。広い陰気な中庭を擁した建物は四階建てで、窓の鉄格子はかなり以前に取り払われたものの、桜島の降灰を吸った硝子窓は現在でも4分の1しか開かない。入院患者の自殺防止の為だった。
潮精神科病院は、鹿児島市の下伊敷の果てに位置していた。近隣には県立短期大学や医療専門学校があるが、此処だけは周辺と全く隔絶していて、陰湿極まりない雰囲気を醸している。
街中に在るので、所謂大型コロニーとは異なるものの、矢張り異次元の暗さが建物全体を覆っていて、陸の孤島然としている。
時刻は深夜の2時、閉鎖病棟は全て消灯され、看護師詰め所周辺だけがledを点していた。
洗面所とトイレは、人を感知した折りだけ、暗い照明を点す。
今年八十八になる老人の入院患者、山神信行は独り洗面所にて、手を洗っていた。山神は近年は加齢が著しく、歩行もままならない状態だった。老人はまた極度の不眠症でもあった。
山神はプラスチックのコップでうがいをした。
看護師詰め所では、まだ経験の浅い若い看護師、佐藤が夜間詰めていた。佐藤はパソコンに向かって、入院患者の状態の情報を打っていた。その患者はかなり重度の譫妄状態にあり、報告は容易ではなかった。佐藤看護師は作業に没頭した。
矢庭に、詰め所の硝子窓を叩く者があった。
佐藤が振り向くと、三十代の患者、横川広光だった。
「どうされました?眠れないんですか」
「そうではありません。大変なんです」
二人は刹那、意味ありげに眼と眼を合わせた。
「何事でしょう」
「山神さんが……」
「えっ」
「山神さんが、洗面所で倒れています」
「そうですか。直ぐまいります」
佐藤は詰め所を飛び出た。
人気の皆無な暗い廊下を佐藤は駆けた。
確かに、洗面所に山神がうつ伏せに倒れていた。
「山神さん、大丈夫ですか?」
看護師は山神を抱き起こした。
山神は唇から大量に出血している。意識はなかった。
佐藤は大急ぎで脈を取った。鼓動は既に失われていた。
「大変だ」
佐藤は、近くに立っていた横川に言った。
「詰め所から他の看護師を呼んでください、大至急」
「分かりました」
急いで救急車を呼ばねばならない。AEDの処置も必要かもしれなかった。
2
早朝の天文館、春まだ浅く、寒さ慣れしていない南国の住人には冴えた冷たい朝なのだった。
亀田浩志は、電車を敢えて新屋敷で降りて、少し遠方まで散歩した。運動の為だった。運動不足のせいで、最近腹に少しく脂肪が付いてきた。また動脈硬化も心配されるので、毎朝軽いウォーキングを近頃日課としていた。
天文館まで来ると、亀田は通りすがりのファミリーマートに立ち寄った。折角の運動が無駄になる、いけないと思いつつ、ハンバーガーを購入した。どうにも抗しがたい空腹を覚えていたからだ。
亀田はコンビニの外で、立ったまま、温めたハンバーガーにかじり付いた。彼は通例として、食事と言えば、ハンバーガーか牛丼かの何れかだ。彼の経済状態が常に苦しい為だった。
亀田は更に散歩を継続して、いずろの彼自身の私立探偵事務所に向かった。廃ビル寸前の旧いビル内にある事務所に、数分で着いた。
事務所に入ると、まずデスク上の書類を片付けに掛かった。本来ならば大切な個人情報の集積ながら、其処がぞんざいな探偵事務所のこと、書類整理も怠っているのだった。
亀田は雑事のbgmに、リモコンでCDを掛けた。プレイングマンティスのディファイアンスを一曲早送りして、二曲目から再生した。
始まったハードロックサウンドは恐らくは、ウクライナ戦争を歌った内容だ。ウクライナ支援を国是とする英国としては、かなり思い切った政治的反抗の歌詞だった。
亀田はどちらかと言えば、日本の大向こうとは異なり、トランプ支持者だった。停戦を望んでいるのだ。
書類の片付けは予想よりハードな仕事だった。小さな書類棚にはどうしても入り切れない、厚い束が残る。
如何に整理すべきか悩んでいる折り、机上の電話が鳴った。
亀田は急いで受話器を取った。
「はい、亀田探偵事務所」
「嗚呼、すみません。僕、松元勇樹と申します」
若い男の声だった。
「どのような御用件でしょうか」
「ええ、実はちょっと悩んでいるんです」
「と仰有いますと」
「僕、今、病院に入院しているんですが、鹿児島大学医学部の学生です」
「なる程」
「入院している病院は、ちょっと憚られるんですが、大丈夫です。学生証と成績証明書を持参します」
「どちらにご入院ですか」
「ええ、潮病院なんです」
「と仰有いますと、下伊敷のあの精神科病院ですか」
「はい、かなり不眠が続いたものですから。一ヶ月の入院予定です」
「そうですか。で、御用件は?」
「それが、正直かなり悩んでいるんです」
「どのようなお悩みでしょう」
「実は、病院内にかなり深刻で不穏な空気がありまして」
「……」
「分かります。こんなシチュエーションだから、僕が妄想を抱いていると思われるのでしょう」
「一概にそうとは申しませんが」
「有難うございます。ですから、学生証と、成績証明書をお見せ致します。僕に、事理を弁識する能力がある証明にしたいと思いますので」
「そうまで仰有るなら、お話を伺っても結構ですが」
「そうですか、安心しました」
「ただですね。学生さんですが、探偵料の方は大丈夫でしょうか」
「それは大丈夫です。医者の父が亡くなったばかりで、遺産が入りました」
「そうですか。なら結構です。外出して来られるのですね」
「はい、10時頃に伺います」
電話は切れた。
受話器を置いて、亀田は考え込んだ。精神科の患者といっても、医学生らしい。悩み事ならば、主治医に相談した方が良いのではないだろうか。
亀田に精神医学の知識はなかった。それにしても、兎も角話だけでも聞いてみて良いのではなかろうか。
午前10時5分前に、松元勇樹は事務所に現れた。医学生らしい長身の若者で、長髪に銀縁眼鏡が似合っていた。顔色が少し悪くなければ、精神科病院入院中とは到底信じられなかっただろう。
亀田はデスク対面の肘掛け椅子を勧めた。松元は幾分落ち着きなく、腰を下ろした。
「松元さん、煙草を如何ですか」
「いえ、僕は吸わないので」
「そうですか、最低の悪者扱いですが、これ程の鎮静剤は他にないと思うんですが」
「肺癌が怖いですね。指宿陽子線治療でも、肺癌の経過は決して良くない」
「既にお医者さんらしいですね。何年生ですか」
「三年です。これが学生証と成績証明書です」
亀田は、松元がデスク上に置いたそれらを確認した。彼は確かに成績優秀だった。
「で、将来は何科を志望ですか」
「普通の平凡な内科医を。外科は不得意でして」
「なる程、それでは伺いましょう。貴方の悩み事はなんですか」
松元は怯えた表情になった。
「実は、閉鎖病棟内で近く、何か大変なことが起きる予感があるのです」
「大変なこととは?」
「殺人事件です」
亀田は嘆息した。
「矢張り、信じては頂けませんか」
「それを、主治医には相談なさっていますか」
「しています」
「主治医は何方ですか」
「院長の潮晃二です」
「潮院長は何と言っています」
「妄想だろうと」
「誠に残念ながら、そうかもしれません」
「僕は、誰に頼って良いか分からないんです。警察にも相談しましたが、取り合ってくれません」
「それは仕方ありませんね」
「どうか、信じてください。病棟内には死者が多いんです」
「それは患者が高齢化しているせいではありませんか」
「認めます。先日も、山神という老人が舌を噛み切って自殺しました」
「舌を噛むと死ぬものなんですか」
「噛んだ舌が喉に詰まったらしいです」
「高齢者の自死は防げないんですかね。しかし貴方は殺人と仰有った」
松元は頷いた。
「確かに閉鎖病棟内に殺人の兆候があると、僕は予感しています。直感は科学的なものです」
「ううん、残念ながら、信じがたいです」
「其処を何とか、信じて頂きたいと思います」
亀田は煙草に火を点じた。
「殺人の兆候とは、具体的には何ですか」
「それは、申し上げ難いです。漠然としていて。唯、病棟内の空気感から、強くそれを感じるんですが」
「空気感、確証は掴んでいらっしゃらない」
「それを、貴方にお願い致したいのです。確証を掴んで頂きたいんです」
「すみません。少し考えさせてください」
亀田は煙草を吸い終わるまで熟考した。
「そうですね、規定の料金を払って頂けるなら、お引き受けしてもいいですよ」
松元の表情に明るさが兆した。
「有難うございます。何と言って良いか」
「こちらは仕事ですから、お気になさらずに。で、私は精神科病院に潜入しなくてはならないんですかね」
「宜しくお願い致したいのです」
「分かりました。酒でも呑んで、泥酔して、患者を装いましょう。任意入院なら、上手く病棟内に潜り込めると思います」
3
潮精神科病院診察室、亀田は外来患者として潮院長と対座していた。アルコールを呑んで、正体を無くそうとも考えたが、それでは口臭でばれる。しらふで何とか重病患者を装うことに決めた。
まず両目の焦点を故意に合わなくし、肩を震わせた。プロの精神科医を上手くごまかせるか余り自信はなかった。
「すみません。先生、兎に角頭痛が酷いんです」
「それから、どんな具合ですか」
潮院長の声は落ち着き払っていた。単なる入院ではなく、閉鎖病棟に入らなければならないので、ハードルは高い筈だった。
「兎に角何日も一睡も出来ません。それに恐いんです」
「何が恐いのですか」
「誰かが私を殺しに来るんです」
「何故そう思うんですか」
「そういう幻聴があります」
「なる程、お困りでしょうな」
亀田は頭を下げた。
「お願い致します。閉鎖病棟に入院させてください。恐くて溜まらないんです」
潮院長は暫し沈黙したが、口を開いた。
「現代は大量退院の時代ですから、簡単には入院出来ませんよ」
「いいえ、そこを何とかお願い致したいのです。恐くて死にそうです。いや、自殺するかもしれません、このままでは」
院長は相変わらず表情を変えず、答えた。
「仕方ありませんな。任意入院に同意なさるんですね」
「はい」
潮院長は書類を提示した。
「それでは、此方に署名と拇印をお願いします」
「有難うございます」
屈強な男性看護師が診察室に入ってきた。亀田はサインと捺印を済ませると、立ち上がった。
「亀田さんですね。私、看護師の山尾といいます。さあ、一緒に行きましょう」
「はい」
病院内の裏廊下を通って、エレベーター前まで来た。亀田は全身に緊張が走った。いよいよ正気と狂気の境界を越境するのだ。
「荷物は準備なさっていますか」
亀田は携えているボストンを示した。
「この通り、着替えとかも持ってきました。初めから入院するつもりでしたので」
「結構です」
エレベーターは不気味な音を立てて、4階に上がった。
4階に着くと、分厚い鉄の扉を開き、二人が入ると、ガタンと大きな音を立てて閉められ施錠された。亀田は深呼吸した。
看護師詰め所に入ると、手荷物を検査すると言われた。
「直ぐ済みます……なる程、着替えと洗面道具、それに小型のラジカセですか」
「はい」
「髭剃りはお持ちですか」
「入っております」
「宜しいでしょう。ボストンバッグを持って入られて結構です」
「有難うございます」
「亀田さん、貴方の病室に案内しましょう」
看護師が詰め所の内部への扉を開いた。
其処にはどんな狂騒が待ち受けているのか。亀田は覚悟した。
硬い冷たい床の廊下を看護師とともに進んだ。心に問題を抱えた患者達の群衆は、まばらに廊下を徘徊していた。大声を挙げる者、ぶつぶつ呟く者、人夫れ夫れだった。
食堂を通って、廊下の奥、401号室に案内された。亀田が見ると、偶然にも松元勇樹が同室だった。
「此処が貴方のベッドです。部屋の患者さんと仲良くしてください」
「分かりました」
四人部屋だった。松元が近寄ってきた。看護師は詰め所に戻った。
「亀田さん、凄い偶然ですね。確かにこの部屋、ベッドが一つ空いてましたが」
「松元さん、何処か二人だけで話せる場所はありませんか」
「トイレしかないですね」
「なる程」
残りの二人の同室患者が、ほぼ同時に亀田に挨拶した。
「西川竜夫といいます。宜しくお願い致します。私は言わばベテランだから、分からないことは何でも聞いてください」
西川は70歳くらいの、白髪の美しい老人だった。
「私は横川広光といいます。宜しく。私はまだ若いんですが」
「若いと言っても、君も40過ぎだろう」
西川が茶々を入れた。横川は苦笑した。
「私は亀田といいます。しがない電気工事士をしております。宜しくお願い致します」
亀田は深々頭を下げた。続いて亀田は、松元を誘った。
「松元さん、ちょっと行きましょう」
「ええ」
病棟内で唯一トイレだけが、プライバシーを保てる場所だった。亀田と松元は二人トイレに入り、内側から施錠した。
「松元さん、どうやら上手く潜り込めました」
「良かったです」
「ボストンバッグは底が二重になっていましてね、何とか探偵七つ道具も病棟に持ち込むことが出来ました」
「七つ道具と仰有ると」
「盗聴器とか、指紋検出セット」
「なる程ですね」
「あと解錠の道具も。うまくいけば、病棟内の鍵を開けて、何処へでも行けます」
「完璧ですね」
「いえ、これが仕事ですから」
「私にお手伝い出来ることはありますか」
「結構です。どうぞ、安静に療養なさってください」
「まず手始めに何を?」
「そうですね、夜の眠剤を呑む真似をして、呑まないようにします。夜は見張りにつかなければなりません」
「眠らなくて大丈夫ですか」
「昼間寝ますよ。その間、緩くでいいので見張っていてください」
「分かりました」
「昼間、ot、作業療法があるんですか」
「あります。軽スポーツ他が」
「重病患者を装って、otには出ないようにします」
「そうですね。亀田さん、同室の西川氏から当たってください。彼はこの病棟内の生き字引、長老ですから」
「了解しました」
二人はトイレを出た。
亀田は病室に戻ると、西川に探りを入れた。西川自身の何でも聞いてくれとの言葉に、甘えた形だった。温厚そうで、知性も垣間見える西川は、この未体験の世界の案内役としては適役に思われたのだ。
「西川さん、何分自分は精神科は初めてなので、分からないことだらけなんです」
「本当に何なりと聞いてください」
「甘いものはお好きですか」
「ええ、好物です」
「チョコレートを持ってきたので、差し上げます」
「有難う。此処は菓子は売店の注文制だから、充分には食べられません。有難く頂きます」
西川は板チョコにかじり付いた。
「この病院の特色は何でしょう」
「ご存知かもしれないが、鹿児島県は日本一精神科病床数が多い。その沢山ある病院の中でも、此処は一種の楽園です」
「楽園。意外な表現ですね。私は此処に堕ちたばかりで鬱になっているのかな」
「何故そう言うかというと、此処程、患者と職員が一体化している病院は、他にないからですよ」
「一体化?管理する側と、管理される側の関係とは一味違うと仰有るのですか」
「そうです。此処は医師や心理士と、患者の間でも、所謂ラポール形成以上の関係が繋げていると思いますよ」
「一体感がある。情報の非対称性ということは余り問題視されていないということでしょうか」
「そうです。この病院は極めて民主的なのです」
「それは良いですね」
「それでいて、患者は皆、潮院長を深く敬愛しています」
「結局、此処は非常に過ごし易いということなんですね」
「さようです」
亀田は首を傾げた。
「私は、外から此処の建物を見ただけて、何かしら陰気な怖い所だなという印象を持ちましたが」
「精神科ですから、それはある程度仕方ありませんな」
「エレベーターで病棟を上がってくるとき、恐くて仕方なかったんですが」
「精神科が怖いというのは、昔の話です。法律も何度か変わって、随分クリーンな空間になりました。現在では看護師は患者に敬語で接します。そんなことは昔は考えられませんでした」
「そうなんですか」
「貴方は今でも電気ショックや、ロボトミーの大昔の精神科をイメージなさっているのではありませんか」
「そうかもしれません」
「アメリカでも精神科の処遇は地獄的に最悪でしたが、北欧の思想を導入して、随分と改善されたと聞いています。何しろ、ADA法があるくらい自由なのです」
「それは日本にはない法律ですね」
「確かに無いが、時代と共に其処に近づいていると思います。実際のところ、そんな時代に逆行する、津久井とかの悲惨な事件は起きている訳ですが、時代の流れは漸次解放に向かっています。例えば、障害者に対する合理的配慮が事業者に義務化されたりしています。確実に解放に向かっているのです」
4
深夜の閉鎖病棟、薄暗い洗面所にて、水道の流れる音が響いている。
横川広光はプラスチックのコップを持ったまま、暫し静止した。
数分後のこと。横川はゆっくりと床に倒れ臥した。
倒れた横川を発見したのは、病棟内に眼を光らせていた亀田だった。亀田は、横川の唇付近が真紅に染まっているのを見て、刹那、詰め所まで駆け出そうとしたが、洗面所にコールボタンがあることに気付いた。
亀田は気を取り直して、横川に近づいた。脈を取った。鼓動はなかった。洗面台にコップがあるのに気付いて、コップを取り、丁寧にハンカチでくるんだ。それからコールボタンを押した。
夜勤の山田看護師が、洗面所に駆けてきた。
「横川さん、横川さん、大丈夫ですか」
看護師は直ぐさま脈を取り、首を振った。
「既に事切れていますか」
亀田は尋ねた。
山田看護師はそれには答えず、立ち上がった。
「亀田さん、自分の病室に戻ってください。これは命令です。当直の先生を呼ばねばなりません。何よりこの現場は保存しなければならない」
「亡くなられているんですね。横川さんは。殺人ですか」
「莫迦な。舌を噛んでいる。明らかに自殺です。さあ、亀田さん、早く病室に戻って」
山田看護師は、亀田を強引に押し戻した。
自室に亀田が戻ると、西川も松元も起き出していた。
「ばたばた廊下を走る音が聞こえましたが、何があったんですか、亀田さん」
西川が尋ねた。
「どうやら横川さんが亡くなられたようです」
「亡くなった。まさか、自殺ですか」
「そうらしいですね」
「殺人ではないんですか?」
松元は恐怖にかられた表情で訊いた。
「殺人、莫迦な、有り得ない」西川は吐き捨てた。
「数日前にも誰か自殺したんですよね」亀田が言った。
「そうです。山神さんが自殺なさった」西川が答えた。
翌日、警察が病棟内に来た。洗面所は暫く立ち入り禁止になった。
患者達は不思議なくらい、横川の死に無関心だった。亀田は首を傾げた。
401号にて、亀田は西川に尋ねた。
「西川さん、自殺者が続いていますね。これでも此処が楽園と言えますか」
「地獄なのは外の社会の方です。私は知っているが、横川はギャンブル依存症だった。到底払いきれない借金を抱えていたんです」
「借金苦で自殺したと仰有るんですか」
「そうに違いない」
「舌を噛み切っての自殺が二度連続した訳ですが」
「それは偶然でしょう」
「そうですかね。とまれ、有難うございました」
亀田は、松元の方に向き直った。
「松元さん、ちょっと行きましょう」
「ええ」
二人はトイレに逃げ込んだ。
「松元さん、横川氏には親しい友人はいましたか」
「います。405号室の浦島という人です」
「どの程度の関係でしょう」
「さあ、昔からの知り合いらしいですが」
「分かりました。その人に話を聞いてみましょう。それにしても松元さん」
「ええ」
「貴方の直感は当たりましたね」
「えっ、これは殺人なんですか」
「同じ手段の自殺が二度続くとは考え難い」
「矢張りそうでしたか」
「私も無駄足ではなかった訳です」
「良かったです」
「此処は完全な閉鎖病棟。ですから必ず犯人はこの中にいる筈なんです」
「誰でしょうか、一体」
亀田はトイレを出ると、405号室に向かった。
浦島は40格好、横川と同年齢くらいの顔色の悪い男だった。
「貴方が浦島さんと、伺って来たんですが」
「ええ、浦島ですが、貴方は?」
「横川氏と同室の亀田といいます」
浦島は明らかに何事かに怯えていた。それを悟られまいと努力するが故に却って恐怖が露わになる感じだった。
「私に何の用事ですか。話せることは何もありませんが」
「ということは何かしらご存知なんですね」
「何のお話でしょう。私は何も知らない」
「横川さんについて知りたいんです。どんなことでも良いので」
「煩いな。知らないと言っている」
「浦島さん、お願いします。お友達の横川さんの為なんです」
「何ですって。貴方は一体何者なんですか」
「私のことは何でもいい。恐らくは貴方達の味方です」
「知らない。帰ってください。他人の病室に入ってこないで」
「分かりました。浦島さん、気が変わられたら、いつでも401号室にいらしてください。それでは」
亀田は一礼して、病室を出た。
それから作業療法が始まった。
亀田は自室で、仮眠を取ることにした。同室の西川と松元はotホールに行った。
亀田は何時か眠りに落ちていた。
夢を見た。幻覚のような錯雑した夢だった。精神薬は呑むふりをして、吐き出していたから、薬のせいではなかった。経験のない特殊な状況が見せた夢なのだった。
誰かが亀田を揺り起こしていた。
眼を覚ますと、それは浦島だった。
「嗚呼、浦島さん」
亀田は身体をベッドから起こした。
「話す気になってくれましたか」
浦島は首を振った。
「私は何も知らない。しかし貴方は誰なんですか」
「しがない電気工事士ですよ。分かってくださいますか」
「全く分かりません。しかしこれだけは言っておきます」
「何でしょう?」
浦島はまだ躊躇していた。
「浦島さん、お願い致します」
「横川さんは、詰め所からスマホを取り上げられていました」
「病棟内で、スマホが使えるのですか」
「共有ルームで使うことが出来ます。でも横川さんは看護師に奪われていたんです」
「何故ですか」
「さあ、横川さんの状態が悪かったのか」
「それで、通信の制限を受けた、ということですか」
「分かりません」
「いえ、分かりました。有難うございます。他には?」
「横川さんは、見てはならないものを見てしまった、と言っていました」
「見てはならないものを見た、なる程そうでしたか」
「あと一つ、横川さんは入院したての新参の患者でした。他には私は何も知らない」
浦島は病室を出て行こうとした。
「浦島さん、あと一つだけ教えてください」
「何でしょう」
「プラスチックのコップは患者自身がコップ消毒するのですよね」
「そうです、コップは完全な自己管理です」
「私は新入りで、まだ消毒しなくて良いと言われましたが、コップ消毒は昨晩あったのですか」
浦島は頷いた。
「分かりました。大変有難うございました」
浦島は素っ気なく頭を下げると、401号室を出て行った。
5
亀田にとって意外だったのは、この閉鎖空間のもたらす精神への影響だった。常々冷静で、滅多に惑乱しない筈の彼が、悪夢にうなされるようになった。閉鎖空間が人に病をもたらす、施設病というものが、実在することに酷く混乱させられた。
今回は仕事自体は余りにも単純だった。しかしこの環境が生み出す悪夢めく狂気は確実に亀田をも蝕んだ。
実は例えようもなく、困難を伴う仕事となった。正気と狂気の狭間でもがく彼は、恐らくはシステムに内包されたスティグマに抗い得なかったのだろう。冷厳な、恐ろしい調査となった。
亀田は、潮院長の診察に呼ばれた。
亀田は既に、全ての準備を整えていた。しかし最後の一歩を踏み出すのは、実際のところ容易ではなかった。
診察室にて、潮院長と対座した亀田は、中々口を開き兼ねていた。
「どうですか、亀田さん、体調の方は」
院長の声は、相変わらず落ち着き払っている。
「院長先生、少しお話させて頂いて良いですか」
「嗚呼、どうぞ」
「調べてみたんですが、最初の自殺者、山神さんは実の妹さんを亡くされたばかりでしたね」
「ええ、そうでした」
「山神さんには他には血縁者はいない。生活保護を受給中の山神さんは天涯孤独になられた」
「それが何か」
亀田は服のポケットからicレコーダーを取り出した。
「誠に失礼ながら、私は、看護師詰め所に盗聴器を仕掛けました。最初の録音は、山尾看護師と山田看護師の会話のようです。どうぞ、お聴きください」
亀田はレコーダーのスイッチを押した。
〈……悲しいものだな〉
〈何がだ?〉
〈此処の患者は、血縁がいなくなって、天涯孤独になると自動的に舌を噛み切る〉
〈違うな、俺が夜中に、メスで患者の舌を切るんだ〉
〈まじか?〉
〈まじだよ、勿論。分かっているだろう〉
〈嗚呼、全く、やりきれないな〉
亀田はレコーダーのスイッチを一旦切った。
「院長先生、如何ですか」
潮院長は沈黙したままだった。
「院長、もう一つ、これをご覧ください」
亀田はハンカチでくるんだコップを取り出した。
「これは、第二の自殺者、横川さんのコップです。実は遺体の第一発見者の私が、こっそり遺体の傍から取ったものです。コップの指紋を検出しました。調べてみると、横川さん以外に、もう一人、別人の指紋が付着していました。コップは完全な自己管理で、あの夜にコップ消毒されたばかりなのにです。何者かが、横川さんの死の直前に、このコップに触れているんです」
潮院長は表情を硬直させた。
「あの夜に当直だった、山田看護師に、故意に私のコップを触らせました。単なる勘でしたが、驚いたことに、横川さんのコップに触れたのは、その指紋の一致から、山田看護師であることが分かりました。先程の盗聴器録音とも合致する訳です」
院長は亀田を睨めつけた。
「すると、横川さんを殺害したのは、山田看護師だったのか。私はそれだけではないと思っています。次の盗聴器録音をお聴きください。次には、院長先生、貴方の声が入っています」
〈……浦島は大丈夫か?〉
〈院長先生、大丈夫だとは思いますが〉
〈横川は奴の親友だったからな〉
〈ええ〉
〈浦島が何か口を割るようなら、浦島も処分しろ〉
亀田は、院長を見返した。
「この事件の犯人は、閉鎖空間だからこの中にいる筈と考えていましたが、犯人は実際、松元さんと私を除く、職員、患者、全員が犯人の、組織的な犯罪だった訳です。この病院の職員と患者は一体化している。浦島さんも明らかに真相を知っていましたよ。……横川氏は、山神さんの殺害を目撃したから殺されたのですね。横川氏のスマホは職員に取り上げられていた。警察に通報されないためですね」
「宜しいかね……」院長は漸く口を開いた。「全ては国の福祉行政のためなんだ。毎年生活保護費がかさんで財政はパンクする。山神のような孤独者は死んで当たり前なのだ。88歳でもう充分生きた。冷たいようだが、これが現実だ。医療パターナリズム、父権主義とは、本来こういうものなんだよ」
亀田は首を振った。
診察室のドアが開き、山尾と山田、両看護師が入ってきた。
亀田はポケットから小型ナイフを取り出した。
「精神科病棟内でそんなものを振り回したら、どうなるか分かっているかね」
「私も、自分の身は守らなくてはなりません」
亀田は片方の手で、スマホを取り出した。
「ああ、叔父さん。院長、叔父さんというのは、県警の警部補です……叔父さん、亀田です。潮病院で殺人事件が起きました。ええ、既に証拠は掴んでいます。至急来てください。それから、県に通報をお願い致します。潮病院で入院患者の虐待があります……」
意外にも、院長は平然としていた。
「無駄だ、亀田君、ナイフを捨てたまえ。此処は精神病院だ、君は全く分かっていない」
「何をです」
「君の言葉は全て妄想として、握り潰せるのだ。君は保護室に入らねばならない」
「私は任意入院だ、私の意思で退院出来る」
「違うのだ。例え警察が来ても、君は重篤患者として保護室監禁だ」
「直ぐに警察が来るんですよ」
「無駄だ。君の証拠とやらは我々が握り潰す」
亀田は立ち上がったが、診察室の端に追い詰められた。
「院長、貴方こそ無駄だ。警察は兎も角、県に虐待を通報した。精神保健福祉法の改正があった。虐待のあったこの病院は、どの道処分される。二度の不審死を警察が再捜査する」
看護師達が進み出てきた。
「私は私立探偵だ。格闘技の鍛錬にも日々精進している。舐めてもらっては困る。二人くらい楽に倒せる。院長、まだ患者の方が新時代を理解している。虐待の通報は妄想として、握り潰せない。時間の問題だ。従兄弟の警部補が直ぐに此処に来る」