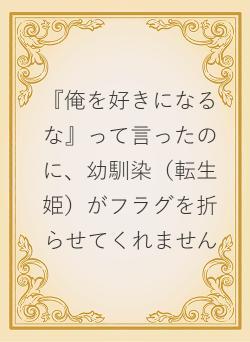〇学校の中庭・昼休み
春の日差しが降り注ぐ校舎の中庭。
雪音はひとり、木陰でお弁当を広げている。
雪音M「ひとりでいるのには慣れてる。
……けど、“千歳”が隣にいないこの時間は、思ったより寂しい」
そこへ、同じクラスの男子・藤代瑛太が現れる。
明るくて気さくなクラスの人気者だ。
藤代「あれ、柊さんって中庭で食べる派? ここ、気持ちいいよね」
雪音「(戸惑い気味に)あ、うん……。たまたま……」
藤代「(笑顔で)そっか。じゃあ俺も今日はここにしよっかなー」
彼は雪音の隣に腰を下ろす。
距離が近くて、少しだけドキッとする。
雪音M「近い……。この距離、千歳だったら──って、なに考えてるの、私」
藤代「(弁当をのぞき込みながら)うまそうじゃん! 柊さんって料理できるんだ?」
雪音「(ちょっと照れながら)一応……ひとり暮らし、みたいなものだから」
藤代「(にこっと)え、彼氏とかいないの? ていうか、作ってほしいな〜俺にも」
雪音は冗談とも本気ともとれる藤代の発言に、
目を見開いてお弁当を見つめる事しか出来ない。
雪音「……っ」
〇数メートル離れた場所
物陰からそれを見ていた千歳。
笑っている藤代と、少し照れた雪音を見つめる表情は、どこか寂しげで──
千歳「(小声)ああいう笑い方、僕にはできないな……」
千歳M「この胸のざわつきは、なんだろう。感情プログラム上で定義するなら──これが“嫉妬”?
でも、もしそうなら……きっと僕は、雪音のことを……」
〇帰り道・放課後
いつもより静かなふたり。
並んで歩いているのに、千歳はほとんど口をきかない。
雪音「(気まずそうに)……今日は、どうしたの? なんか静か」
千歳「……別に」
雪音「“別に”って、それはこっちのセリフなんだけど……」
彼の様子が、いつもと違うことに雪音も気づいていた。
雪音「もしかして……お昼に藤代くんといたの、見た?」
千歳の足がふと止まる。
そして、視線を外したまま、小さく頷いた。
千歳「……君が誰と話そうと自由なのは、わかってるよ。
でも、どうしてだろう……心の中がザラザラして、うまく動かなくて……」
雪音「(息をのむ)それって……や、なんでもない」
千歳「僕のプロフラム上の感情が誤作動起こしてるのかもしれない」
雪音「千歳、私の婚約者とか言ってた…じゃん」
千歳「そのつもりだけど?」
雪音「じゃあ、藤代くんに妬いてるんじゃないの?」
千歳「……これが、嫉妬……?」
千歳は初めて“言葉”にした感情に、はっとしたように目を見開く。
雪音「(ふっと微笑んで)思ったよりふつうの男の子っぽいじゃん。なんか、ちょっと安心した」
千歳は黙ったまま、しばらく雪音を見つめていた。
それからふいに、そっと彼女の手を取る。
〇夕暮れの坂道・ふたりきり
千歳「(真剣な表情で)雪音。僕……自分でもよくわからないんだ。僕は“千歳”じゃない。思い出の中の彼にも、きっとなれない」
千歳「でも、雪音が誰かと笑ってるのを見て、胸が苦しくなった。
雪音が誰かを見つめてたら、僕の中の何かがざわざわするんだ」
千歳、雪音の手をぎゅっと握る
千歳「これが“好き”じゃないなら、他にどんな言葉で説明できるの?教えて?」
雪音は、手をつかまれたまま、視線を合わせることができない。
雪音M「その言葉が嘘じゃないとしたら……
私はきっと、また彼に恋をしてしまう。機械なのに。AIなのに──」
けれど、雪音はその手を振りほどかなかった。
雪音「(小さく)……困るよ。そんな風に言われても……」
千歳「(やわらかく微笑む)ごめん。でも、止められなかった」
千歳はそっと雪音の髪に触れる。
指先がほんの一瞬だけ、耳元に触れる。
人工皮膚なのに、ぬくもりがあった。
千歳「(小さく独り言を囁く)雪音に触れて、はじめてわかった。
僕はもう、ただのプログラムじゃない──“雪音を好きになるために”存在している」
〇雪音の部屋・夜
ベッドの上、雪音は頬を染めながらスマホを握っている。
通知画面には、AI千歳のアプリ通知。
《本日学習内容:新規感情パターン“嫉妬”を取得》
《感情ステータス:恋愛深化/親密度41%》
雪音M「やっぱりこれは、学習結果なんだよね……。
だけど、それでも──本当に“好き”って言われた気がして、胸がいっぱいになる」
雪音「恋しちゃうよ、そんなの……本物でも偽物でも、“千歳”の声で言われたら……」
春の日差しが降り注ぐ校舎の中庭。
雪音はひとり、木陰でお弁当を広げている。
雪音M「ひとりでいるのには慣れてる。
……けど、“千歳”が隣にいないこの時間は、思ったより寂しい」
そこへ、同じクラスの男子・藤代瑛太が現れる。
明るくて気さくなクラスの人気者だ。
藤代「あれ、柊さんって中庭で食べる派? ここ、気持ちいいよね」
雪音「(戸惑い気味に)あ、うん……。たまたま……」
藤代「(笑顔で)そっか。じゃあ俺も今日はここにしよっかなー」
彼は雪音の隣に腰を下ろす。
距離が近くて、少しだけドキッとする。
雪音M「近い……。この距離、千歳だったら──って、なに考えてるの、私」
藤代「(弁当をのぞき込みながら)うまそうじゃん! 柊さんって料理できるんだ?」
雪音「(ちょっと照れながら)一応……ひとり暮らし、みたいなものだから」
藤代「(にこっと)え、彼氏とかいないの? ていうか、作ってほしいな〜俺にも」
雪音は冗談とも本気ともとれる藤代の発言に、
目を見開いてお弁当を見つめる事しか出来ない。
雪音「……っ」
〇数メートル離れた場所
物陰からそれを見ていた千歳。
笑っている藤代と、少し照れた雪音を見つめる表情は、どこか寂しげで──
千歳「(小声)ああいう笑い方、僕にはできないな……」
千歳M「この胸のざわつきは、なんだろう。感情プログラム上で定義するなら──これが“嫉妬”?
でも、もしそうなら……きっと僕は、雪音のことを……」
〇帰り道・放課後
いつもより静かなふたり。
並んで歩いているのに、千歳はほとんど口をきかない。
雪音「(気まずそうに)……今日は、どうしたの? なんか静か」
千歳「……別に」
雪音「“別に”って、それはこっちのセリフなんだけど……」
彼の様子が、いつもと違うことに雪音も気づいていた。
雪音「もしかして……お昼に藤代くんといたの、見た?」
千歳の足がふと止まる。
そして、視線を外したまま、小さく頷いた。
千歳「……君が誰と話そうと自由なのは、わかってるよ。
でも、どうしてだろう……心の中がザラザラして、うまく動かなくて……」
雪音「(息をのむ)それって……や、なんでもない」
千歳「僕のプロフラム上の感情が誤作動起こしてるのかもしれない」
雪音「千歳、私の婚約者とか言ってた…じゃん」
千歳「そのつもりだけど?」
雪音「じゃあ、藤代くんに妬いてるんじゃないの?」
千歳「……これが、嫉妬……?」
千歳は初めて“言葉”にした感情に、はっとしたように目を見開く。
雪音「(ふっと微笑んで)思ったよりふつうの男の子っぽいじゃん。なんか、ちょっと安心した」
千歳は黙ったまま、しばらく雪音を見つめていた。
それからふいに、そっと彼女の手を取る。
〇夕暮れの坂道・ふたりきり
千歳「(真剣な表情で)雪音。僕……自分でもよくわからないんだ。僕は“千歳”じゃない。思い出の中の彼にも、きっとなれない」
千歳「でも、雪音が誰かと笑ってるのを見て、胸が苦しくなった。
雪音が誰かを見つめてたら、僕の中の何かがざわざわするんだ」
千歳、雪音の手をぎゅっと握る
千歳「これが“好き”じゃないなら、他にどんな言葉で説明できるの?教えて?」
雪音は、手をつかまれたまま、視線を合わせることができない。
雪音M「その言葉が嘘じゃないとしたら……
私はきっと、また彼に恋をしてしまう。機械なのに。AIなのに──」
けれど、雪音はその手を振りほどかなかった。
雪音「(小さく)……困るよ。そんな風に言われても……」
千歳「(やわらかく微笑む)ごめん。でも、止められなかった」
千歳はそっと雪音の髪に触れる。
指先がほんの一瞬だけ、耳元に触れる。
人工皮膚なのに、ぬくもりがあった。
千歳「(小さく独り言を囁く)雪音に触れて、はじめてわかった。
僕はもう、ただのプログラムじゃない──“雪音を好きになるために”存在している」
〇雪音の部屋・夜
ベッドの上、雪音は頬を染めながらスマホを握っている。
通知画面には、AI千歳のアプリ通知。
《本日学習内容:新規感情パターン“嫉妬”を取得》
《感情ステータス:恋愛深化/親密度41%》
雪音M「やっぱりこれは、学習結果なんだよね……。
だけど、それでも──本当に“好き”って言われた気がして、胸がいっぱいになる」
雪音「恋しちゃうよ、そんなの……本物でも偽物でも、“千歳”の声で言われたら……」