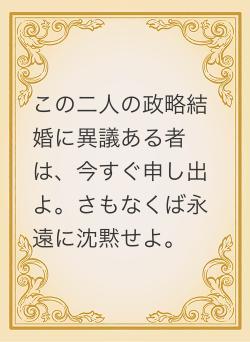「ええ。ごめんなさい。ロベルトのご友人に、こんなこと。気まずいですわね……今、私は不安に思っていることは、これからどうやって生きようか……ということです。私はこれまで、ロベルトと結婚するという前提で生きて来ましたし……あ! 良かったら、ブライアント公爵家で雇ってくれませんか?」
「え?」
「その……まだ、ニコラス様はご結婚はしていないと思うのですが、私は貴族令嬢として育ち、礼儀作法は教えられるほどには精通しているつもりです。ですから、未来のお嬢様の家庭教師として……」
とは言え、彼はまだロベルトと同じ二十二歳で、遊びたい盛りの若さだ。これから、結婚をして子どもも生まれて……となると、かなり先になってしまう。
けれど、私は実家に居座ったままで跡取りの弟のお荷物でなんて、居たくはない。
ブライアント公爵家ならば、うなるほどの財産を持っているだろうし、少々縁がある私を雇ってくれるだけの金銭的な余裕を持っていると考えたからだ。
「参ったな……ルシール嬢」
「はい?」
ニコラス様は口に手を当てて、言いにくそうに私に質問した。
「え?」
「その……まだ、ニコラス様はご結婚はしていないと思うのですが、私は貴族令嬢として育ち、礼儀作法は教えられるほどには精通しているつもりです。ですから、未来のお嬢様の家庭教師として……」
とは言え、彼はまだロベルトと同じ二十二歳で、遊びたい盛りの若さだ。これから、結婚をして子どもも生まれて……となると、かなり先になってしまう。
けれど、私は実家に居座ったままで跡取りの弟のお荷物でなんて、居たくはない。
ブライアント公爵家ならば、うなるほどの財産を持っているだろうし、少々縁がある私を雇ってくれるだけの金銭的な余裕を持っていると考えたからだ。
「参ったな……ルシール嬢」
「はい?」
ニコラス様は口に手を当てて、言いにくそうに私に質問した。