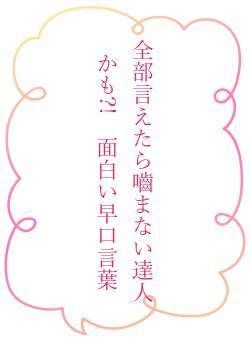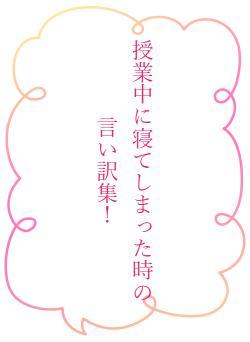柔らかな春の風が、そっと頬を撫でる。
満開の桜が、舞い散る花びらとともに光を浴びて輝いていた。
律歌は深く息を吸い込み、目の前にそびえる大きな屋敷を見上げた。
そこは――奏希くんの家。
奏希くんがいた場所。
彼が夢を語り、共にピアノを奏でた場所。
6年ぶりに訪れたこの家は、以前と変わらぬ姿で静かに佇んでいた。
けれど、奏希くんがいないという事実だけが、そこにぽっかりと空いた穴のように感じられる。
「久しぶりですね、律歌さん」
玄関の扉が開き、奏希くんの母が微笑んでいた。
彼女は変わらず上品で、けれど少し年を重ねたように見える。
「本当に立派になられて……あなたの演奏、何度もテレビで拝見しましたよ」
「……ありがとうございます」
律歌は少し照れくさそうに微笑んだ。
22歳になった今、律歌は世界的に有名なピアニストとして活動している。
ヨーロッパを拠点に、世界各国でコンサートを開き、名だたる音楽祭にも招かれるようになった。
でも――。
「律歌さん、どうぞ。奏希の部屋へ」
律歌は深く頷き、懐かしい廊下をゆっくりと歩き出した。
一歩踏み出すごとに、6年前の記憶が鮮やかに蘇る。
彼と過ごした日々、彼の言葉、彼の笑顔――。
静かに扉を開けると、そこには変わらぬままのピアノ室が広がっていた。
大きなグランドピアノが、優雅に佇んでいる。
あの時と同じ、黒く艶やかな鍵盤。
奏希くんがいつも弾いていた、彼の音が詰まったピアノ。
律歌はそっと、鍵盤に触れた。
指先に伝わるひんやりとした感触。
それはまるで奏希の手のひらを思わせる温もりのようだった。
「奏希くん……私、ここまで来たよ」
小さく呟いた声が、静かな部屋に優しく溶けていく。
奏希くんが遺してくれた音楽を、律歌は今も奏で続けている。
彼の分まで、彼の夢だった音を、この世界に響かせるために。
目を閉じて、ゆっくりと鍵盤を押す。
奏希くんと一緒に弾いた、あの旋律が、空間に優しく広がる。
まるで彼が隣にいて、一緒に演奏しているかのように――。
「奏希くん、聴いてる……?」
涙が零れそうになるのを必死でこらえながら、律歌は微笑んだ。
音は消えない。
彼と紡いだ音楽は、これからも響き続ける。
そして、律歌はまた前を向いて、新たな旋律を奏で始める。
――奏希くんの想いと共に。
満開の桜が、舞い散る花びらとともに光を浴びて輝いていた。
律歌は深く息を吸い込み、目の前にそびえる大きな屋敷を見上げた。
そこは――奏希くんの家。
奏希くんがいた場所。
彼が夢を語り、共にピアノを奏でた場所。
6年ぶりに訪れたこの家は、以前と変わらぬ姿で静かに佇んでいた。
けれど、奏希くんがいないという事実だけが、そこにぽっかりと空いた穴のように感じられる。
「久しぶりですね、律歌さん」
玄関の扉が開き、奏希くんの母が微笑んでいた。
彼女は変わらず上品で、けれど少し年を重ねたように見える。
「本当に立派になられて……あなたの演奏、何度もテレビで拝見しましたよ」
「……ありがとうございます」
律歌は少し照れくさそうに微笑んだ。
22歳になった今、律歌は世界的に有名なピアニストとして活動している。
ヨーロッパを拠点に、世界各国でコンサートを開き、名だたる音楽祭にも招かれるようになった。
でも――。
「律歌さん、どうぞ。奏希の部屋へ」
律歌は深く頷き、懐かしい廊下をゆっくりと歩き出した。
一歩踏み出すごとに、6年前の記憶が鮮やかに蘇る。
彼と過ごした日々、彼の言葉、彼の笑顔――。
静かに扉を開けると、そこには変わらぬままのピアノ室が広がっていた。
大きなグランドピアノが、優雅に佇んでいる。
あの時と同じ、黒く艶やかな鍵盤。
奏希くんがいつも弾いていた、彼の音が詰まったピアノ。
律歌はそっと、鍵盤に触れた。
指先に伝わるひんやりとした感触。
それはまるで奏希の手のひらを思わせる温もりのようだった。
「奏希くん……私、ここまで来たよ」
小さく呟いた声が、静かな部屋に優しく溶けていく。
奏希くんが遺してくれた音楽を、律歌は今も奏で続けている。
彼の分まで、彼の夢だった音を、この世界に響かせるために。
目を閉じて、ゆっくりと鍵盤を押す。
奏希くんと一緒に弾いた、あの旋律が、空間に優しく広がる。
まるで彼が隣にいて、一緒に演奏しているかのように――。
「奏希くん、聴いてる……?」
涙が零れそうになるのを必死でこらえながら、律歌は微笑んだ。
音は消えない。
彼と紡いだ音楽は、これからも響き続ける。
そして、律歌はまた前を向いて、新たな旋律を奏で始める。
――奏希くんの想いと共に。