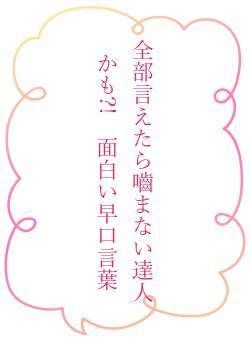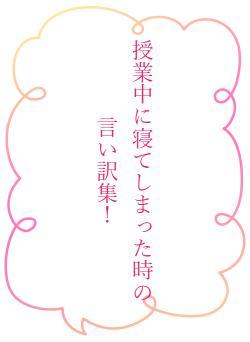冷たい冬が過ぎ、やがて春が訪れた。
それでも、律歌の時間はあの日から止まったままだった。
奏希くんがいない日常は、色を失い、まるで遠い世界の出来事のようだった。
食事をしても、会話をしても、すべてが上の空で、ただ空白の時間が流れていく。
「お姉ちゃん……」
響歌の声に振り向くと、心配そうな目がそこにあった。
「ねぇ、お姉ちゃん。そろそろ……ピアノ、弾いてみない?」
律歌はかぶりを振った。
「……もう、無理だよ」
「でも、奏希さんとの思い出、ピアノと一緒に閉じ込めたままでいいの?」
響歌の言葉に胸が締めつけられる。
ピアノを弾けば、奏希くんを思い出してしまう。
あの温かい笑顔も、優しい声も、もう二度と戻ってこないのに。
それなのに、どうして――
「……でも、奏希さんは言ってた」
響歌は静かに続けた。
「お姉ちゃんが奏でる音が好きだって……。お姉ちゃんのピアノが、世界で一番心に響くって」
律歌は息を呑んだ。
奏希くんが、生きていた頃に言ってくれた言葉。
あの人は、いつも律歌の音を褒めてくれた。
自信を失っていた律歌に、「君のピアノは美しい」って、何度も伝えてくれた。
――奏希くんは、私の音が好きだった。
――だったら、私は……。
気づけば、律歌は部屋の片隅に置いてあったピアノに向かっていた。
震える指で鍵盤に触れる。
一音、また一音と、ゆっくりと音を紡ぐ。
奏希が教えてくれた、あの曲だった。
ぽろぽろと涙が零れ落ちる。
それでも、涙を流しながらも律歌は音を止めなかった。
ピアノの音が、優しく心に響く。
奏希くんがこの音を好きだと言ってくれた。
この音を愛してくれた。
「奏希くん……」
律歌は涙を拭い、そっと微笑んだ。
――私は、もう大丈夫だよ。
彼が遺してくれた音とともに、律歌はまた前を向いて歩き出す。
彼の分まで、この音を響かせていくために。
それでも、律歌の時間はあの日から止まったままだった。
奏希くんがいない日常は、色を失い、まるで遠い世界の出来事のようだった。
食事をしても、会話をしても、すべてが上の空で、ただ空白の時間が流れていく。
「お姉ちゃん……」
響歌の声に振り向くと、心配そうな目がそこにあった。
「ねぇ、お姉ちゃん。そろそろ……ピアノ、弾いてみない?」
律歌はかぶりを振った。
「……もう、無理だよ」
「でも、奏希さんとの思い出、ピアノと一緒に閉じ込めたままでいいの?」
響歌の言葉に胸が締めつけられる。
ピアノを弾けば、奏希くんを思い出してしまう。
あの温かい笑顔も、優しい声も、もう二度と戻ってこないのに。
それなのに、どうして――
「……でも、奏希さんは言ってた」
響歌は静かに続けた。
「お姉ちゃんが奏でる音が好きだって……。お姉ちゃんのピアノが、世界で一番心に響くって」
律歌は息を呑んだ。
奏希くんが、生きていた頃に言ってくれた言葉。
あの人は、いつも律歌の音を褒めてくれた。
自信を失っていた律歌に、「君のピアノは美しい」って、何度も伝えてくれた。
――奏希くんは、私の音が好きだった。
――だったら、私は……。
気づけば、律歌は部屋の片隅に置いてあったピアノに向かっていた。
震える指で鍵盤に触れる。
一音、また一音と、ゆっくりと音を紡ぐ。
奏希が教えてくれた、あの曲だった。
ぽろぽろと涙が零れ落ちる。
それでも、涙を流しながらも律歌は音を止めなかった。
ピアノの音が、優しく心に響く。
奏希くんがこの音を好きだと言ってくれた。
この音を愛してくれた。
「奏希くん……」
律歌は涙を拭い、そっと微笑んだ。
――私は、もう大丈夫だよ。
彼が遺してくれた音とともに、律歌はまた前を向いて歩き出す。
彼の分まで、この音を響かせていくために。