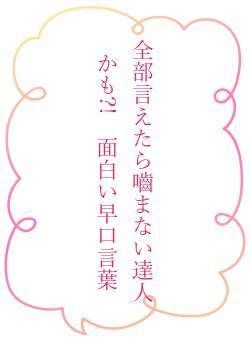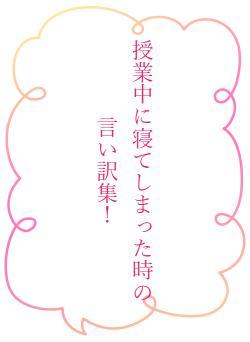病室の時間が止まったようだった。
ベッドの上で目を閉じる奏希くんの姿は、まるで眠っているかのように穏やかだった。
しかし――もう、目を開けることはない。
「……うそ……」
律歌は震える指で、奏希くんの頬に触れた。
冷たい。
こんなに、冷たい。
「奏希くん……ねぇ……起きてよ……」
声が震える。涙が零れ落ちる。
どれだけ呼んでも、奏希くんはもう答えてくれなかった。
「いやだ……いやだよ……!」
律歌は必死に奏希くんの手を握りしめた。
温もりはすでに消え去り、彼を形作っていた命のぬくもりが失われていることを、否応なく実感させられる。
嫌だ。こんなの、嫌だ。
「奏希くん、ねぇ、冗談だよね……?」
頬を撫でても、呼吸は戻らない。
指を絡めても、握り返してはくれない。
涙が頬を伝い、指輪の上に落ちた。
「奏希くん……奏希くん……っ!!」
張り裂けそうな痛みが胸を締め付ける。
何もかもが色を失い、世界が崩れていくようだった。
律歌は叫んだ。
声にならない声で、奏希くんの名前を何度も何度も呼んだ。
でも――その声はもう、彼には届かない。
***
それからの日々は、ただただ空っぽだった。
朝が来ても、目覚めたくなかった。
夜が来ても、眠りたくなかった。
ピアノに指を置いても、何も感じなかった。
音が、何の意味も持たないものに思えた。
「奏希くん……」
指輪を握りしめる。
「なんで……なんで私を置いていったの……?」
返事はない。
あるわけがない。
心が、ぽっかりと空いた。
まるで、世界に取り残されたみたいに――。
ベッドの上で目を閉じる奏希くんの姿は、まるで眠っているかのように穏やかだった。
しかし――もう、目を開けることはない。
「……うそ……」
律歌は震える指で、奏希くんの頬に触れた。
冷たい。
こんなに、冷たい。
「奏希くん……ねぇ……起きてよ……」
声が震える。涙が零れ落ちる。
どれだけ呼んでも、奏希くんはもう答えてくれなかった。
「いやだ……いやだよ……!」
律歌は必死に奏希くんの手を握りしめた。
温もりはすでに消え去り、彼を形作っていた命のぬくもりが失われていることを、否応なく実感させられる。
嫌だ。こんなの、嫌だ。
「奏希くん、ねぇ、冗談だよね……?」
頬を撫でても、呼吸は戻らない。
指を絡めても、握り返してはくれない。
涙が頬を伝い、指輪の上に落ちた。
「奏希くん……奏希くん……っ!!」
張り裂けそうな痛みが胸を締め付ける。
何もかもが色を失い、世界が崩れていくようだった。
律歌は叫んだ。
声にならない声で、奏希くんの名前を何度も何度も呼んだ。
でも――その声はもう、彼には届かない。
***
それからの日々は、ただただ空っぽだった。
朝が来ても、目覚めたくなかった。
夜が来ても、眠りたくなかった。
ピアノに指を置いても、何も感じなかった。
音が、何の意味も持たないものに思えた。
「奏希くん……」
指輪を握りしめる。
「なんで……なんで私を置いていったの……?」
返事はない。
あるわけがない。
心が、ぽっかりと空いた。
まるで、世界に取り残されたみたいに――。