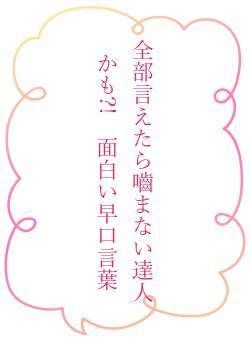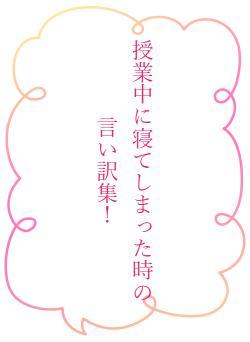最後の音が静かに消えていく。
まるで夜空に溶けていく星の光のように、儚く、静かに。
律歌は鍵盤からそっと指を離し、ゆっくりと振り返った。
奏希くんはベッドの上で、微かに微笑んでいた。
その姿はあまりにも脆く、今にも消えてしまいそうだった。
「……ありがとう、律歌」
かすれた声が、静寂の中に溶けていく。
「奏希くん……」
律歌がそっと手を伸ばすと、奏希くんは震える指で何かを握りしめていた。
「……これ……受け取ってほしい」
ゆっくりと開かれたその手のひらに、繊細な銀の指輪が乗っていた。
小さな石が月光を受けて儚く輝いている。
「……奏希くん、これは……?」
「ずっと……渡したかったんだ」
律歌の手をそっと取ると、奏希は震える指で、律歌の薬指に指輪を通した。
「本当は……ずっと一緒に生きて、もっとたくさんの時間を過ごしたかった……」
その言葉に、律歌の胸が締め付けられる。
「だけど……僕は……」
律歌は、そっと奏希の手を握りしめた。
「そんなこと言わないで……奏希くん」
目の奥が熱くなる。
でも、今だけは泣きたくなかった。
「たとえ時間が少なくても……私は……私は奏希くんと一緒にいられて、幸せだよ」
奏希くんが、微かに微笑んだ。
「僕も……」
指輪にそっと唇を寄せ、奏希くんは目を閉じた。
「律歌……君の音は、ずっと僕の中に生き続けるよ」
まるで、夜の静寂に溶けるように――。
まるで夜空に溶けていく星の光のように、儚く、静かに。
律歌は鍵盤からそっと指を離し、ゆっくりと振り返った。
奏希くんはベッドの上で、微かに微笑んでいた。
その姿はあまりにも脆く、今にも消えてしまいそうだった。
「……ありがとう、律歌」
かすれた声が、静寂の中に溶けていく。
「奏希くん……」
律歌がそっと手を伸ばすと、奏希くんは震える指で何かを握りしめていた。
「……これ……受け取ってほしい」
ゆっくりと開かれたその手のひらに、繊細な銀の指輪が乗っていた。
小さな石が月光を受けて儚く輝いている。
「……奏希くん、これは……?」
「ずっと……渡したかったんだ」
律歌の手をそっと取ると、奏希は震える指で、律歌の薬指に指輪を通した。
「本当は……ずっと一緒に生きて、もっとたくさんの時間を過ごしたかった……」
その言葉に、律歌の胸が締め付けられる。
「だけど……僕は……」
律歌は、そっと奏希の手を握りしめた。
「そんなこと言わないで……奏希くん」
目の奥が熱くなる。
でも、今だけは泣きたくなかった。
「たとえ時間が少なくても……私は……私は奏希くんと一緒にいられて、幸せだよ」
奏希くんが、微かに微笑んだ。
「僕も……」
指輪にそっと唇を寄せ、奏希くんは目を閉じた。
「律歌……君の音は、ずっと僕の中に生き続けるよ」
まるで、夜の静寂に溶けるように――。