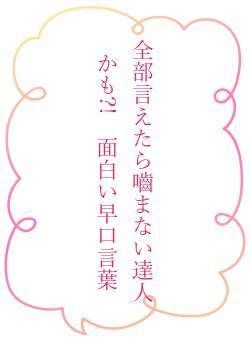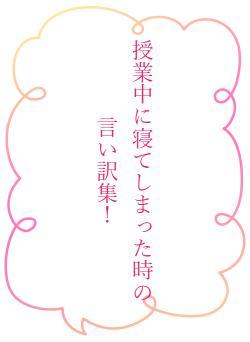手を繋いだまま、二人はツリーの前で立ち止まった。
宝石のように輝くイルミネーションが、奏希くんの横顔を優しく照らしている。
その光景があまりにも美しくて、律歌は無意識のうちに彼をじっと見つめていた。
「どうしたの?」
奏希くんが律歌を覗き込むように尋ねる。その声の優しさが律歌の胸をぎゅっと締め付けた。
「……奏希くんが、綺麗だなって思ったの」
言った瞬間、恥ずかしさがこみ上げてきて顔を伏せた。しかし、奏希くんは驚いたように目を瞬き、そのあとふっと微笑んだ。
「律歌の方こそ、綺麗だよ」
「えっ……?」
「今日の律歌、すごく楽しそうで、幸せそうで……そんな顔を見られて、俺も嬉しい」
律歌の心臓が、鼓動を速める。
奏希くんの目が、そっと律歌の唇を捉えた。
「……律歌」
その名前を呼ぶ声が、優しくて、どこか切なさを帯びていた。
「僕、今……すごく、律歌に触れたい」
鼓動が、壊れそうなくらい高鳴る。
律歌は何も言えず、ただ静かに目を閉じた。
次の瞬間、ふわりと温かいものが唇に触れた。
柔らかく、優しく、まるで壊れ物を扱うような繊細なキスだった。
触れて、離れて、またそっと触れて――。
長くはないけれど、心が震えるほどのキス。
イルミネーションの光が、二人を包み込むように輝いていた。
唇が離れたあと、律歌はそっと目を開ける。
奏希くんは穏やかに微笑んでいた。
「……律歌、大好き」
その言葉に、律歌の目元がじんわりと熱くなる。
「……私も、奏希くんが大好き」
もう迷わない。
どれだけ時間が残されていようと、この気持ちは揺るがない。
――この先、何があっても、最後まで奏希くんと一緒にいたい。
そう、心から思った。
宝石のように輝くイルミネーションが、奏希くんの横顔を優しく照らしている。
その光景があまりにも美しくて、律歌は無意識のうちに彼をじっと見つめていた。
「どうしたの?」
奏希くんが律歌を覗き込むように尋ねる。その声の優しさが律歌の胸をぎゅっと締め付けた。
「……奏希くんが、綺麗だなって思ったの」
言った瞬間、恥ずかしさがこみ上げてきて顔を伏せた。しかし、奏希くんは驚いたように目を瞬き、そのあとふっと微笑んだ。
「律歌の方こそ、綺麗だよ」
「えっ……?」
「今日の律歌、すごく楽しそうで、幸せそうで……そんな顔を見られて、俺も嬉しい」
律歌の心臓が、鼓動を速める。
奏希くんの目が、そっと律歌の唇を捉えた。
「……律歌」
その名前を呼ぶ声が、優しくて、どこか切なさを帯びていた。
「僕、今……すごく、律歌に触れたい」
鼓動が、壊れそうなくらい高鳴る。
律歌は何も言えず、ただ静かに目を閉じた。
次の瞬間、ふわりと温かいものが唇に触れた。
柔らかく、優しく、まるで壊れ物を扱うような繊細なキスだった。
触れて、離れて、またそっと触れて――。
長くはないけれど、心が震えるほどのキス。
イルミネーションの光が、二人を包み込むように輝いていた。
唇が離れたあと、律歌はそっと目を開ける。
奏希くんは穏やかに微笑んでいた。
「……律歌、大好き」
その言葉に、律歌の目元がじんわりと熱くなる。
「……私も、奏希くんが大好き」
もう迷わない。
どれだけ時間が残されていようと、この気持ちは揺るがない。
――この先、何があっても、最後まで奏希くんと一緒にいたい。
そう、心から思った。