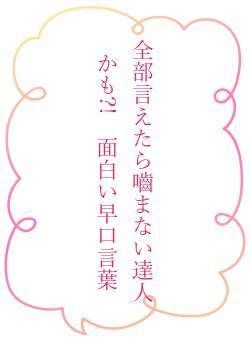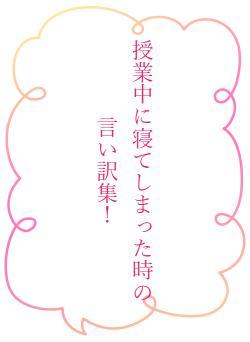病室の窓から差し込む冬の日差しが穏やかで、静寂に包まれた室内に暖かさをもたらしていた。
律歌はいつものように奏希の病室に入り、にこやかに微笑んだ。
「おはよう、奏希くん」
「おはよう、律歌」
奏希くんは微笑んで応じたが、どこかぎこちなかった。
律歌はベッドの横に座ると、小さなバッグから温かい紅茶の入った水筒を取り出した。
「今日はね、ちょっと特別な紅茶を持ってきたの。カモミールとハチミツ入りだよ。奏希くん、最近寝つきが悪いって言ってたから」
「……ありがとう。律歌は本当に優しいね」
奏希くんは紅茶の香りを楽しみながら、小さく微笑んだ。しかし、その目はどこか寂しげだった。
律歌はふと、その表情の変化に気づき、そっと首を傾げた。
「奏希くん……? 何かあった?」
奏希くんは少し迷うように目を伏せ、それから意を決したように律歌を見つめた。
「律歌……最近、毎日俺のお見舞いに来てくれてるよね」
「うん。だって……奏希くんに会いたいし、一緒にいたいから」
律歌くんは当然のように微笑んだが、奏希の表情は複雑なままだった。
「でも……それでいいの?」
「え……?」
「響歌ちゃんや鈴子ちゃんとは遊んでる? 学校の友達と楽しい時間を過ごしてる?」
奏希くんの言葉に、律歌は少し驚いたように目を瞬かせた。
「私は……今は奏希くんのそばにいたいから」
「その気持ちはすごく嬉しい。でも……律歌の時間は律歌のものだよ」
奏希くんは静かに律歌の手を取った。
「僕はもうそんなに長く生きられない。でも、律歌には未来がある。友達と遊んで、笑って、たくさんの思い出を作ってほしいんだ」
律歌はその言葉にハッと息を呑んだ。
「でも……!」
「律歌は優しすぎるよ。僕のことを思ってくれるのは本当に嬉しい。
でも、それで律歌が自分の時間を犠牲にするのは違うと思うんだ」
奏希の手は温かく、それでいてどこか儚かった。
「僕のそばにずっといてくれるのは嬉しいよ。でも、律歌が笑っているところが一番好きなんだ。
だから……響歌ちゃんや鈴子ちゃんと過ごす時間も大切にしてほしい」
律歌は俯き、握られた手の温もりを感じながら、静かに呟いた。
「……奏希くんは、私といると迷惑?」
「違うよ。そんなこと、絶対にない。でも……もし、律歌が僕のそばにいることで、自分の時間を削っているなら、
それは僕の望むことじゃないんだ」
奏希くんは優しく律歌の髪を撫でた。
「僕は律歌が幸せでいてくれることが、一番の願いなんだ」
律歌はしばらく言葉を発せず、ゆっくりと目を閉じた。
奏希くんの言葉は、まっすぐに彼女の心に響いていた。
「……わかった」
律歌は顔を上げ、少し寂しげに微笑んだ。
「じゃあ……明日は響歌と鈴子と遊びに行くね」
「うん、それがいいよ」
奏希くんは安堵したように微笑んだ。
――奏希くんは私が自分のことを大切に思ってくれていることを知っている。
でも、だからこそ、彼女が自分自身の人生を見失わないようにしたかった。
律歌は窓の外に目を向けた。
冬の青空が、澄み切った光を降り注いでいた。
(私は奏希くんのそばにいたい。でも、奏希くんが望むことも大切にしたい)
律歌はそっと手を握りしめ、決意を固めるように微笑んだ。
律歌はいつものように奏希の病室に入り、にこやかに微笑んだ。
「おはよう、奏希くん」
「おはよう、律歌」
奏希くんは微笑んで応じたが、どこかぎこちなかった。
律歌はベッドの横に座ると、小さなバッグから温かい紅茶の入った水筒を取り出した。
「今日はね、ちょっと特別な紅茶を持ってきたの。カモミールとハチミツ入りだよ。奏希くん、最近寝つきが悪いって言ってたから」
「……ありがとう。律歌は本当に優しいね」
奏希くんは紅茶の香りを楽しみながら、小さく微笑んだ。しかし、その目はどこか寂しげだった。
律歌はふと、その表情の変化に気づき、そっと首を傾げた。
「奏希くん……? 何かあった?」
奏希くんは少し迷うように目を伏せ、それから意を決したように律歌を見つめた。
「律歌……最近、毎日俺のお見舞いに来てくれてるよね」
「うん。だって……奏希くんに会いたいし、一緒にいたいから」
律歌くんは当然のように微笑んだが、奏希の表情は複雑なままだった。
「でも……それでいいの?」
「え……?」
「響歌ちゃんや鈴子ちゃんとは遊んでる? 学校の友達と楽しい時間を過ごしてる?」
奏希くんの言葉に、律歌は少し驚いたように目を瞬かせた。
「私は……今は奏希くんのそばにいたいから」
「その気持ちはすごく嬉しい。でも……律歌の時間は律歌のものだよ」
奏希くんは静かに律歌の手を取った。
「僕はもうそんなに長く生きられない。でも、律歌には未来がある。友達と遊んで、笑って、たくさんの思い出を作ってほしいんだ」
律歌はその言葉にハッと息を呑んだ。
「でも……!」
「律歌は優しすぎるよ。僕のことを思ってくれるのは本当に嬉しい。
でも、それで律歌が自分の時間を犠牲にするのは違うと思うんだ」
奏希の手は温かく、それでいてどこか儚かった。
「僕のそばにずっといてくれるのは嬉しいよ。でも、律歌が笑っているところが一番好きなんだ。
だから……響歌ちゃんや鈴子ちゃんと過ごす時間も大切にしてほしい」
律歌は俯き、握られた手の温もりを感じながら、静かに呟いた。
「……奏希くんは、私といると迷惑?」
「違うよ。そんなこと、絶対にない。でも……もし、律歌が僕のそばにいることで、自分の時間を削っているなら、
それは僕の望むことじゃないんだ」
奏希くんは優しく律歌の髪を撫でた。
「僕は律歌が幸せでいてくれることが、一番の願いなんだ」
律歌はしばらく言葉を発せず、ゆっくりと目を閉じた。
奏希くんの言葉は、まっすぐに彼女の心に響いていた。
「……わかった」
律歌は顔を上げ、少し寂しげに微笑んだ。
「じゃあ……明日は響歌と鈴子と遊びに行くね」
「うん、それがいいよ」
奏希くんは安堵したように微笑んだ。
――奏希くんは私が自分のことを大切に思ってくれていることを知っている。
でも、だからこそ、彼女が自分自身の人生を見失わないようにしたかった。
律歌は窓の外に目を向けた。
冬の青空が、澄み切った光を降り注いでいた。
(私は奏希くんのそばにいたい。でも、奏希くんが望むことも大切にしたい)
律歌はそっと手を握りしめ、決意を固めるように微笑んだ。